
| このページ以前の コラムはこちら |
||||||||||||||||||||
8月3日、本日は何日振りでしょうか、朝から青空です。 この2週間の間に、太陽が差し込んできたことはありましたが、「狐の嫁入り」の天候で、細かい雨の中の陽射しであったり、十数分の陽射しで直ぐに雲に覆われていましたが、本日は既に3時間以上の陽射しです。 時間の経過と共に各家庭の物干し竿には、待ち焦がれていた洗濯物が次々に登場してきます。 さて、以下の写真は8月2日のものです。 夕方、雨がひとしきり降った後、もう大丈夫と散歩に出かけました。   ↑増水した岩舟神社前の大谷川で二人の少年が釣りをしていました。 パンの耳を餌にしていましたが、あれでは釣りの成果はないでしょう。 餌のパンの耳は大物の鯉でも狙うような大きさで針に括り付けられていました。 以下は散歩道にて  ↑ムクゲの花。 ↓その万華鏡     ↑ムクゲの蕾、赤のムクゲ、そして万華鏡です。   ↑「キクのご紋」のような百日草、日照りでも・曇りでも変わらずに咲いています。 昨日はカボチャの収穫は取りやめました。 雨続きの中の収穫では、湿っぽい中身のように感じられたからです。 お隣の奥さんも、もう収穫の時期になったと思われたのでしょう、「立派なカボチャが出来ていますね」とのお言葉です。 私の家より、お隣さんの方が庭の隅の通路にありますから、気になるのでしょう。 本日は収穫しようと思います。そして、数日後に試食します。
  ↑ご覧のように、その後も蔓はドンドン伸びています。 元は二本の苗から始まりました。 東西南北、生垣や松の木に這い上がった蔓の全長は有に100メートルはおろか、200メートル以上になっていることでしょう。 本日も朝からの雨で畑の中に入り込むことはやめました。 花が咲いているのは見かけるのですが、実は一向に姿が見えません。 小さな実はつけるのですが、その後黄色に変色して腐って仕舞いました。 雨の性でしょうか。 唯一、お隣との石垣に垂れ下がっていった蔓に大きな実を実らせています。   ↑直径は20数センチあります。指先で弾いてみますとポンポンと良い音がします。 収穫時期でしょうか、日照が殆どありませんから中味のお味は如何でしょうか。 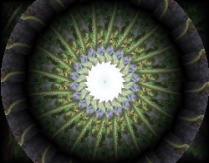 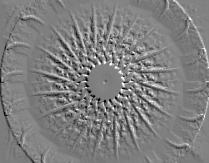 ↑万華鏡 ↑エンボス 万華鏡とエンボスで診断してみました。 多分大丈夫でしょう。 本日、夕食の一品としたいと思います。
 ↑ピンクのカンナ ↓  ↓   ↑黄色のカンナ ↓  ↓   ↑真っ赤なカンナ ↓  中部大学の今期の最終講座は20世紀で、いや今日に至るも、あらゆる分野に影響を与えた「構造主義」思想でした。 単語は聞いていましたが、その意味するところは殆ど知りませんでした。 というよりは、間違えて理解していました。 それは「全てのものには構造がある」と理解していました。 それが大間違いでした。 逆に、「全てもののには構造がある」という考え方を否定したものでした。 その具体的な例題として「虹の色」が取上げられました。 「虹の色は何色でしょう」と質問されると、殆どの方が7色と答えます。 7色と答えるのは先進国で学校教育が制度化されて、科学的に分析された結果、「紫、藍、青、緑、黄色、橙、赤」の7色に「分節化」された教育を受けているからといわれます。 即ちそのように教わり、知識として刷り込まれたからだというのです。 スマトラ島、オーストリアの原住民等に「虹は何色」と問うと「3色」と答えたそうです。 (今では、その地でも教育によって「7色」と答えることでしょうが・・・・) 彼らは「紫と藍色」の区分がなかった、同様に青と緑の区分も同様であった。 彼らだけでなく、私も現在においてすら「青と緑の区分はイイカゲンで、発言しています」 さて、結論ですが、19世紀までの文明に対する考え方は、3色に見えたものが、進歩・進化することによって7色に見えるようになったという考え方でした。 『社会が進歩・進化し、科学文明が発達し、物の考え方が厳密化され、学校教育が制度化された後に虹の色7色になった』。 では本当に「虹の構造」に変化があったんでしょうか。。 「分節化」とは、社会が進歩・進化し、科学的になって可能になったのではなく、単なる「恣意」=「約束事」であり、文明化・上級化ではない。 科学的・合理的に分析された結果を教育として教え込まれ、刷り込まれた結果「虹は7色」と答えているにすぎない。 3色に見える文明も、7色に見える文明も同じ=イコールである。 虹そのものの構造には違いはないということです。 一見異なって見えるが、どちらも「物の構造を見て・考える」ことは同じである。 生半可な知識で書きましたので、お分かりいただけたでしょうか。 以上のようなことを考えていますと、私たちの周りには同じような事柄や考え方が蔓延しているのではないかと思われます。 そのように思い込んでいるのは、自分で実験したのでもなく、体験したことでもなく、タダ単に知識として書物や聞きかじりしているうちに、刷り込まれた事柄なのではと考えます。 今、私たちは不透明感の中、手探りで不満、不信、不安な中を進んでいると感じずにはいられません。 痛みも苦労もなく、当たり前のよう享受してきたあらゆる事柄に、今ここで一度振り返り、新たな時・場・事を自らの手足で作り直す・創造するときにきていると感じるこのごろです。 それにしても、長梅雨の中カンナの花は咲きそろってくれました。 ピンクも黄色も赤色も分け隔てなく、今日も続く雨の中輝いています。 おまけ  ↑「フヨウ」の花 ↓   ↑フヨウの花に、水滴が落ちました 本日は「波動の会」で午後から名古屋・伏見へ行きます。
 ↑さて、この万華鏡はなんでしょうか? タイトルに酒のツマミの一品とありますから、「フグの刺身」でしょうか? この時期にはフグはありませんので、白身の魚の一種でしょうか? 答えを言う前に、何度もこのホームページでは紹介していますが、私は小学校を卒業するまでは、北設楽郡・豊根村・下黒川にいました。 その地は無形文化財「花祭り」の地です。 私の地区は1月元旦から「花祭りの練習」が始まり、本番は1月7日でした。 (今は、1月3日のようです。 町に出ていった方々が帰省するのに合わしているようです) その練習期間は毎日、夜食が出るのです。 集落の方々が廻り番で担当します。 その時の夜食は決まって、「マグロフレークの混ぜご飯」でした。 混ぜご飯と言っても、私の家では白いご飯など食したことは殆どありませんでしたから、毎日がご馳走でした。 オカズは殆どの場合、自家製のダイコンのお漬物です。 この「マグロフレークの混ご飯」とダイコンの漬物が絶妙な取り合わせでした。 ところで、昨日は一日中雨が降っていましたので、買い物に出かけなかったようです。 そこで、買い置きの「マグロフレーク」が食卓に置かれていました。   ビール、日本酒、焼酎と進み、中日ドラゴンズが逆転したところで、もう一品欲しくなりました。 そして食卓の隅にこの缶詰の存在を知りました。 私は夜は殆どご飯は口にしませんが、昨夜は白いご飯の上に、「マグロフレーク」を乗せ、ダイコンの漬物ならず、白菜の漬物で最後の仕上げをしました。  最初の万華鏡の写真は、皿の上のマグロフレークのものです。 フグの刺身、白身の刺身以上に、満足した夕食でした。
一般の学生とは異なり試験はありませんが、講義の中には予習=宿題があります。 この宿題も一般学生には、試験に負けず・劣らずの評価項目に入っており、提出が義務づけられていますが、聴講生は出しても、出さなくてもかまはないのですが、途中で根をあげるのが悔しくて、最後までやり遂げました。 同じ講義を受けておられるお一人の方、私が”途中で棒を折るのは悔しい”と言ったから、私も続けていると言われましたので、止めるわけにもいきませんでした。 昨夜はプロ野球の後半戦、巨人対中日戦で復習=講義の活字化は早々と中止して、BSテレビ「読売」チャンネル、首位攻防戦よろしく、なかなかの熱戦でした。 中日ドラゴンズの勝利についつい乾杯の調子があがり、ビール、日本酒、焼酎ロック、そしてウイスキーロックと相成りました。 それでいて、今朝はポリフェノールを普段同様にいただきましたから、続きの講義の活字化に手間取っています。 連日の雨ですので、外へ出る誘惑がない内に仕上げないと、記憶が更に薄れてしまいます。 教授に受講ノートの点検を依頼してありますので、早めにメール送信しなければと思っています。 小学生と同じで、早めに夏休みの宿題を終えなければと思っています。 別に宿題があるわけではありません。 それにしても、毎回感じることですが、15週の講義の後半になると、休みが待ちどうしく成ります。 そして、2ヶ月ほどの休みの後半に成りますと、又学校が始まらないかと思うのですから、「よく遊び、よく学べ」とはよく言ったものです。
今月も20人以上の集まりと成りました。 遠くはシンガポールからの参加者も居られました。  ↑集合は25日昼前後、遅い昼食と成りましたが、そのまま宴会です。        ↑3時間近くの時間をかけた「モロッコ料理」が特別提供品でした  ↑翌日は龍渕寺の「観音霊水」から始まりです、もちろん「お饅頭」も食べました。  ↑今回はこの角度から「遠山城」の撮影です   ↑寺の「アジサイ」(?)を万華鏡で  ↑「観音大杉」を今回も見上げました  ↑大杉に石(岩)が食い込んでいるということで、除去作業が行なわれていました。  ↑↓、遠山川の川原の「埋没木」、今回はお花を添えてみました。    ↑、その横で、プロの庭師による即席「石組み」(ミニ石盆栽)講習会の開催  ↑最後は「下栗の里」に上り、昼食を頂き、記念撮影で終了しました。
ご近所に昆虫が好きなお子さんがいるということで、日食騒ぎのあった日、陽が沈んでから庭に出て幼虫を探しました。 今年は例年の場所ではなく、少し場所移動したところに羽化後の抜け殻が目立ちます。  ↑5令幼虫(満5歳)が、カーテンにつかまって脱皮を始めました。 眼は初めから黒いです。  ↑体をそり繰り返しました。足の先まで抜けました。腹の先が架かっています。  ↑ 横から見た状態です。  ↑起き上がって殻につかまりながら、羽を伸ばしました。  ↑横からの状態です。 ここで、眠たくなり床に入ってしまいました。 朝までには羽が黒い色に変わります。  ↑窓を開けていませんから、逃げてゆくことはないのですが、見当たりません。 そのうちに、室内をバタバタと飛び回るでしょうから、その時に逃がします。 今夜も、見つけ出して、夏休みの昆虫観察の材料を届けようと考えています。 と言っても、撮影は私ですが、蚊の中に突入するのは、蚊に強い女房です。
我が家の狭い敷地に、大きな栗の枝は三分の一しか茂っていません。 では、後の三分の二は何処でしょうか。 そうです、一般道路(通学路)と歩道の上です。 かって、近くのお婆さんが散歩の時、日陰があって嬉しいといっていただきましたが、9月下旬になると「栗の毬」が落下して頭にでも当たらないかと心配します。  ↑、思いっきり大きい枝の剪定をして3年目、今年の毬の実は例年の3倍はあります。 このまま、台風の被害がなければ、ご近所や散歩途中の方の楽しみの一つになるのではないでしょうか。 (ご自由に拾ってくださいです) 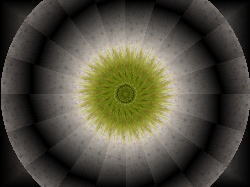 ↑栗の毬の万華鏡は、実物がそのまま反映されています。
まず、このコラム NO1063で紹介しました、その後のカボチャの状況です。  ↑今回7月20日、 ↓ 前回 7月5日  隣の畑、7月5日では(B)畑と紹介しました。↓  隣の畑、7月20日の状況です。↓  ↑2週間で、畑全体を覆い尽くす程に蔓を伸ばしていますが、既に枯れ葉が見え始めましたし、葉全体の色に力強さがありません。 同じ種で、同じ肥料を施しています。 一番の違いは「BMD土地改良プラス・アブラカス」を撒いたのと「万田酵素」を散布をしてきたことです。 夏野菜、人参、ダイコン、ジャガイモ等の収穫の内容を見ていますと、他の畑との違いがでているように感じます。 これからの秋〜冬の野菜作りではっきりすることでしょう。 ↓その該当する畑はご覧の通りの状況でした。   ↑朝は前夜の雨で、草は湿ったいました。 草刈をして、その葉をサトイモ畑に敷き藁の代わりとしました。   ↑ Iさんに運転指導、若い方の飲み込みは早いです。  ↑午後4時にはご覧のようになりました。 8月8日か9日には、第1陣の種まきを予定しています。
7月17日、「NO1070」で、どこまで伸びるカボチャの蔓を紹介しました。 その時は、外壁と生垣を伝わる姿を紹介しました。 外壁塗りの工事終了のままでしたので、狭い庭中が十種以上の園芸の鉢や支柱、傘立てやその他様々が散らかり、梅雨空の下一層暑苦しく感じていました。 一番目立つところを整備すると、松の木に絡まった「カボチャの蔓」がうっとおしい。 根本から切ってしまおうかとも思ったが思いとどまる。 今暫し、どのような展開になるか眺めることとしました。   ↑松ノ木どころか、数メートル離れた黄金ヒバの天辺までつたい昇り、頂上を極めた蔓の先が、「さて、何処に行こうか」と蛇の頭のようにブラブラと揺れています。 このカボチャの向こうに、夏野菜のナス、キュウリ、トマトがあります。 陽射しが心配ですが、ナス、キュウリは順調に収穫しています。 赤くならないというトマトを一つ収穫して、食べてみましたが、酸っぱいことはありませんでしたが、後、数日強い太陽光線が欲しいところかと判断しました。 この地は皆既日食ではありませんが、青いトマトの味がどのように変化するのでしょうか。 それにしても、元気の良いカボチャさんはどのような実を付けてくれるのでしょうか。 COLUMN 1−D 1071 平成21年7月18日 ・記 |
||||||||||||||||||||
それから8ヶ月が経過しました
|
||||||||||||||||||||
| 以下の写真は、2008年11月8〜9日「遠山郷・藤原学校」の秋の紅葉見学の時に、拾ってきました落ち葉です。 2008年 11月10日 (自宅にて) 拾い集めてきた落ち葉を撮影しました。 この後は「押し葉」にしようかな。         1ヶ月前に、「押し葉」にしていました冊子を手元においていたのですが、大学の予習・復習に追われて、本日まですぎてしまいました。 今日は百姓学校の日ですが、生憎の空模様で日延べしましたので、「押し葉」を取り出しました。      あの紅葉の色鮮やかさはありませんが、落ち着いた色合いは良いものです。 今の遠山郷は緑濃く、力強い木々が連なる南アルプスの連山が夏休みの人々を待ち受けていることでしょう。 と言っていましたら、行きたくなりました。来週末にでも出かけようかな。 |
||||||||||||||||||||
| 前のページはこちらからどうぞ |