
| このページ以前の コラムはこちら |
||||||||||||||||||
この散歩道は月に1回か2回下ります。 中仙道の岐阜県・瑞浪(釜戸)から、江戸時代・大名の使った中仙道・本街道から「下街道」という庶民・商人の利用した道に分岐し、名古屋の熱田の渡しから桑名にに至る街道です。 岐阜県多治見市から内津峠を超えた愛知県側の内津・西尾でさらに分岐して、これまた江戸時代の愛知県瀬戸市の水野代官所に通じる「玉野街道」に沿って流れているのがウグイ川です。 庄内川に注ぎます。 なんども登場します愛岐3山の弥勒、大谷、道樹山から流れ降りた沢水が集まってウグイ川となります。 私の住む高蔵寺ニュータウンが開発されて40年、10年前まではこの街道に沿ってJR(国鉄)バスが走っていましたが、今はニュータウンの外周にのみを名鉄バスしか巡回していません。 ニュータウンが開発されるまでは、「玉野街道」に沿った集落の方々の里山でありました。 マツタケが良く採れたそうです。 今この街道は殆どが車で生活道路として活用する人しか利用していないようで寂しい限りです。道路の両側には針葉樹と雑木が生い茂り、所によっては日中でも暗く寂しいところもあります。 その道路で雑木に絡みついた蔓の先にアケビがぶら下がっているのを発見しました。  → → 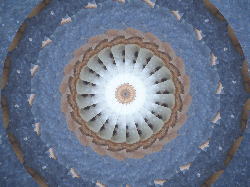 ↑1ヶ月ほど前に、「植物園のアケビ」を掲載しましたが、この野生のアケビは大きさも、色艶もまったく異なります。 蔓を手元に引き寄せてやっと2個もぎ取りました。 手の届かないところに、あと5個の存在を確認していますので、本日いただきに上がろうと思っています。 脚立でも持ってゆくのかな・・・・? 甘いものを口にすることはできなかった50数年前は、山の秋の魅力的な果物でした。 残念ながら、子供の私たちにはなかなか見つけ出し、手にすることは出来ませんでしたが・・・。今は種ばかりで美味しさと言うよりは懐かしさです。  ↑大きく川が蛇行しているところは、田圃の適地です。 刈り取られた稲が小さなハザに架けられていました。 この連休で全ての田の稲の収穫が終わることでしょう。
 ↑台風一過後の築水池と弥勒山(429メートル)  ↑ザリガニが散歩道の真ん中を後ずさり(彼はこれが正常の歩き方か)  ↑カメラを近づけると、ご覧のように鋏を開き、両手を広げて威嚇してきました。   ↑それほどの被害ではありませんが、刈り取り前の稲が倒れています。  ↑5年前、大谷川の土手に植樹した10種の木々の内、柿が初めて実をつけました。 「桃・栗3年、柿8年、梅はスイスイ11年」とかいいますので、移植した時が3年生だったのでしょうか。 この時期、この柿色は土手の真ん中で一際存在感があります。 爽やかな秋晴れが続きそうです。 大好きな季節です。
昨夜、床に就く前に家の周りを懐中電灯を照らして一周し、風に飛ばされそうなものを片付けました。 その折、一度も蜘蛛の巣に引っ掛かりませんでしたので、蜘蛛は早々と退散してしまったのか、それとも風に吹き飛ばされたのかと思いました。 明け方、外の様子は分かりませんが、風の音と雨音から判断して近くに上陸したなとラジオのスイッチ・オン、『知多半島に上陸し、今愛知県内を通過中」と報じられた。 雨の中、新聞受けに。 特に大きな被害が報じられていない。 午前9時、風が治まり、雨も霧のようになった。 さて、蜘蛛の巣はどうなったか。 二つの蜘蛛の巣を除いて、他は影も形もありません。 残っている二つの巣も、大被害です。 昨日の大きさの5分の一程度に縮小されていますが、中心部は残っており、そこで早くも修復作業が始められていました。 ところで、平成21年のこの秋から、来年の夏に向けて、世界と日本の金融関係、経済の縮小・倒産、それが家庭生活にまで及んでくると予測しています。 一時のガマンと対策で通過を辛抱する台風とは根本的に異なると考えます。 どのような状況になるのかは予測できませんが、どちらにしても今回の台風の通過に見せた我家の庭の蜘蛛とその巣作りと同じように、そのときには次に向かって行動しなければと教えられました。
明日の未明にも東海地方に接近・上陸の可能性があるという台風18号。  ↑庭の苗床に水遣りに行くと、頭やら顔に巻き付いてくる蜘蛛に閉口します。 ここで、充分に栄養を補給して冬眠となるのでしょう。 何度、破り・破壊しても同じ場所に巣をかけます。 特に今年はその数が多いように感じます。 それにしても、今度の台風が我が家の近くを通過したらどのように対処する積りなのでしょうか。 確かめたくて、台風よ近づけなどと思ったりします。  → →   → →  早々と2階の雨戸が半分閉められています。 豊橋に住んでいたころには、雨戸の上から斜交いの板やつかい棒を打ち付けていましたが、今はそんなことをする家はこの辺では見かけません。 今年は伊勢湾台風から50年、大きな災いを招く台風にならねば良いなと念じています。
ここ数年、書物はインターネットの通信販売で購入しています。 しかも、殆ど中古品で購入しています。 それは、「はじめ」と「終わり」そして、目次を読んで、気になるところだけの拾い読みだからです。 もう一つ、手元に入った書籍には、ドンドンと線を書き込む、汚しまくるからです。 昨年の教科書で何度か読み直さないと文意が理解できず、しかも、A3一枚の紙に要約しなけらばならなかったときは、初めは黒エンピツ、次に赤鉛筆、そして蛍光ペンでアンダーラインを入れるのですから、中心ページなどは線だらけでした。 さて、昨日手元に入った「昭和史・戦後編」も、数ページで睡魔に襲われるだろうと予測しましたが、エンピツで線を入れながら、意外と100ページ以上も読み進みました。 それは話し言葉が活字化されていることで読みやすかったことにもよりましょうが、記憶としては確かではなくとも微かに覚えている事柄や父親・先輩から聞かされていたことが展開されていたからでしょうか。 その中の一つに、昭和20年11月9日の朝日新聞に当時40歳の作家、石川達三さんが書いたものが紹介されていました。 「日本に『政府』は無いのだ。 少なくとも吾々の生存を保証するところの政府は存在しない。 これ以上政府を頼って巷で餓死する者は愚者である。・・・ 経済的には無政府状態にある今日、吾々の命を守るのは、吾々の力だけだ」と。 この一文を読みながら、何を考えたのか私の両親は家族を引き連れて、昭和20年7月6日に豊橋から愛知県・北設楽郡・豊根村・古真立に疎開(?逃げる)したことを思い出しました。 そこでの生活は大変なもので、今も思い出すのはサツマイモの粉で出来た饅頭が食事です。 苦くて食べれたものではありません。 口イッパイに頬張って、家を飛び出し吐き出したことです。 その後、古真立から豊根村の銀座(?・役場の所在地)に移り、昭和29年3月、豊根村・黒川小学校を卒業したことは、何度もここに書きました。 話はそこから、飛びます。 今年の夏の衆議院選挙です。 既にこのページで書いたことですが、不透明感極まりない世相にあって、不信、不満、不安の”3不のマグマ”が遂に爆発して、政権交代と言う結果を生みました。 では、これで暗雲が晴れて光が差してくるのでしょうか。 世論は政治に対してそれほど甘く期待はしていないようですが、それでも今までよりはどうにかしてくれるのではないかとの思いを抱いていると感じないわけにはいきません。 このところ金融が安定してきた、アメリカの経済も落ち着き始めている、株価ももっと上を望めるようになったと書き立てる人たちは、本人はそのように考えていず、何も知らない庶民にマタマタ不良債権・投信等をつかませて、逃げ延びようとしていると思っています。 基本的に、自然の意に逆らった考え方で作り上げてきた、仕組みや制度、ルールは一度ご破算し、願いましてはとゼロに戻さなければ、新たな時代のスタートは切れないのではと感じています。 と言っても、昭和20年8月の爆撃や焼夷弾によって生産現場が破壊された状態ではなく、一人ひとりにとっても住む家はあります。 周りを見れば、緑の野山が広がり、蛇口をひねればそのまま飲める水がジャブジャブと流れ出てきます。 なんと、恵まれた状況ではないでしょうか。 夢や希望が失われ、これからは暗く・冷たい時代の到来などとは思えないのです。 視点を変えて、何が本当に必要なのか・大切にするものかを見直して、行動を改めれば、心安らかな明るく・温かい夢と希望に満ちた世界が展開される前夜と感じています。 ただこの時、自戒していることは「人頼り」はダメということです。 誰かがやってくれる、悪いのは他人だと言う精神からの脱却です。 昭和20年11月の石川達三さんの一文「政府は無いのだ」とまでは申しませんが、それと同様な環境・状況がこないとも限らないと腹を括っておく必要はありと言い聞かせています。 本日、日本の明治維新とそれ以降を分析した「日本資本主義分析」の岩波書店の文庫本が手元に届きました。 斜め読みしましたが、これは途中で棒を折りそうですが、「昭和史・戦後編」と併読することによって、近時日本の歴史からこれから、試行錯誤してゆく日々に対して大きなヒントを与えてくれるのではないかと思っています。
 ↑今年、庭のウメモドキは、実が例年の3~5倍はつきました。 もうすぐ、お山の木の実がなくなると、野鳥が飛んでくることでしょう。  → → 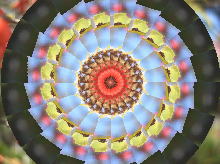 ↑予想どうりに、綺麗な万華鏡となりました。空の青が入っていると綺麗です。  → →  ↑どちらかと言うと「嫌われている」セイタカアワダチソウもご覧のようになりました。  ↑刈り取り前の稲穂に自分の影を・・・  ↑愛岐3山の山並みを背景に、植物園のコスモスを配置してみました。 今日の午後は雨模様とのこと、大学の宿題の参考書が届いています。 600ページ近くもあります。 数ページ読んだところで多分、昼寝になることでしょう。 「昭和史」・戦後編 半藤 一利です。 何年も前から「遠くなりにけり昭和」と言っていましたが、8月の衆議院選挙で最後のダメ押しをしたように感じていますが、それでも色々な方がいるもので、まだ、過ぎ去った、戻ってくることのない懐かしき高度成長を含んだ昭和の幻想を語る方もいます。 それも善しです。 それぞれの方が自分の思いや考え方でこれからの時代を生きてゆくのでしょう。 2日間続いた秋晴れの後に、静かな秋雨が降り始めるとのことです。
、 10月3日の午前中は東高森台小学校の創立30周年と運動会の撮影に。 そして、午後から名古屋・伏見で<波動の会>で午後の2時から飲み始めました(毎度のことですが・・)。 12階のマンションに階下から華やかなマーチ・バンドの音楽が聞こえてきました。  ↑「名古屋祭り」です。 英傑行列もあるようですが、メンバーとの会話に花が咲く。 その後、このところ定例になっている行きつけの居酒屋で盛り上がります。 先月は「スクナカボチャ」を持参し、料理をしてもらいましたが、今回は「飛騨金山の栗」を持って行きました。 マンションの部屋で充分に頂いた為か、ここでは箸が進みませんでした。 10月3日は久しぶりの晴、そして本日10月4日はさらに雲ひとつない快晴です。  → → ↑10月2日、撮影のアサガオの種です。 →意外な万華鏡への変化に見とれました。  ↑10月2日、雨の中での撮影。メキシカン・ブッシュセージです。 花の名を初めて知りました。サルビア・レウカンサとも言うそうです。  → →  ↑10月2日、雨の中のメキシカン・ブッシュセージ  → →  →10月4日、快晴の空の下のメキシカン・ブッシュセージ 日中の気温は28度まで上がるとの予報ですが、気持ちいい秋晴れの朝です。
壁あてキャッチボールをしていると、普段見かけない方々と朝の挨拶です。 普段はまったく見かけない方々です「孫の運動会で名古屋から着ました00です」 「今日が最後の運動会となりました」と、何時も散歩ですれ違う方の挨拶。 御両親ともが学校の先生、珍しくと言うよりは初めてご一緒に歩いているのを見かけました。 上のお子さんは確か高校3年生、一番下のお子さんの運動会でしょう。     ↑まず、創立30周年記念の式典です。 最高時は児童が700人を超えていましたが、今は200数十人です。   ↑ビオトークを改修して、除幕式を行ないました   ↑愛岐3山の道樹山、大谷山の自然に囲まれた環境の運動会の始まり   ↑30年前にはなかった風景です。この下で楽しい昼食を取ることでしょう。    ↑最後まで競った力走に、来賓席から拍手が沸きました。
 ↑あと、10日で稲刈りでしょうか。  ↑夕陽もスッカリ、柔らかくなりました  ↑遅咲きの彼岸花が、夕陽に映えていました。  → →  ↑ピラカンサの実もスッカリ赤くなりました、ヒヨドリの飛来も間近でしょう。   ↑雨戸を閉めると、カマドウナが飛び込んできました。 シーツの上で、身丈の10倍、いや20倍ほど飛び上がって驚いていましたが、陽に干した シーツが気持ちよかったのでしょうか。 しばらく休んでいました。 手にとって、夜陰の庭に放ってやりました。 COLUMN 1−D 1121 平成21年10月1日・記 |
||||||||||||||||||
飛騨金山に二回目の栗拾いに
|
||||||||||||||||||
| 天気予報を調べると、明日からは又雨模様、しからば、本日しかないと出発。 前回は右折すべきところを見損なって山の中に入り込んでしまった。 本日は気をつけていると、目印にしていたお店の看板が替わっていたことに気付きました。 飛騨金山に行く時には殆ど「道の駅・美濃白川」に立ち寄ります。 今年で15周年となりましたと大きな横断幕が掲げられていました。 道の駅が出来て1年後に、田舎道一本を隔てて、地元の方の新鮮野菜販売場所が出来ました。 当初は出品者も少なく、購入する商品も貧弱でしたが、年を経ることにその品数が豊富になってゆくのが分かりました。 今では野菜ばかりでなく、地元で取れる材料を使って弁当やオハギ等様々なものが出品されています。 その道の駅を紹介する積りはありませんでしたので、写真は撮ってきてありません。 が、帰り道がコースを代えて、「道の駅・平成」に立ち寄りました。 こちらも地元の方の直売所が5年ほど前にオープンしましたが、営業日は水と土曜日の二日間です。 が、お隣の「蕎麦の店」は大変美味しいので、立ち寄ることにしています。 蕎麦は地元の蕎麦倶楽部の方々の生産と経営・営業のようです。  ↑道の駅・2店舗で籠の中に入った食材です。 白い袋は新米です。3Kg・1400円のコシヒカリ。これは初めて購入で味は分かりません。 夏野菜はキューリ、ナス、ゴーヤ、トマト。 秋野菜はインゲン、マコモタケ、ズイキ、サトイモ、原木栽培のナメコ、ネギ、大根の葉 その他、シソの実に漬物、地鶏の卵、露地栽培の菊の花。米を除いて、3000円でした。 それにプラスして栗約10Kg、と栗の木の下のミョーガが加わりました。 以上の品を全て、自分達で作ることは出来ませんが、私たちの畑にも大根、ニンジン、ネギ、赤カブ、白カブ、小松菜、ホウレンソウ、白菜、サトイモ(試掘り)が10月10日に収穫できます。 他のモノを生産されておられる方と、物々交換しようと思っています。 それらを寄せ集めれば、写真の品々とも劣らないと思います。 |
||||||||||||||||||
| 前のページはこちらからどうぞ |