
| このページ以前の コラムはこちら |
||||||||||||||||||
書斎から眺められる道樹山の緑も、心なしか色付き始めました。 数日前まで、放たれていた金木犀の香りも弱まり、今朝は色あせた金色色の小粒な花が地面に散らばっています。 イチイと金芽ツゲの組み合わさった垣根の間に、タイ産の置物の上で、既に1ヶ月以上も咲いています「オンシジューム」が目立つようになりました。 ↓  今夏の南米の旅の時に購入してきましたCD、「アンデス パン フルート」のロマンチックな調べを聞きながら、昨日までの大学の講義の復習に入ります。 「中国の近・現代史」と「日本の戦後思想の変遷」です。 大きな時代の転換期にある今、 「転ずる」とは、どのようなことか。どのように展開してゆくのだろうかと、時折パソコンに入力する手を置いて”ボーヤー”としています。
 ↑9月30日の散歩時、宮滝大池の放水口の鯉、鮒 この時、「大変革期は”大魚は生き残れないのか”と書きました  ↑3週間後の同じ場所は、ご覧のようです。 この間、カラスや青、白サギが飛来している姿を遠目に見かけましたが、近づくと逃げてしまいました。 そして、昨日のことです。同じ場所は大魚の姿は無く、元の放水口になっていました。 食べられたのでしょうか、それとも腐って地中に還っていってしまったのでしょうか。 自然の循環はこのようなものなのでしょう。  ↑ご覧のように3〜5年で、池の総ざらえされた状態です。 時に、全てが大浚えされて、再び田畑を潤す水が蓄えられてゆきます。 人間の構築した池はこのような頻度でですが、自然が展開する大浚えはこんなものではないことでしょう。  ↑散歩から帰って来ると、わが町の空は茜色でした。 本日は名古屋駅の百貨店のレストランで、30年前に入社してきた新入生と食事をしました。 その彼女も既に50歳を超えました。 息子達もそれぞれに成長られ、それぞれの道を歩んでおられるようです。 彼女自身も多才な才能を持っており、各方面で活躍しているようです。 が、2^3年、時には5年ぶりに連絡があり、その度に食事をして、お話しています。 経済的には何の問題も無く、いやそれどころか豊かな層にランクされる状況であると思いますが、何か物足りないというか、「これでよいのか、このまま月日を過ごしてよいものか」と自問した時に、連絡が来るように感じています。 今回も特にどうの・こうのという事ではありませんでっした。 私には幸福病というか、贅沢病とも思いましたが、金銭的・生活的には何にも問題が無いのですが、人間はまさに”物が満たされていれば良いと言う問題でない”と言うことでしょう。 3時間もの時間、彼女の一言、二言の疑問や質問に私の体験、意見を語るという毎度のスタイルでした。 体力の気力があり、平均睡眠時間は3~4時間と言っていました、私には考えられない日々を過ごされています。 「三不=不信、不満、不安」のエネルギーが爆発した、8月30日の「市民革命」。 「極まる時が到来するまでは、本当の変化は起こらない。 そのときのため、「今と言うときは、試行錯誤のとき、留まっていては、必要な時に体が硬直して動かなくなってしまうから、常にジャブを出していること」。 などに、反応していたように感じました。
幾つか在る散歩道の中でも一番利用させていただいているコースから少し横道に入りました。  ↑愛岐3山・弥勒山と大谷山から流れ落ちる沢水を集めた内の一つの水路からです。 どんなに日照りが続いても年間この管の水が絶えたことを見たことはありません。 400メートルを少し超えるだけの山ですが、それなりに整備されているから、保水力があるのでしょう。 (県有林で、ボランティアの方々も活躍しています)  ↑廻間町の稲刈りも終了しました。 最後の田圃は「古代米=赤米」の田圃でした。 この写真の稲刈り機は中ぐらいです。 もっと大きな機械も導入されていましたが、年間何日稼動するのでしょうか。 70代の親と40代の息子が手際よく脱穀を終えて、夕陽に照らされた家路を帰って行きました。 白鷺が飛び降りてきましたが、撮影は失敗しました。  → →  ↑ 時期外れの八重のヤマブキが大谷川の土手に、パラパラと咲いていました。 今朝はこの秋一番の冷え込みになりました。 開け放った室内の気温は14度でした。 それでもストレッチを終えた頃には、微かに額に汗が滲みました。 今日も素晴らしい秋空が望めそうです。
昨日は百姓学校の「稲刈り」でしたが、朝から一雨来そうな雲行きでしたので、出かけるのを見合わせました。 結果はオーライだったのですが、稲刈りは出来たのでしょうか。 今年の春の田植えはお手伝いしましたが、別のグループの田圃で直接参加しているわけではないので、腰が引ける状況です。 本日(18日)は晴天ですので、秋空の下、子供たちを交えた稲刈りが進行していることでしょう。 自宅の遅蒔きの大根が抜き菜に良い大きさになりましたので、今夜の夕飯の一品が出来そうです。 今年は大根を4回に分けて種を蒔きました。 抜き菜を茹で塩で揉み、ご飯に乗せて(混ぜて)頂くのもよし、油炒めにすると、丼イッパイ食べてしまいます。 翌朝は便通よろしく、お腹スッキリです。 採れすぎた時などは、どうしようかと贅沢な悩みもあります。 御近所にお裾分けしていますが、若いお母さん達には料理の仕方を伝授しなければなりません。 野菜ではありませんが、先日のアケビ(開け実)はどうしましたかと尋ねると、そのままにしてありますと言う、50代のお父さんも体験が無いとの事でした。 特に美味しいものではありませんが、私には懐かしく・思い出の甘い山の果物でした。  ↑この辺りで、一番大きな金木犀が四方3〜40メートルに放香しています。  ↑地上25メートルからの眺めです。 稲刈りは終了していました。
世界情勢や内外の政治・経済・社会のことについては、それなりに関心を持って勉強している積りですが、このところ悪友からの助言と言うか批判や挑発がめっきり減少したのでそれらのことに言及する機会が減りました。 と言うよりも、自然の草花や木々に目が奪われることの方が気持ちよいからでしょう。 ところが、昨日手元に届いた情報から、このコラムに目を通していただいている方にお知らせしておいた方が良いかなと思う情報に出会い、入力しています。 その内容というのは「ドル暴落の鐘は鳴った」と言うタイトルで10月15日に届きました、月2回の情報紙なのですが、次の日・即ち16日付けで緊急情報が入ってきたのです。 そのタイトルは「円高で、為替仕組み債が破裂(破綻続出へ)」です。 その中に「今、日本国として、全てのデリバティブ契約無効を宣言すべき」と書かれています。 その事を論理的には説明する能力はありませんが、2ヶ月ほど前に中国が国家の意思として、デリバティブ契約の無効を宣言したとの新聞報道を読んでいました。 その意味は、損失が確定したら、商取引として損金は払わないと言うことであり、無茶な宣言をしたものだ、そんなことでGNPが世界第2位になろうという国に許されることだろうかと考えたものでしたが、よそ事でした。 しかし、このデリイバティブ契約については、昨年来、大阪産業大学や、駒澤大学、慶応義塾大学、早稲田大学、更に経団連や地方の自治体、地方銀行、幼稚園まで損金を出していることと同じと考えると他人事とは思えなくなっております。 経団連でも、各大学でも経済・金融の専門家が存在しながらの実態なのですから、この仕組みに隠されたテクニックは凄いものだと考えざるを得ません。 『すべては日本国民から巨大な金融資産を巻き上げる為の施策=(仕掛け)』とあります。 自分の事として考えました。もちろんデリバティブ取引などはしていませんが、思いもしない円高になった時、老後資金として虎の子の資金を海外投資している資金はどのようになるのだろうと、自分事になりました。 平成15(2003)年2月の時点での対ドル円は119・50円でした。 このところ対ドル円は90円前後ですので、少しばかりの金利や配当があったも、25%ものドル安(円高)では、目減りばかりです。 これ以上の円高、しかも超円高(想像を絶する)となれば・・・・資金は半減、いやゼロです。 ここ数ヶ月、世界経済は落ち着いた、金融危機は去った、株価は持ち直しているなどの情報が目に付きますが、果たしてどうなのでしょうか。 私は懐疑的ですので、大概の事件や状況には驚かないでいる積りですが、上記の情報を手にし、やはり新たな時代へ移行の為には、いまひとつ私たちにこれまで以上の試練を与えてくれるのだろうと気付かせ・考えました。 と言うことを思いながら、昨夜、床に就きました。 そして、今朝こんなことを思っています。 自公政権で成立した補正予算の見直しが新政権の下終了しました。 首相官邸は2・9兆円削減と、報道されていた3兆円に迫った事で安堵しているようですが、各閣僚には不満が残っている様子です。 自公政権を批判してきた民主党議員=大臣もシブシブは飲み込んだものの、次にくる平成22年度の予算編成ではその反動が予測されます。 根本的に国のあり方を改めるには、大きな波をかぶる必要があるように思えてなりません。 それなくして、抜本的な改革は始まらないのでしょう。 何度も発言していますように『3不ー不信、不満、不安』の心理が生んだ「市民革命」の本年8月30日の衆議院選挙の結果でした。 江戸幕府から明治維新、あるいは昭和20年の敗戦という外の力による変革・改革ではなく、自ら、しかも平和裏に行なわれた選挙による市民革命が起きたことに、日本は捨てたものではないと感じさせてくれ、嬉しかったです。 が、と言うものの今、時代の転換期のトンネルの向こう側の社会や生活についての価値観や具体的な映像が、政治家・経済人・学者・マスコミ共に描かれていないように感じます。 もちろん、私とて同じことです。 できることなら、事が極まる前に次の準備と試行錯誤の行動が始まればと思っているのですが、どうやら行き着くところまでいかないと、事柄は始まりそうに無いと、時を過ごしている感じです。 数日前、「では、加藤さんは”ドスンとくるまで仕方ない”と言うが、”そのドスンとはどのような状況か”」と問われました。 そのことに対して、「世界的にも、日本においても再び金融の混乱にみまわれ、崩壊するのではないか。 その結果、産業は行き詰まる・輸血すら出来ない。 結果、生産現場の崩壊でそこで働く人々の生活の維持が不可能になる」と言いました。 もちろん、生産現場、生活現場が物理的に崩壊・破壊されるわけではないので、意思さえあれば、そこから再生が始まります。 その再生は昭和時代やその延長の考え方や価値観では、多くの賛同を得られない。 新たな見方、考え方のもと、新たなリーダーのよって創出される。 今はその環境や条件を満たす為の必要な時間であるのだろう、と考えています。 本日、久しぶりに「コラム2−N 新聞を読んで、眺めて、切り抜いて」に書きました。
 ↑植物園前の道路に沿った「ケヤキ」が色付きました   → → 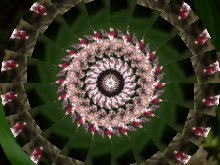 →ホトトギスが咲きそろい、家の中のアチコチの花瓶に挿されています。 何故、この時期に「ホトトギス」というのかなと思っていましたら、昨夜のテレビでホトトギスの胸の斑点と良く似ているからだと教わりました。 毎年、この時期にプランターに定植される「サクラ草」の姿が見えました。 寒い冬を越して、新入生の通学路で出迎えます。 次回に、現在の姿と今年の春、咲き揃った状態を掲載しましょう(探し出せません)
10月10日、このコラム・No1130で取上げました、「ウグイ川を下る」の「アケビ=開け実」の場所に再度行ってみました。 蔓を引っ張り・手元に引き寄せましたが、どうしても数十センチメートルが足りません。 自宅に引き返しました。 その間に、どのような手立てをすれば良いか考えました。  黒竹の先に、鎌を結び付けました。 アケビの実は斜面角度60度以上の雑木の木に絡まっています。 家の前の夢実ちゃんに出会いました。 「蝉か蝶を採る網は無いか」と尋ねました。 「物置に在るのではないか」と、そこにお母さんが帰ってきました。 数分後、写真の網が届きました。 再度、アケビの所に行きました。 ご覧のとおりの収穫です。 と、簡単なようですが、斜面角度60度に在るアケビは簡単には手にすることは出来ませんでした。 鎌で切り落としたアケビが網に入らずに、斜面を転げ落ちて行きます。 急斜面を降りて拾いに行きましたが、落ち葉と同じ色のアケビは見分けがつきません。 ズルズルとウグイ川に落ち込みそうになりました。 夢実ちゃんに届けました。高校3年生の姉さんもアケビのことなど知りません。 お父さんが帰ってきたなら、食べ方を教えてもらいなさいと言ってきましたが、そのお父さんが果たしてアケビのことを知っているでしょうか。 私は神棚にお供えしました。  ↓  ↑素晴らしい万華鏡になりました。 子供の頃、手にすることの出来なかったアケビ=開け実 種ばかりのアケビの実の上品な(?)甘さが、食べなくても口イッパイに広がりました。
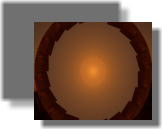 ↑ 夕陽の万華鏡  我が家の金木犀が香り始めた。 よそ様の金木犀の香りを認識してから3週間ほど遅れである。 日記を開いてみると、我が家の金木犀は例年10月上旬でしたので、1週間ばかり遅れたことになるのですが、やっと来たのかとの思いです。 しかも、香りが例年と比較して弱く感じます。 今夜は窓を空き放ち、忍び込む金木犀ではなく、「良くおいででした」と歓迎しよう。 「ひやおろしの酒」で、お迎えしよう。 上弦の月もすぎたが、弱い薄明かりも雰囲気を盛り立ててくれることだろう。
 ↑年寄りの冷や水になるからどうしようかと思いながら・・・ 11日息子が参加している、瀬戸のチームの試合を下調べに行きました。 60歳以上のクラスがあるそうです。 草野球とはいえルールは厳しく、所属チームのユニフォーム着用はもとより、スパイク、帽子など全て揃えなければ球場に入ることすらできません。 1試合半みなしたが、やれば何とかなりそうと思いました。 息子もその投げっぷりならOKと言っていましたが、さてこれ以上手を広げると時間の制約を受けそうなので、思案中。 帰宅して、午後からは春日井植物園で開催されている、第2回「高蔵寺フォーク・ジャンボリー」を覗きに行きました。 ”大人の学園祭”とのサブタイトルが付いています。 誰でもが参加できると言うのではなく、今年の夏にオーデションがあって、勝ち抜いたアマチュア演奏者たちです。 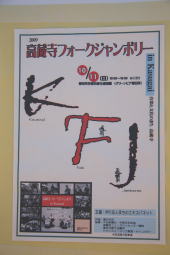    ↑メインステージです。 バック・パネルに大きな筆で「楽」と言う字を書き上げてオープニングが始まったようです。 書の町・春日井ならではで、海外でも活躍されている春日井在住の新進芸術家、波多野明粋さんの作品です。    ↑カナール(運河)の両側は様々な出店で、普段とまったく変身してしまいました。   ↑小さなお子さん連れや子供たちは紅葉を始めたケヤキと桜の下で、はしゃぎまわっています。 おじいちゃん、おばあちゃんはマットの上で眠っていました。   ↑秋のバラは数は少ないですが、深みある色に影を入れて見ました。  ↑事務所棟では「紙粘土」の展示も開催されています。  ↑メイン、サブのステージには団塊の世代以下の年齢層の方々が大半です。 こちらは「グリーンピア」(温室室内)の会場です。   ↑、そこでは、ハーモニカ演奏やシャンソンが歌われていました。 「まちのエキスパネット」が主催する市民手作りの参加型イベントです。 歌以外でもボランティア参加されている方々の立ち振る舞いや笑顔に触れて、まさしく秋晴れの一日を過ごさせていただきました。 COLUMN 1−D 1131 平成21年10月11日・記 |
||||||||||||||||||
10月9日の農作業
|
||||||||||||||||||
 ↑9月23日、色付き始めました。  ↑10月10日の紅葉です。(同じ紅葉です)  ↑小松菜と水菜です  ↑ ご覧の出来映えです 今・秋〜冬の野菜もおかげさまで豊作となりました。 校長に「私の管理する畑については、口出ししてくれなくて結構です」と、偉そうなことを言って殆ど指導、助言を貰わず実行し始めて4年目になります。 10年前から始めた生徒は皆卒業して、昨年はまったく一人でした。そして2週間に一度畑に行けば、一番悩む真夏の草にも負けずに収穫までこぎ着けれることが実証でき、自信を持ちました。 今年からは研修生というか、息子の友人とその又友人と新人を従えての作業となりました。 特別な思いは持ちませんでしたが、可能な限り毎回お土産を持たせたいものだと考えました。 夏野菜は殆ど誰でも間違いないでしょうが、秋〜冬の野菜はそんな訳には行きません。 事実、同じところで他のメンバーも実施していますが、色々と苦労しています。 今回も殆ど誉め言葉を言わない校長ですが、”やっぱり、10年の年季は伊達ではないな ”と一言です。 また、上記の小松菜と水菜はリッパに出荷可能と言われました。 この、小松菜、水菜はまだ抜き菜です。 2週間後の本番の収穫はどのようになっていることでしょう。 他のグループの方に、どうぞお持ちくださいと声を掛けて置きました。 11日にその方が友人とサトイモ堀に来るそうで、「そのとき頂きます」と言っておられました。 頂くのも良いですが、「どうぞお持ちください」と言うのも、気分良いですね。  ↑全て、抜き菜のレベルですが、大根、白カブラ、赤カブラ、ニンジン、サトイモと根物も順調です。 昨夜、食べてしまったので、ほうれん草、と抜き菜の大根の姿が見えません。 と言うことで、豊かな実りの秋を堪能しています。 |
||||||||||||||||||
| 前のページはこちらからどうぞ |