
| このページ以前の コラムはこちら |
||||||||||||||||||||
ここ数年、この時期になりますとタダでも狭いリビングが更に込み合ってきます。 それは、庭に出ていた観葉植物がリビングに持ち込まれるからでした。 組み立て温室を百姓学校で利用しようと購入したのですが、取りやめになり私が引き取りました。  この手の作業はどちらかと言いいますと苦手なのですが、何時までもほったらかして置くわけにもいかず、本日組み立てに取り掛かりました。 出来上がってしまえば、もっと簡単な手順もあったなと感じ、「もう一組挑戦すれば・・・」と思っているところです。 ところで、冬場は結構重宝され感謝されることでしょうが、夏場はどのようにしようかなと早くも来夏のことを心配しています。
 ↑ この瑞々しく、気品ある(?)色合いから何を想像されますか? 一夜明けた食卓では、このように↓お色気がつきました。  このまま、種明かしをしては面白くありませんから、雫を落としてみました。   お答えはあと数行下に表示されます。   ↑3日前に収穫してきました、ミニ大根です。 昨夜、晩酌の食卓に「スパッツをはいた若い子が晩酌のお相手です」とのこと。 「余りにもそのものではないか。パンティー・ストッキングぐらいははかせよ」と言いましたら、 赤い腰巻の彼女が本日の朝食ポリフェノール(赤ワイン)の相手をしてくれました。
 ↑朝は陽が射していたが、2時限目の講義室への移動の時には、曇り空となっていました。 この紅葉も、一雨くれば散ってしまうことでしょう。 本日の講義「日本文化比較」の中で、「良妻賢母」という単語の出所のことが語られた。 私の認識は儒教から来ており、良き妻であり、良き母でした。 明治時代になって、特にアメリカの女子大学に留学した若い女性は、この大学に流行した育児観と女性教育観を受容した。 これは1890年代の日本に作った「良妻賢母」という女性教育に関する理念に強い影響を及ぼした。 儒教の思想は、女性の男性に対する服従が社会の秩序を守る為には重要な道徳であった。 家庭内の女性の役割において、家風を知らない「嫁」は基本的によそ者と考えられ、日本の伝統的なエリートにおいては、子育ては「姑」の監督の下に置かれた。 いまひとつ、女性の教育そのものに対して敵対していた。 女性にとって「無能なことは良い道徳」であり、女性が文を知ることは、社会秩序が崩壊すると言うのが儒教の女性観の根底をなしていた。 儒教の中国語、韓国語、日本語の文献には、「良妻」、「、「良母」と言う単語は在るが「賢母」は見られない。 明治の女性教育観における「賢母」とは、優良な次代の国民を育てるにたるだけの知識を持った女性の教育を目指したものだった。  以上の講義を聴いていた若い女性はどのように聞いただろうか。 今回の講義は幕末の庶民の生活、明治以降の家庭、農村風景、そして昭和30~40年代の日本の働く女性の写真が数多く示されたが、釜戸も、お勝手も、井戸も、洗濯場の風景も彼女達には全く何処の国の話と言おうことだったろう。 どのような感想が講義後のミニ・レポートに書かれたいたか読んでみたいものである。 女性もさることながら、男子学生はナヨナヨで、携帯電話ばかりを相手にピコピコばかり、 黒船も来たわけではなく、また、戦災で全てが失われた状況ではないが、それ以上の 崩壊を感じさせる講義室であった。
本日、コラム 2−N No307に、「天木 直人」さんの”どのツラ下げて”を掲載しました。
まずは、秋の進展を百姓学校の紅葉でお知らせします。  ↑9月23日、色付き始めました。  ↑10月10日の紅葉です。(同じ紅葉です)  ↑ 10月25日の紅葉です。 如何でしょう、秋も日増しに深まってきたことが伝わりますネ。  ↑残念ながら11月2日の瑞浪・日吉は朝の最低気温がマイナス4度でした。 結果、紅葉したモミジの葉の先は茶色に変色しておりました。(11月8日撮影)  ↑例年、11月下旬の収穫祭の時には、右のカラマツが最高なのですが・・・  → →  ↑ 今年の紅葉は、残念ながら、世相を現しているのでしょうか。  ↑10年目の経験から、一度には種まきも、苗の定植もしなくなりました。 写真はタマネギです。 左は2週間前に定植しました。 ピンと背を持ち上げています。 手前は本日定植しました。 前回の定植の確立が98%で、今回は不要なほどの定着率でした。 このまま、順調に成長してもらえば、(どのような玉が出来るかはわかりませんが)、一人前のお百姓の免許がいただけそうです。 本日の収穫の内容は表示しませんが、前日に仲間が日程を間違え作業を半分ほど終了していました。 特に、サトイモの掘り出しを全て終了してくれていました。 やはり、収穫は11月中旬以降が正解です。 それでも、試堀りよりは一段と成長しており、満足の行く内容でした。 本日、作業にこられた他のグループの方に、お裾分けが出来ました。 差し上げれる立場になると言うことは、気分が良いものです。 また、何時かは頂く身になるのでしょうが・・・・
夏から初秋は陽が残っており、午後の6時頃から散歩に出かけておりましたが、10月に入り午後の5時頃に家をでることにしていました。 11月の声を聞きますと、午後の5時では帰って来ると石ころの山道は足元が危なくなり、日ごとにスタートの時間が早まります。 昨日は午後の4時に家をでましたので、久しぶりに大回りコースで西高森山を目指しました。 春日井市内から名古屋方面が見渡せる眺望の素晴らしい250メートルほどの濃尾平野の最北西の外れの小山です。  ↑その前に、定点観測地点の一つ「北池」に立ち寄りました。 鴨がバタバタと飛び立ち驚きました。人が来ることが少ないからでしょう。  ↑陽が沈む前にと急ぎました。 半分、諦めながら額に汗して到着 雲間に隠れる寸前で、(約1分間)間に合いました。 丸の太陽ではありません。  ↑陽が沈み3~4分後の春日井から名古屋方面の光景です。  ↑西高森山から50メートルほど下ったところから、鈴鹿山脈が雲の上に・・・ 帰宅時間は午後の5時半を少しすぎた所でしたが、街路灯の存在を認識しました。 そして、本日は立冬です。温かな・気持ちの良い一日になりそうです。 午後からが、「波動の会」で名古屋・伏見です。どんな話題が提供されるのでしょうか。
 例年この時期、植物園内大久保池のラクウショウは見事な紅葉を楽しませてくれますが、今年は力なく赤茶色に染まったと言おう感じです。 心なしか、池の太りすぎの鯉の動きが更に悪く、鴨の羽の色も鮮やかさが見られません。 一昨日から始まった我が家の松の剪定は順調にすすんでいます。 本日は午後から用事で出かけますので、一番茂りのやさしい松に取り掛かりたいと思います。 事前に写真でも撮っておきましょうか。
蚊に弱いと言うか、大嫌いな蚊が庭から退散した11月に入ってから毎年始めます。 今回も11月2日の夜からの冷え込みで、しぶとい小さな蚊も姿が消えました。 以前は根を詰めて実施しましたが、体力が続かないことと、長時間になりますと後半は手荒な扱いになりますので、1日当たり4時間を限度としています。 我が家に松が来た時、手入れしておけば老後の小遣いくらいにはなるだろうと期待していましたが全くの期待はずれで、近くの農協の園芸部も購入を中止していると聞いています。 (自分で実施できる間は良いですが、費用を払ってまでは、どうしましょう) その上に、成長した松は、1・5坪の庭の畑に日陰を作り邪魔者扱いです。 それでも、剪定・もみ上げをしますと、それなりの姿・形となり見上げては満足しています。 年々、切り込み方も思い切りがよくなり、短時間で進行しています。  ↑脚立の上から見下ろしますと、ツワブキがアチコチに咲いています。  → →   ↑  ↑ミニ・シクラメンが私たちの出番間近と騒ぎ始めました。 松の剪定を早くしないと、蜂屋柿の収穫が待っています。 2日前、あるブログに今年は柿の成りが悪く、ご覧のように何もありませんと、異なる実の無い柿木が紹介されていました。 果たして、飛騨金山の柿はどうなっていることでしょう。 世の中、これまでの動きや流れと様相を異にする現象が表面化しています。 これまでの行いが積もりに積もって、顕在化してきているのでしょう、松の一枝一枝に挟みを入れ、揉み上げ、チクリと松のトゲにさされながら修行の松剪定です。
 → → ↑アスファルトの隙間、ナンキンハゼの落ち葉に囲まれて  → → ↑タイヤのプランターの中で咲いています  → → ↑野生の「ノコンギク」は、栗の木の下です。蜂が蜜を吸っています。  → → ↑岩陰からやっとこれだけ顔を覗かせていました  → → ↑この付近では一番目だっています。  → →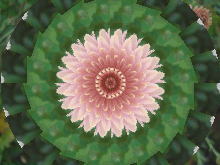 ↑次の菊の色と良く似ていますが、良く見ると色合いが少し違います。  → → b b↑並べてみますと、やはり色合いも表情も違いました  → → 気になっていた菊たちを全てこの画面に登場させましたので、ヤレヤレです。 彼女(彼氏?)たちは何もいいってはいませんでしたが、私には気になっていたのです。 アップで取上げていますので、それぞれに存在感と個性が感じられますが、どれもこれも庭の中の一角でヒッソリと咲いています。 きっと、人間社会も同じことなのでしょう。 これからの時代、ヒッソリと主張もせず、余分なエネルギーも消費しないで、生きてこられた花々や動物、そして人間が注目される時代になる。 いやそのような彼らこそ時代の先端を歩いていることになるのでないか。 だって、回れ右して時代が逆転し、動き始めているのですから・・・・。
昨夜から急に冷え込みました。 寝室の窓が少し空いていた為に、吹き込む隙間風で起きてしまいました。 本日は11月1日から始まった中部大学の大学祭に行きましたが、生憎の気温と風で春日井や周辺からの一般市民の出足は鈍くなったようです。 カメラ持参で何か面白い対象はないかと思いましたが、例年通りの屋台が目に付くばかりで、被写体として目に留まったものがありません。  ↑一昨年から開講された「幼児教育学部」は、人気でした。 ご覧のように子供たちはパソコン画面で漫画を描いています。 昨年受講し顔見知りになった教授とお話させていただきましたが、「学生が年々小粒になって、研究発表会の内容も色々と手間がかかります」と言っておられましたので、「学生ばかりではありませんよ。企業でも30歳ぐらいにならないと、給料分の働きはしないですよ」と答えると。 「そうですね、時々卒業生が訪ねてきますが、その応対振りに困ってしまいます」と言っておられました。 「時流は待ったなしで変化・進展しています。 そのうちにドカンと一発これまでの社会基盤が大崩して(本当は既に崩れているのですが、、対処療法して、更に深刻化を促進している)初めて目覚めるのではないでしょうか」と持論を口にしました。 教授は「本当にそのようなことが予感できる最近の情勢ですね」と、話がすすみましたが、同じ部屋にいる学生に聞こえないように声を潜めて話をされる教授がいささか可哀相でした。 ゼミの学生の就職の世話のために、教授の企業訪問もあるという学校のことも聞いています。 中部大学はどうなっているかは知りませんが、学生のことを心配することも必要でしょうが、数ある大学そのものの存続が問われている状況とまでは言えませんでした。  ↑学校創立者を記念して建てられた、「記念塔」と思われます。 大変なご苦労をして設立、ここまで発展させてこられたと聞いています。 聴講生として通学させていただけることに感謝しています。 学校のみならず、社会・経済の先行きが不透明な時には、安定した就職先として官公庁に対しても一般市民の目はさらに厳しくなることでしょう。 大学祭のメイン・ステージでは、大音響が響き渡っていましたが、急に訪れた寒波に鳥肌を立てた足長のお嬢様にはカメラを向けずに帰ってきました。 COLUMN 1−D 1151 平成21年11月2日・記 |
||||||||||||||||||||
遠山郷、3泊4日となりました。
|
||||||||||||||||||||
 ↑10月31日の、午前5時半、遠山郷の和田の道の駅で 前夜は月と星が綺麗に輝いていました。  ↑5時45分、白々と明けて来ました。建物は道の駅です。  ↑午前6時、遠山川  ↑遠山川に沿ったところは、ここでは広い畑があります。  ↑ 陽が射し始めました。霧が昇ります。  ↑「アンバマイ館」観光案内所と足湯のところで待ち合わせです。  ↑普段は下から眺めてばかりでしたが、時間がありましたので和田地区全体を  → →  ↑「赤石銘茶」としての特産品でしたが、今は出荷量が落ちているとのこと。茶花です。 この日は前日に続いて、再び「しらびそ高原」と「下栗の里」を今回の「遠山の休日」の参加された方とバスにて、見学してきました。  ↑「しらそび高原のダテカンバ」、上空高く飛行機が飛んで行きました。 夜はジャズ・コンサートを楽しみ、その後は恒例の「舞夢」でのカラオケで盛り上がりました。 翌日は昼のバーべキュの時に、炭火の焼き魚、生シイタケ等が美味しく、ついつい、いや初めからグイグイと頂きました。 夜は夜で、当日開店したお店の披露に参加し、しこたまいただきましたので、結局ご帰宅は4日目の朝となりました。 |
||||||||||||||||||||
| 前のページはこちらからどうぞ |