
| このページ以前の コラムはこちら |
||||||||||||||||||
朝のラジオで今日は20度を越す暖かい一日になりますと報道されました。 ストレッチをしている時間帯は、やっと雨が上がったばかりでしたので、想像が出来ませんでしたが、大学の一時限目の授業に合わせて9時ごろには学内に入りました。  ↑雨上がりの学内一番の目抜き通りですが、登校してくる学生が少なく、ご覧のように、誰一人も通行人の無い落ち葉の写真となりました。 連続2教科の講義はいささか疲れますが、講義内容が良く、満足して帰宅しました。 本日はこれから少しばかりお手伝いと言うか、関係していますWEB関連の会社の10周年記念の会社説明会とパーティーで、春日井・勝川駅前にゆきます。 勝川駅の再開発は既に30年くらいの年月がすぎているのでしょうか。 1週間前に、下り線につづいて今回は上り線も開通したと新聞で読みました。 春日井市にはJR中央線の駅が5駅ありますが、一番名古屋市内に近い場所にあります。 第3セクターの勝川ホテルもありますが、ご他聞にもれず赤字経営からやっと抜け出たようですが、スレスレの経営が続いているようです。 春日井市内や周辺の企業や個人がもっと活用し、赤字経営を心配するのではなく、価値ある存在になるようにと思っています。 私の通学している中部大学も今では春日井市になくてはならない学問や文化の発信基地となりました。 これからは公共の施設や場所は市民の参加によって更に盛り上げ、有意義なものにしてゆく時代となったと考えています。 本日の新聞で、春日井のNPO法人「愛岐トンネル群保存再生委員会」が実施した、旧国鉄中央線廃線跡で実施した市民公開の入場者が14838人になったと報道されていました。 事前予測では3000人と言うことでしたので、一本しかない道路は最大1時間半待ち、何時もは快速が止まらない駅の「定光寺」ですが、初日の午後からは臨時停車するほどになったとのことです。 跡地を民間から買い上げる為のナショナルトラスト運動への寄付も3日間で160万が集められ、目標総額1500万円に確実に向かっています。 行政に頼るのではなく、自分達で物事を立ち上げ、前進させてゆくことがマスマス求められている環境になってきたと感じずにはいられません。 そのこと自身が楽しいことであり、そこから喜びが生まれてくる時代になってきたと言うことでしょう。
10年程前から義姉のところに出張庭師をしています。 義兄が針金で松の枝を誘導していたため、枝に食い込んでしまい門かぶりで一番肝心な枝が根本からポキリと折れて、失われています。 出張庭師としては遣り甲斐が無いと言うか、その後どのように枝を誘導しても、肝心要が失われているのですから、どうしようもありません。 しかし、怖いもので、それがこの松に与えられた運命かと思い、10年間この時期に剪定してきました。 すると、それはそれで良いのではないかと感じるようになりました。 他の2本の松は更に、惨めな年月を送っていましたが、それも手を入れている間に愛着が出てきました。 写真でお見せすることもありません(写真撮りませんでした)ので紹介は又いつかいたしましょう。 話変わって「柑橘類」のことです。松と同じ狭い庭に「カボス」と「ユズ」のことです。 今年は我が家の庭のカボスも5〜60個収穫できました。例年は2〜3個です。 義姉のところのカボスは1本なのですが5〜600個ほどがタワワ・タワワなのです。 その隣のユズも4〜500個は下らない実を付けています。 その実りの姿を写真に納めてくることを失念してしまいました。  ←カボス ←カボス → →  ↑ カボス  ←ユズ ←ユズ → →  ↑ユズ 今夜はユズ湯に浸かって、5時間の庭師の疲れを癒します。
毎年、この時期になりますと名古屋JR(高島屋)の表玄関は電飾で飾られます。 3年に一度程しかお目にかかることは出来ませんが、昨夜は「一献会」ということで、早めに出かけて見学してきました。  ↑ある家庭の春夏秋冬というテーマのようでした。  ←春 ←春 ←夏 ←夏 ←秋 ←秋 ←冬 ←冬小型デジカメで手振れをしています。   突然「剪定ハサミ」の登場で、編集間違いではないかと思われたことでしょう。 嬉しくて掲載しました。 今秋、松の剪定をしていたときハサミのバネが飛んでしまいました。 最寄のホームセンターで探してみましたが見つかりません。 昨秋、群馬県に紅葉見学に行ったとき、休憩で立ち寄った農協の店頭で本場新潟県の刃物が店頭販売されており、気に入ったので購入してきたものです。 そのときの入れ物の箱が残してあり、そこに書かれた住所にFAXで連絡を取ったのですが、今のところ何の音沙汰もありません。 この時代の波で工場は閉鎖されたのでしょうか。 昨日、名古屋に行ったときに、高島屋に出店している「東急ハンズ」に立ち寄ってみました。 販売場所を探しましたがなかなか見当たりません。 最初に尋ねたパートタイマーと思われる高齢の男性は、「バネ売り場」を案内してくれました、そこはバネはバネでも用途の異なるところでした。 そのパートの男性との会話を聞いていたのでしょうか、若い販売さんが「こちらにありますよ」と案内をしてくれました。 種類が少なくピッタリのバネと思われるものは、見当たりませんでしたが、これが近いかなと思われるものを一つ購入してきました。 そして、今朝、あてがってみますと写真のようにピッタリで、嬉しくなってしまいました。 郊外のかなり大きなホームセンターでは販売しておらず、都心のど真ん中のお店で購入できるとはショット意外でしたが、考えてみるとそんなに需要があるものではないので、広域商圏を対象とした交通の便の良いお店での品揃えと言うことになるのでしょうか。 なお、そのときの若い販売員さんの接客態度が親切で気持ちが良かったです。 その後、かって勤めていた会社の仲間との一献会でしたので、最近の小売業の話が持ち上がりましたが、30数年前の頃との様変わりに、これからの方向性についての前向きな・積極的な発言は聞かれませんでした。 が、時に時代は断層をもって、新しい時代が形成されてゆくと明るく発言した積りですが、果たしてどのように受け止められたのでしょうか。
  ↑まだ、干して6日目です。 渋が浮き出て、柿色が気持ち赤味を増したように感じます。   → → 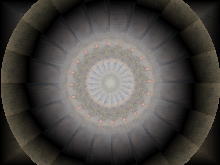 ↑、冬に向かう庭が日増しに綺麗になります。 市の条例ではダイオキシンの関係でしょうか、焚き火は「ご遠慮願います」となっているようですが、街路樹のナンキンハゼ、敷地内の桜、シデコブシ、剪定した松の小枝等が集められた庭の切り穴で焚き火です。 一年中を通して思い出すと、日ごとに花が咲きそろってくる春の庭は綺麗ですが、スッカリ葉を落とした枝ばかりの庭も悪いものではありません。 「命が誕生し、成長する春」と「命枯れ、土に還って行く冬」、それぞれに良いものです。 この時代、役目を果たして土に還って行くモノもあれば、近づくお役目のために準備を始めたモノもあります。 本日はかっての会社で仲間だった知人と名古屋で一献です。 まっさらな現役はいません。一役終了した仲間達です。と言って、皆さんご隠居様というわけでもなさそうです。 どのような話題が持ち上がるのか、興味があります。 私もこの一年間で、記憶に残る体験を持参する計画です。
ナンキンハゼの街路樹の落葉が今が盛りです。  ↑一番早い木はご覧のようです。 今朝の冷え込みで一段と落葉が早められたようです。  → →  ↑雪雲が到来しているようにも見えますが、陽光は時間と共に温かです。  → → ↑それに引き換え、我が家の「花之木」は今が紅葉の真っ盛りです。 コンクリートの軒先に吊るされた柿の色と相まって、秋深しの一日が始まります。
 ↑例年、木立ダリヤは背丈が4メートル以上になるのですが、今年は3メートルです。 7月の中旬で一度背丈の伸びるのが止まり、秋風が吹き始めますと再度背丈が伸びてゆくのですが、今年は秋の成長が充分ではありませんでした。 その分、撮影はし易いのですが、木立ダリヤ、あるいは皇帝ダリヤと名づけられているように空に向かって思い切りぼ姿が似合うと感じているのですが・・・・ 御近所の木立ダリヤも更に背丈が小さく、しかも蕾がついていません。 天候・気候によるのでしょうが、天空の異変が地上にも及んでいることなのでしょうかと大げさに考えたり、いや間違いなく、時代の転換のときの兆候の一つであると考えたりしています。  → →  ↑万華鏡に尋ねますと、ご覧のような涼やかで・温かみが感じる映像となりました。 昨日の気温の低下と雨に代わって、温かな陽光に照らされた道樹山を眺めながら、本日の復習にかかります。 お隣の国、中国の近・現代史をこれほど詳しく学んだことはありませんでした。 知らなかったこと、気付かなかったこと、ソウだったのかと改めて認識することばかりです。
 ↑ ご覧のようにと言ってもお分かり願いでしょうが、数量では昨年の7割と言ったところですが、大きさを加味しますと9掛けと言うところでしょうか。 今年は裏年ですが、各地の柿の収穫の話を聞きますと、全くダメという所もあったようですので、平年並みか少し落ちると言ったところでしょうか。  御近所の方で、柿が吊るされると「灯油を購入しなければいけない」といわれる方と、もうおひとり「里が恋しくなります」と声をかけて、コンクリートの軒先を眺めて居られる方がいます。  ↑干しあがった柿を持参するのも良いですが、皮を剥くところから体験するのも良かろうと、(本音は皮むきが大変の為)ダンボールに詰めて差し上げました。 一軒は軒先も小さく、またお忙しそうでしたので、結局皮を剥いてビニールテープで括るところまでの作業となりました。 後、4割ほど残っています、本日学校から帰ってきてからの作業となります。 手についた渋を洗い流しながら、柿色が日ごとに黒ずんでゆき、渋が甘味に変わったなら毎度の宅に贈れることが今年も出来そうだと少しばかり心弾みます。
 ここ数年の記録を調べますと、早い年で11月14日前後、遅い年ですと23日前後です。 今年の栗の収穫時期から判断して20日前後かと思っていましたが、14日現地より情報が入りました。 カラスが突き始めましたと・・・・ 早速、昨日金山に走りました。  ↑収穫の数量は平年並みでしたが、大きさが一回り大きいものが採れました。 多分、昨年収穫後、思い切った剪定をした木からの実が大きかったことから判断して、剪定が良かったのではないかと判断しました。 そこで、今年も思い切った剪定を試みました。 と、入力は簡単ですが、2メートル強の脚立の上からでも届かないツンツンと伸びた枝にはなかなか届きません。 剪定鋏で届かないところは、手ノコギリで切り落とします。 同行の女房が「毎日のストレッチが効果がでているね」と思わぬ発言です。 昼飯もそこそこに(義理の姉持参のボタモチとお茶で済ます)、連続作業5時間弱終了。  → →  ↑この万華鏡の映像をどのように解説しましょうか。 中央に柿の甘さが閉じ込められているのでしょうか。 周りには渋はちりばめられているのでしょうか。 イヤイヤ、その渋と見えるところが、これからの寒さに当たり甘味と変化してゆくのでしょうか。 雨に直接当たるとカビが生える事もあります。 今年の収穫も残り少なくなりました。 本日より、柿剥きが始まります。 メンドクサイと感じたり、この渋柿がどうしてあんなに甘くなるのだろうと感じたりしながら、楽しむこととします。
 ↑愛岐3山、大谷山に霧が流れています、午後からは晴れるでしょう。  ↑家の前のナンキンハゼの紅葉、本日が一番綺麗です。   ↑午後から陽が射せば、各家で一斉に落ち葉掃くとなることでしょう 静かな土曜日の朝、シットリと湿った空気が美味しいです。 COLUMN 1−D 1161 平成21年11月13日。記 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 数年前に世界を又に新種の種を捜し求めて旅している方に頂きました。 正確な名前は忘れてしまいましたが、確か「昇り(登り)菊」と言われたと記憶します。  ↑一輪の花の大きさは直径2センチメートルほどです。 生垣を生え昇り生垣の上に顔を出しています。 遠くから見ると菊と言われても一般的な菊の花を想像させません。  → → 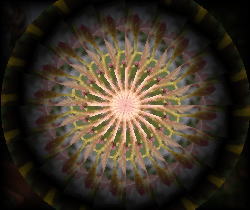 ↑ここまで、近づきますと、菊の花と認識いただけることでしょう。  → →  ↑密集して咲いていますので、一輪のみをアップするに苦労しました。 |
||||||||||||||||||
| 前のページはこちらからどうぞ |