
| このページ以前の コラムはこちら |
||||||||||||||||||||
 毎朝、朝食後に壁当てキャッチボールをします。 曜日によって異なりますが、平均午前9時前後、頭上を5~6機の飛行機が東から西、西から東(こちらは少ない)に飛んでゆきます。 冬の青空を一度このページに掲載しようと思っていましたが、単に青空を映しても面白くもありませんし、何のことやら判りません。 ところが、昨日は1機が飛行雲を残して西の空に消えました。 約3~4分後もう1機が頭上多分6〜7000メートルを飛んでゆきました。 カメラが近くになく其のまま見過ごしました。 その直後、東の山の頂に機景を認識しました。 一目散にカメラを取りに走りました。 其の結果の上記の写真です。 下の枝は吹き残された栗の葉です。 キャッチボールと素振りを20分もすれば、ポカポカです。
吉川英治・著「私本 太平記」全8巻の5巻を読み終えましたと昨日書きました。 講談社版の吉川英治・全集40「私本 太平記」では第2巻の後半・後40ページ(全500ページ)残しのところにさしかかりました。 1221年・承久の乱後の鎌倉・北条幕府は第9代執権・高時を最後に崩壊します。 彼の最後は壮絶と言うよりは惨めと言えます。 母より使わされた春渓尼を前に、何とか武士の対面を保って切腹した。 その周りに高時に殉じ自害した華の輪=お局、側女、小女房たちの血の海であった。 また、最後まで高時を守った譜代の側臣の差し違い、腹を切った血の海でもありました。 舞台は回り、場面が変わる。 北条倒れれば論行賞に預かれる思っていた武士たち。 同じ源氏の血を引き北条を倒すために手を組んだ足利、そして新田の思惑も早くも怪しげな空気が流れる。 バサラ武士・守護佐々木道誉、忠臣とされる楠正成や如何に・・・・ 宮方の公卿・公家衆は戦い取ったのは武家の力ばかりではないと、裏取引、賄賂が始まる。 天皇親政で”俄か政務官”になった公卿たちには行政手腕はなし。 北条の下ではうだつがあがらぬと思っていた多くの武士たちの土地欲、子孫繁栄欲、身一代の名聞欲。 結果、戦後社会の現象、社会に吹き出たものは1、小酒屋の灯の繁盛 2、火つけ、強盗、ゆすりの横行 3、女狼藉、ばくち流行 4、主殺し、良人殺し、5、河原の捨て子 6、乞食、疫病、男娼喧嘩と書かれている。」 以上何一つ庶民にとって安心楽土となっていない。 私の関心の一つに、長く続いた社会体制が崩壊した時、どのような社会現象が発生するのだろうかがあります。 西暦1318年後醍醐天皇の世とはなりましたが、ここからが南北朝時代であり、さらに社会は混迷し下剋上〜戦国時代へと歴史は流れます。 700年も前の時代とは比べることはできないでしょうが、時のリーダーやそれまでの権力者の立ち振る舞い、庶民の生活ぶりには共通点があるのではと思うのです。 平成23年世界で、日本での起こっている現象と対比しながら読み進みます。。  ↑福寿草が満開となりました
 テレビ横のサイド・ボードの上に今年も雛飾り 3段だとか5段だとかの華やかなモノではありません。 一番背丈が高いもので10センチ、他はそれ以下でほとんどが焼き物です。  本日は昨日までとは異なり一転気温が上昇しました。  ↑桃の花にも見える梅が香っています。  ↑ボケ(木瓜)の花 本来の鮮やかな赤色でないところに、単に物忘れではない「認知症」気味のボケの花なのかと問いかけてみました。 もちろん返答などあるはずもありません。 余談 政局は益々混迷の色濃く最終局面となりました。 ボケ老人ならず(いや加わって)欲ボケ政治屋の田舎芝居の終盤となりました。 などと言っている暇があるならば、「私太平記」でも読みましょう。 全8巻の内、5巻を読み終えました。 鎌倉幕府の崩壊「散りいそぐ」〜北条9代執権・高時の最後です。 「満つれば花にも 落花みじんの日が 否みようなく 訪れる」 其の時、 死にたくないと泣き吠えて死ぬのか、、武士として切腹し果てるのか。 平成のなまくら武士は恥も外聞もなし。 各いう己は・・と問う。
昨年入学の中部大学の学生が「歴史研究会」を立ち上げた。 学生がどのような勉強・交流をするか興味を持って参加しました。 既に5回ほど開催されていて、今回は休み中ですがメールで案内がきましたので覗いてみました。 開催と同時に、配布されたプリントがマキャヴェリの「君主論 第3章、複合の君主政体について」でした。 文庫本からのコピーですので書体は小さく、其の上難解な翻訳でいささかヒルミましたが、与えられた30分の間に何とか大意はつかみました。 その後、各人の感想と意見を述べることとなりました。 数人の意見を拝聴している間に、自分一人で読んでいた時よりは、内容の理解が少し深まりました。 マキャヴェリは1469年から1527年、イタリアのルネッサンス期の政治思想家、フィレンツェの外交官だったのです。 理想主義的な思想の強いルネッサンス期に、政治は宗教・道徳から切り離して考えるべきとの現実主義的な政治理論です。 読んだ項目のところからだけですが、ユーラシア大陸の西ではその後に続く繁栄と騒乱の時代を生き抜くにはこのような考えが必要だったのでしょうか、島国日本とはかけ離れた発想だなとの印象を述べました。 が、時代は今、グローバル時代ということで否応なしに日本もその波の中に巻き込まれ、巻き込まれるのみならず自らのかじ取りもままにならない混迷の政治・経済・社会情勢です。 近代以降の思想、論理にもとずく政治・経済・社会の仕組みではどうにもならないところに行き着き、流れ落ちる大滝を前にした難破船のごとき状況です。 新しい思想・理念・哲学が求められていますが、今のところ期待が持てそうにありません。(あるのかもしれませんが、私は気付いていません) 毎度の結論ですが、人頼りではなく自分の手足を使った試行錯誤の実践が求められていると、改めて感じました。 なを、この研究会に現在3年生で就職活動を開始した学生も参加しています。人文学部・歴史学科の学生は他の学生と比較してもさらに就職口が狭いようです。 私が「今後長く安定し・生活が保障されるような会社はないよ。それよりも、好きなこと、納得できることに取り組むべきではないですか」との発言に、静かに頷いていました。 それにしても、かつて何処かの書棚から借りてきて、数ページも読むこともなかった「君主論」をここで読むことになるとは思いもしませんでした。
今朝はきつい冷え込みでしたが、陽が登ると風もなく穏やかな日和です。 そこで、2月11日の日記に次回は”つばき園”を紹介しますと案内しましたので、本日行ってきました。 結論からいえば、マダマダ早すぎでした。  咲いていない訳ではないのですが、数種で、ほとんど蕾です。   ↑初音 ↑ 常満寺 と言うよりは、「春日井緑化自然公園」の20周年記念行事として平成20年にオープンしたばかりでまた若木なのです。 平成21年末で120種・385本だそうです。 「緑の相談所」で調べてみると、椿は2200余種あり、同じ種に入るサザンカは200余種あると書かれていました。 年々新しい品種が開発されるとのこと、その後も増えていることでしょう。 この公園のつばき園の最終計画は200種・400本とのことです。 春日井つばき愛好会の方たちが寄付された椿もあるとのことです。  。 ↑春日井つばき愛好会の方たちの看板です。  ↑「紅卜伴」(ベニボクバン)に蜂が来ておりました。(下の花)
 ↑昨日(2月14日)午後から雪が降り始めました。 この1週間で3度目です。 大きな積雪になるかと庭の写真を撮りました。  ↑一夜明けました。 積雪は1センチにも満たなかった。 (撮影時に太陽は山の上には登っていません)  → → ↑同じ場所の写真を撮ったつもりでしたが、ご覧のような状況 人間の記憶のいい加減さと言うよりは、私のいい加減さです。 ガラス戸を開け放つと冷たい冷気が飛び込んできました。 たちまち室内温度は4度です。 エイヤーと気合を入れて、朝の定番スケジュールをこなしました。 本日も順調・快適な滑り出しです。
いつもの散歩コースで「定点観測」している池が5個あります。 愛知高原国定公園・愛知岐阜県境の3山(私流には春日井3山)から流れ落ちた山水を溜めて灌漑用水の池として利用されています。 大きい順番に築水池、大久保池、若宮大池、大谷北池、そして大谷池です。 其の他にも数j個ありますが散歩道から離れています。  ↑大谷北池です。 この池は散歩道から少しそれますので年に数回しか行きません。 静かな環境ですので渡りの冬鳥が多く泳いでいます。が、昨日は見当たりませんでした。 葉を落とした枝の間から眺められる一番高い山が弥勒山です。 陽が西に傾き湖面は暗いですが、山手には陽が残っています。 落葉樹と針葉樹が半々の山です。 既に花粉も舞っていることでしょうが、有りがたいことに私には全く関係はありません。 子供のころからこの地で育った人は花粉症が少ないと言っていましすが、本当でしょうか。  ↑築水池です。 定点観測で一番よく登場する池です。 昨日は何時もとは反対側からシャターを切りました。 湖面まで降りから、西に沈んだばかりの太陽光線が丸く映っていました。 今朝は真っ青な空ですが、午後から曇り始め、夕方には雨と予報しています。 早めに散歩に出掛けることにします。
 ↑会場となったホテルから犬山「入鹿池」、明治村を望む 木地師は昭和30年代に途絶えたと聞いています。 それを映像として残そうと、昭和51年民族文化映像研究会が奥会津で収録したものです。 昭和35年に木地師としての仕事を辞めて山里に降りて生活していた4人の木地師、そして木地師と関連する山里の村民(田島町・針生)が協力して、山の中に木地師の小屋をつくるところから始まりました。 小屋を造り終えた山里の村民が帰りと、木地師は材料の選定から始まり、切り出し、小屋の中にフイゴをつくり、作業台、手引きのロクロをつくります。 手引きのロクロは初めてみました。 奈良時代からあると言われていますが、もしかすると縄文人が火を起こしたところから伝わっているのかもしれません。 映像撮影が昭和51年。 昭和35年に木地師として仕事を終えてから16年の年月が経過していますが、木地師の手の動きはスムーズです。 荒削りされた椀状の木を両足で抑え、クルクルと回しながらノミを振り下ろし、椀の中削りをしてゆく女性、其の映像のときは”ワ〜”と歓声が上がりました。 ノミが指先に振り下ろされないと恐怖の歓声です。 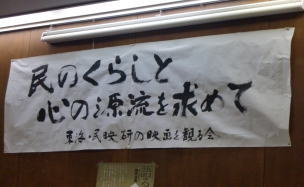 一度身体で覚え・染み込ませた技術は簡単には忘れないものだと教えられました。 数日前、NHKテレビで「無縁社会」と言うタイトルで番組を流していました。 又「限界集落」の単語も良き聞かされます。 が、その陰で多くの先人が伝え、残してきた文化、技術、伝統がまだまだ隠されているのではないのか。 近代社会から続く論理、合理に基づく政治、経済、社会の終焉と閉塞感に満ち溢れている今日この頃ですが、私たちの身近に新たな時代を切り開いてゆく数々の知恵や技術(宝物)があるのではないか。 それに触れてみる、それを掘り起こしてみる、それを活用してみるところから、明るい希望と未来が開けてくるのではないかと改めて気付かせてくれた映像でした。 さらにもう一本 1994年作成「寝屋子ー海から生まれた家族」と題された、伊勢湾の入り口・三重県答志島の今も続いている伝統的な若者宿の制度(寝屋子(ネヤコ)を、1980年3月から1994年秋までの14年間余をかけ記録したものを鑑賞しました。 当日、その寝屋子の親となられた山下正弥さんも来られており直接お話しが聴けました。 17年前の映像の中では寝屋親・山下さんは『漁師、海の仕事には危険がつきまとう、助け合わなければならない。寝屋子はその助け合いの制度 だ』と言われ、『ここで漁業で生き続ける限り寝屋子はなくならない』と語っていました。 が、昨日は『このままでは後10年で、寝屋子はなくなる』と言われました。 (今、山下さんは海を上がり、老人介護の仕事をしておられる) 私たちのこれからは助け合わなければならないが、絆はズタズタに切れてしまった。 ここから、新しい絆、仲間、ネットワークづくりが始まる。 寝屋子に登場する人々や若者の姿に一つのモデルを見た。 追伸 民族文化映像研究所には116本の作品があります。 貸出、販売及び刊行物資料等の問い合わせは 〒 160−0022 東京都新宿区新宿2−1−4 御苑ビル2F 民族文化映像研究所 tel 03−3341−2885 fax 03−3341−3420
昨日、朝から降り始めた雪は瞬く間に3〜4センチメートルの積雪となりましたが、午後には止みました。  ↑ アスファルトは直ぐに溶けてしまいましたが、田圃には残ります。 先週から読み始めた「私本 太平記」はこのような天候で書斎で順調に読み進めています。 既に、後醍醐天皇が隠岐の島への遠流される「亭獄帖」を読み終えていますので三分の一は進んだこととなります。 登場人物が極めて多く、人物の相関図を描きながら読み進んめているが、それでもときどきページを戻して確認しつつです。  ↑手書きの人物の相関図 ・若殿=又太郎=足利高氏(後の尊氏)は供の一色右馬介(=具足師 柳斎)と京都に遊学、其の帰りにバサラ武士・佐々木道誉との出会い。 そこで、終生の想の人となる藤夜叉との出会い。(其の子不知哉丸) から語り始められた歴史絵巻。 其の頃は、源氏の流れをくむ足利義康がしたためた置文(遺書)の存在など知らない尊氏。 ・天皇新政を望む後醍醐天皇とそれを取り巻く公卿・日野資朝、日野俊基(其の妻・小右京)が起こす「正中の変」。 ・後宇多院に仕えていた北面(院の武者)、左兵衛ノ尉兼好(すね法師と呼ばれていた吉田兼好)。初恋がもとで北面を辞し出家した。 ・後宇多院のみ后、西華門院のお内で、雑仕の卯木(楠正成の妹)。 卯木の夫は伊賀の服部家の族党で公卿小姓として地方武士の子が“しつけ習び”として都の権門に住み込み中に恋に落ちた服部元成。 二人が兼好と出会ったときはその日暮らしの生活をしている。 ・最後に楠正成は後に戦い巧者とよ呼ばれる武人とは異なり、妻子、一族朗党の安寧を願う河内の一田舎武者の頭領であった。 その弟、正秀は兄正成とはことなり武人としての功を願っていた。 其の楠正成に天皇より出仕の命が届く。 以上、書き留めた人物の一部を紹介したが、「私本太平記」の流れをご存じない方には、なんのことやら判らない人物紹介であったでしょう。 まだここからが本番で鎌倉幕府の崩壊、そして2帝相並ぶ「南北朝時代」、そして、尊氏の側近、高師泰・師直が活躍する時代へと進みます。 本日は三分の一を読み終えた時を振り返ってみました。 この間、朝廷と幕府の関係、守護・大名と鎌倉幕府の関係、地方の守護・大名・領主も官側、幕府側とに分裂し、世は益々疑心暗鬼の様相を示しています。 その間に置ける庶民の生活状況は特に書かれていないが、推して知るべしと言ったところです。 鎌倉幕府の崩壊、そして南北朝時代は、今、私たちが乗っかている時代と同じではないか教えられことから手にし、読み始めた「私本太平記」の物語はどのような展開をし、何を告げ、教えてくれるのでしょうか。 何を学び、次なる行動への指針となるのでしょうか。
今朝、九州・鹿児島沖で発生したという低気圧が関西から東海そして関東に近づき雪を降らすと報道していました。 我が家では午前7時半ごろからチラチラと舞い始めましたが、1時間後にはすっかり庭を白くし、今(午前9時半)もサンサンと降っています。 数日前、春の訪れを感じますとサクラソウ、福寿草を紹介しましたが、福寿草などは雪の下で影・形も見えなくなりました。 昨日の散歩のときの写真を掲載します。  ↑コウトウジ=紅冬至と言う極早咲きの梅の花です。 ↓ 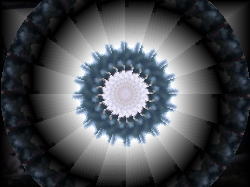 万華鏡にしますと、元の姿・形は全く何処かに行ってしまいました。  ↑これを想像出来たら大したものです。 ↓ ↓ ↓ ↓ 少し、間をとってみましょう。判りますか?  ↑この写真でも判らない方が居られるのでなないでしょうか。 「春日井緑化植物園」の竹林の青竹をプランターとし、パンジーを植え込んであります。 今年が初めての取り組みです。 以前、緑化植物園の「万葉苑」の竹の生垣を紹介したことがあります。 再生費用が100万円かかるということで、職員の方たちが修理しました。 ↓  多分、市財政の経費削減で予算が減少したのしょう。 そこで、生まれた計画と思われます。 竹やぶは整備保全され、しかも手作りのプランター花壇が生まれます。 竹やぶの隣の「椿園」も例年に増して手入れが行き届いているように感じました。今後もアイディアと知恵が湧いてきそうに感じました。 椿園はまた後日紹介します。(数種を除いて花がこれからです) |
||||||||||||||||||||
| 前のページはこちらからどうぞ |