 |
|
||
| NO.310 平成17年6月27日 記 |
百姓学校6月定例会の報告
|
| 梅雨に入ったというのにこの地方はほとんど雨が降りません。 昨年は雨続きで脱穀がなかなか出来なかったのですが、其の面では恵まれた脱穀日和となりました。    ジャガイモの収穫も順調です。 T企業の研修畑も収穫をしましたが、会社に持ち帰って配布しなければならないほどの出来栄えです。 私たちの畑はお土産で持ち帰るだけの掘り起こしにしました。 全部掘り起こしたらその後の対応に困るほどです。 来月にはさらに大きくなっていることでしょう。  と言いますのも、夏野菜の手立てに人出が不足していましたから・・・ こんな状態になっていました。   トウモロコシ ネギ畑  大根とニンジン 大根とニンジン畑は「夏草と 大根・ニンジン 共生す」 ネギ畑は中耕と草取りで何とか、「掻き分けて プンと夏ネギ 香たつ」 トオモロコシ畑、「競り勝った トオモロコシは 甘いのか」 その横では冬に収穫を終えたニンジンが花を咲かせ、実をつけていました。  「知らぬ間に 花咲・実り 種となる」 「知らぬ間に 花咲・実り 種となる」草畑と言われたわけではありませんが、今年は花畑全部が活用されています。 例年よりやはり10日から2週間送れて花が咲き始めました。    この3色はカラーです。 カスミ草をイッパイに咲かそうと300ポットを植え込みましたが、根元から虫に切り倒されるのが2〜3割あります。 やっと数本花をつけました。  夏の花ヒマワリはやはり強いです。 自宅で育てた苗は全部定着に成功しています。 アルストメリアのこの種類は強いです。 既に1ヶ月前から咲き始めていますが、まだまだこれからです。   |
| NO.310 平成17年6月27日 記 |
百姓学校6月定例会の報告
|
| 梅雨に入ったというのにこの地方はほとんど雨が降りません。 昨年は雨続きで脱穀がなかなか出来なかったのですが、其の面では恵まれた脱穀日和となりました。    ジャガイモの収穫も順調です。 T企業の研修畑も収穫をしましたが、会社に持ち帰って配布しなければならないほどの出来栄えです。 私たちの畑はお土産で持ち帰るだけの掘り起こしにしました。 全部掘り起こしたらその後の対応に困るほどです。 来月にはさらに大きくなっていることでしょう。  と言いますのも、夏野菜の手立てに人出が不足していましたから・・・ こんな状態になっていました。   トウモロコシ ネギ畑  大根とニンジン 大根とニンジン畑は「夏草と 大根・ニンジン 共生す」 ネギ畑は中耕と草取りで何とか、「掻き分けて プンと夏ネギ 香たつ」 トオモロコシ畑、「競り勝った トオモロコシは 甘いのか」 その横では冬に収穫を終えたニンジンが花を咲かせ、実をつけていました。  「知らぬ間に 花咲・実り 種となる」 「知らぬ間に 花咲・実り 種となる」草畑と言われたわけではありませんが、今年は花畑全部が活用されています。 例年よりやはり10日から2週間送れて花が咲き始めました。    この3色はカラーです。 カスミ草をイッパイに咲かそうと300ポットを植え込みましたが、根元から虫に切り倒されるのが2〜3割あります。 やっと数本花をつけました。  夏の花ヒマワリはやはり強いです。 自宅で育てた苗は全部定着に成功しています。 アルストメリアのこの種類は強いです。 既に1ヶ月前から咲き始めていますが、まだまだこれからです。   |
| NO.309 平成17年6月27日 記 |
飛騨金山に梅の収穫に行ってきました。 |
| 6月24日飛騨金山に行ってきました。 成木になったのにどうして梅が収穫できないのかと思っておりましたら、飛騨金山は冬の間、野鳥の餌がなく梅の花芽を食べてしまうのだと教えられ、昨冬は防鳥網を仕掛けました。 と言ってもなかなか思うようには網を張れませんでした。 今朝、金山の知人宅に電話をすると少しは生っているよと言われ出掛ける事にしました。 結果は16Kgの収穫です。 帰り道で川辺の「白扇酒造」により2升米焼酎を仕入れ、帰ってきて近くの酒デイスカウントセンターで180リットル(1・8を10本)と氷砂糖を購入。 結果216を漬け込みました。 さて、何処に寝かしておこうかと思案中です。  栗の木が迎えてくれました。 今秋も間違いなく大収穫でしょう。 昨年は全滅でした蜂屋柿(乾し柿にします)がココまでは順調です。 と言っても昨年もこの時期までは実の付きは良かったのですが、台風が3回ほどやってきて全て落としてしまったようです。 今年は生りすぎではないかと思うほどに枝が垂れ下がっております。 摘果は7月ですので今年は出掛けてみようかと思っているのですが、気温が上昇するとついつい出掛けるのが億劫になってしまいます。   スモモが綺麗な実をつけていました。 収穫時期は8月ですが、それにつられて摘果に行ってこようかなと思っています。   これがスモモです よい形でしょう 忘れていました、これが梅の成果です。  |
| NO.308 平成17年6月25日 記 |
またまた、アフリカに出逢いました。
|
「森の学校」から出てグローバル・ループを一回りして帰ろうと西ゲートに向かいました。 グローバルコモン5(アフリカ)に近づくと賑やかな打楽器の音がしてきました。 またまた、出逢いましたアフリカン・ミュージック「カメルーン」の伝統舞踊と音楽です。 どうも、今回の博覧会を期に、特にアフリカを意識する事になりそうです。 「人類のゆりかご」といわれるアフリカ、中部大学の前期に続いて後期も受講してみようという気持ちに成り始めています。 では、映像で紹介しましょう。 兎に角、激しく打ち鳴らし、踊るのでピントのボケた写真ばかりで選択に困りました。         文章はNO304 をお読みください。国、民族は変わっても変わらぬ喜びの音楽と踊りです。 いや、読む必要はありません。 オマケの写真を挿入します。   |
| NO.307 平成17年6月25日 記 |
万博ー「森の学校」を紹介しましょう。
|
6月23日は万博ボランテイアの3回目です。 午後からは晴れという予報です。 午前7時45分に万博会場・北ゲートに降り立ちますと、既に千人ほどの方が列を作っておられました。 開場までは1時間以上あります。 これまでは西ゲートの担当でしたので、一番メインの入り口の状況は知りません。 9時前に一番人気のあります、企業パビリオンBの「トヨタグループ館」と「日立グループ館」が見渡せる場所で眺めていました。 9時開場と同時に「走らないでください」との静止も耳に入らないように皆さん走ってこられました。 以下の写真は開場10〜15分のものです。  朝一番では約9割の方がこの企業パビリオンに向かうということです。 1時間もしない内に午前の部の整理券は終了しました。 なお、午後2時から午後の部の整理券が配布されるのですが、午前11時には既に千人ほどの方が待っておれれました。 昼食を仕入れに行く方、ビールを飲んでいる方、ビニールシートを持参で一眠りの方もおれれました.。 巡回サービス係の私としては気の毒に思われましたが、皆さん覚悟の上のようで、待つのを楽しんでおられるようでした。 さて、午後1時半に早番のボランテイアは上がります。 着替えをしてから、一般客として再入場しました。 本日は混み合っているパビリオンを避けて長久手会場にあります、森の自然学校を紹介しましょう。 「北の森」と「南の森」がありますが、メインは「北の森」です。(なを、瀬戸会場にも「里の自然学校」があります) まず、「北の森」から  こんな看板で迎えてくれました。   入り口のアプローチ そしてゲートです このゲート・案内所で詳しく説明と注意事項を聴きます。 万博がオープンして直ぐのころ雨の中を歩きました、其の時は肌寒さを感じましたが、今回は額に汗です。 こんなビオランテに出会いました。    足早に、「南の森」にまいりましょう。   森の学校の入り口です さて、これは? 瀬戸の土で作られた人形です。 「里」の豊かさを語りかけてきます。   葉っぱのドーム EXPOドーム 葉っぱのドームから振り返りますとEXPOドームが見られましたので並べてみました。   ヒモで作られています 「森の隠れ家」とありました 森の隠れ家の中では歩きつかれたのでしょうか、椅子の上で4人の方がシッカリ熟睡されておられました。 なを、希望者にはインタープリンターの方の案内で、一般道とは異なるところまで案内していただけます。 但し、混み合うときは事前予約が必要です。  望遠でその様子を撮影しました。 望遠でその様子を撮影しました。最後に、ボランテイ巡回中に拾った、「万博見学ノート」の忘れ物です。 事前に勉強してきたのでしょう、イッパイ予定が書き込まれていました。 どれだけ回れたのかな。 なお住所が分かりますので忘れ物カウンターから、貴重な思い出を送ってもらう事にしました。 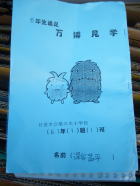 |
| NO.306 平成17年6月22日 記 |
名前が分かりました。 |
名前が分からなかったので、形・姿から「チョウチン花」などと呼んでいましたが、6月20日の”フォット歳時記” 岩木呂 卓巳さんの記事から分かりました。   上記のものは自宅の庭にわずかに残っているものを撮影しました。 大半はこんな姿になっております。  さて、この花は”ヤマホタルブクロ”と言うそうです。 『このホタルブクロは北海道から本州、九州の野山や丘陵地に自生しているが、このヤマホタルブクロは東北南部から近畿東部の山深い斜面に咲いている。 特に東海地方にはなじみ深い花だ。 色は白、ピンク、赤、薄紫など豊富である。 このヤマホタルブクロの名前の由来はチョウチンのことを「火垂る(ほたる)」とよんだことに由来すると言う説と、子供が山でホタルを見つけ、この花に入れて家に持ち帰ったと言う説がある。 後者は作り話っぽいが、夜道でホタル入りの花をチョウチン代わりにして歩く子供の姿は情趣たっぷりで、やってみたくなる。 時期はゲンジホタルの出現とヤマホトルブクロの花期は一致する。 が、ゲンジホタルの生息する場所でこの花を見た事がない。』 今週の土曜日・日曜日は百姓学校の定例会である。 毎年この定例会の時には「ホタルの乱舞」に出逢える。 今年も会えるだろう。 確かに瑞浪・日吉・深沢の地ではこの花を見かけない。 私の庭では年々増え続け、時折除去しないと他の草木の邪魔になるほどなのに。 最後は、通学路に咲き始めた日日草で締めくくります。 直径1〜1・5センチメートルの小さな花です。 朝に開き夕刻には萎みます。       |
| NO.305 平成17年6月21日 記 |
築水池一周、午前中に散歩しました。 |
今春から日中に中部大学の授業に行き、夕方は放送大学の受講となり、散歩することが従来の半分になってしまいました。 気持ちの問題かもしれませんが、筋力が落ちているのではないかと感じられ、今日は朝食後パソコン・インターネットに向かうのを止めて築水池の散歩に出掛けました。 ヒョットしたらまだササユリが残っているのではと期待しましたが、やはり終っていました。 その代わりと言っては可哀想ですが、「山クチナシ」が咲いておりました。    山クチナシというのが正しいかどうかは定かではありません。 自宅の肥やしのタップリ効いたクチナシと比べてください。   香は同じなのですが、山に咲くクチナシのほうが媚びたところがありません。 同じ散策道にアジサイも咲いておりますが、NOー303の「あじさいの里」のアジサイと比べると5〜8分の一の花の大きさです。    この散策道は湿生植物が保護されています。 秋には可憐な花が咲きますので、また紹介しましょう。 この 散策道は今はこんな感じです。    1時間強で自宅に戻ると汗ビッショリでした。 玄関に「今、私最高の時」とばかりにユリが咲き誇っていました。  |
| NO.304 平成17年6月20日 記 | |
NO301「毎日新聞」への投稿はこうなりました |
|
6月14日 NO301「毎日新聞”くりぱる”愛・地球博 特別号」への投稿内容が以下のようになりました。 500字という限られた中では本当に言いたい事が言い切れません。 今回の中で、「力・権力で押さえつけた政治は必ず短期間の内に行き詰まる」というフレーズがあったのですが、それと音楽、踊りとどのような脈略となるか説明し切れませんでした。 (参考、NO301をお読みください。 言いたかったことを解説しています) この投稿は7月17日、「毎日新聞、”くりぱる”愛・地球博 特別号のコラム『ジャンボ』(スワヒリ語で「こんにちわ」)」に掲載される予定です。
|
| NO.303 平成17年6月19日 記 |
「あじさいの里」に行ってきました。 |
| 「 東海地方最大級の五万本のアジサイが咲く蒲郡市金平町の形原温泉「アジサイの里」に行ってきました。 余り期待していなかったのですが、駐車料金500円、入園料300円で久しぶりに満足しました。    ここで、アジサイの由来について 『アジサイは日本原産のガクアジサイを母体した園芸変種。 いつごろ、どうして出来たかは分からないが日本生まれの園芸品種。 中国に渡り、1790年頃ジョセフ・バンスクが移出し、ロンドンのキューガーデンに植栽し、欧米で品種改良。 19世紀に紅色の花が咲くアジサイが出来る。 20世紀以降、品種改良が進み、明治になって日本に逆輸入。 西洋アジサイ・ハイドランジアと呼ばれるようになった。 アジサイを漢名で紫陽花と書くのは正しくは日本名「あじ」は「あつ」で集まると「さい」は真、「さ」の藍の約されたもので青い花がかたまって咲く様子からアジサイと名付けられた。 (牧野新日本植物鑑より) 意識したわけではないのですが、アオ系よりピンク系が多くカメラに収まっていました 。    ウインドミル ソフィテイー ラブユーキッス    ジューンブライト サンルージュ レデイーサチコ ピンクが続きましたので、気分を変えて   アリラン 名? 実に綺麗な紅色でした   伊豆の華 名?線香花火のようです    名?モクモクと カシワバアジロサイ エゾダルマノリウツギ 再び、ピンクに戻ります。 まだ他に数枚ありますが、どれがどれだか区別がつかなくなりました。 判明可能なものを取り上げました。   リップル ソフテイー  脱皮したばかりでしょうか? バッタの子供にとっては最初の餌のようです。 カメラを向けると警戒してヒゲ(触角)をピンと張っていました。 (追記・6月22日) 本日新聞を読んでいたら、上記の虫の記事が目に止まった。 30年前の「昆虫図鑑」では分からなかった虫の名前が判明した。 キリギリスの仲間「クダマキモドキ」である。 <クダマキ>といい、<モドキ>といい怪しげというか、正体がはっきりしない昆虫であることは確かのようである。 まさか、時代を反映して登場してきたわけでもないだろうが、兎に角私のシャターの被写体になったことは確かである。 目にし、シャターを押した私も時代の浮遊物なのか? オマケに    清澄沢 紅アジサイ 名? シャターを100枚以上押しましたが、紹介は以上にしておきます。 今日は花曇で愛・地球博の人手も多いことでしょう。 明日からは雨模様です。 雨の中色づいたアジサイを楽しむこともできるそうです。 |
| NO.302 平成17年6月17日 記 |
梅雨時に咲いています。 |
6月梅雨といえばアジサイを思い出しますが、その他にも 植物園のハナショウブが満開になりました。   左の写真の右上にあります舟の中の壷で1ヶ月強前に雛がかえりました。 大きな鯉がいるために、アッと言う間に飲み込まれてしまいます。 何度訪れても出逢わないので、ことしもヤッパリと諦めていましたら、いました・いました4匹。 アチコチに行ってしまう雛に親鳥は目配せして、ガウガウとなきながら注意を呼びかけていました。  山側から引き水した水路の沿ってユリが咲いています。    自宅に戻り、我が家の庭に咲いているまだ紹介していないユリです。   自宅の門を言ってもそこから出入りできる状態にはなっていません。 といいますのはトケイ草が一面に蔓延り、やっと新聞受けのみが顔を出しております。 そこの撮影はカットしてトケイ草のみアップで紹介します。 時計のようにみえたり、時には妖怪のようにも見えます。   |
| NO.301 平成17年6月14日 記 |
毎日新聞”くりぱる”愛・地球博特別号への投稿 |
NO295で案内しました中部大学生による毎日新聞・特別号「愛・地球博」のコラムへの投稿、私も書いてみましたので、ここに掲載します。 |
”アフリカン・ミュージック”「単調・素朴、力強く・心に響く」 今春放送大学の履修生と中部大学の聴講生となり、8教科の世界各地域の歴史・文化・社会の勉強を始めた。 教科書を読む、講義を聴くだけの座学だけでなく、愛・地球博の開催年でもあり、全期間券を購入して既に十数回会場に足を運んだ。 アフリカは遠くにあって、大きく、民族紛争・疫病・飢餓に満ちた暗黒の大陸とのイメージが私の中に定着していた。 偶然にも3回グループ・コモン4(アフリカ)の野外ステージのショウを見学する事になった。 単調に繰り返される旋律であるが力強く・湧き上がるようなリズムに乗って躍動感あふれる音楽と踊りに見とれた。 「人類のゆりかご」といわれるアフリカ、私の中に流れているDNAを目覚ましたのであろうか。 プロダンサーの舞台は見せるためのショウというよりは彼ら自身が互いに声掛け合い、足踏み鳴らし、激しく身体を揺さぶっているうちにますます熱が入り、周りの観客のことなど眼中に無いがごとく、魂を揺さぶる時空となった。 その踊る姿を見ながら、“力で押さえつけた政治は必ず短期間の内に行き詰まる”というフレーズが横切った。 これからもグローバル化は進展する事だろう、が同時に各民族・地域の歴史・文化・社会に根付いた単位がよりクローズアップされてゆくのだろうと思った。単調で素朴、力強い旋律とリズムは私の中に定着していたアフリカのイメージを静かに氷解させてゆくのを感じた。 |
| 500字でとの制約はなかなかキツイ。 あれもこれもと思うと直ぐに1000字以上になる、端折ると文意が通じなくなる。 仮にこの一文が採用されるとなると、どんな添削が成されるのであろうか。 いや、それにも値せずにボツということかも知れない。 単に見学に行くというよりは何か目的を持って出掛けることに、刺激があってよい。 (追記 6月15日) 上記を送信したところ、以下のメールがとどきました。 『 加藤大喜さま さっそくありがとうございます。 その踊る姿を見ながら、“力で押さえつけた政治は必ず短期間の内に行き詰 まる”というフレーズが横切った。 これからもグローバル化は進展する事だろ う、が同時に各民族・地域の歴史・文化・社会に根付いた単位がよりクローズ アップされてゆくのだろうと思った。単調で素朴、力強い旋律とリズムは私の中 に定着していたアフリカのイメージを静かに氷解させてゆくのを感じた。 この結末の部分のつながり方がよくわかりません。最初の文の意味は音楽・ダン スとどう関連しているのですか。 三鬼治@毎日新聞』 そこで、次のように返信をしました。 『三鬼 治 様 字数に追われて走っています。 こんな事を言いたかったのです。 ”力で押さえ込んだ政治は必ず短期間の内に行き詰まる”というフレーズが横切った。 利害得失が複雑に入り組んだ国際政治の中にあって、覇者は独りよがりの正義を押し付けたり、情報を操作したり、手練手管で己が望む方向にことを運ぼうとしつつも、自ら仕掛けた罠にはまり込んでゆく。 ココまで来ると「モアー&モアーの産業文明の終焉」を迎えるほかには解決の道は無いのであろうか。 これからもグローバル化は進展するだろう、が同時に各民族・地域の歴史・文化・社会に根付いた小単位がクローズアップされてゆくことだろう。 2つとない地球という楽園には様々な生き物が相互に関連しあって共存している。 それが全体としての和音を作り出し、共生ゆくには複雑な理論や力による統治ではなく、太陽、水、土、空気という自然に感謝し、一体となる生活に戻り・体験し、そこに集う人々が単純・素朴に生きる喜びを甘受し、呼び覚まされる力強い旋律とリズムに身と魂を委ねてみることが必要ではと考えさせられた。 「人類のゆりかご」といわれるアフリカ、そのアフリカン・ミュージックにそれを感じ、教えられた。 こんな事でよろしいでしょうか。』 |
| 前のページはこちらからどうぞ |


