 |
|
||
| NO.410 平成17年12月12日 記 |
南遊の会、2005スタデイーツアー感想文完成
|
| 今年の南遊の会の「2005スタデイー・ツアー感想文」が出来上がりました。 これで4回目となります。 今年は参加者も多く一番分厚い感想文集になりました。 南遊の会の財政事情からしますと、1冊当たり150円にもなり大きな出費です、更にご寄付や遠方の会員に郵送となりますので、これまた大変ですが、第7号となる会誌と合わせて送付しますと、今年の最大の事業が完了したことになります。 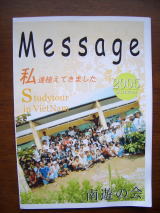 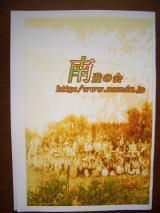 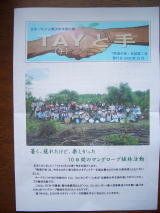 文集の表表紙 文集の裏表紙 会誌 既に、来期以降の計画やツアーを更に円滑に進めるためのミーテイングや取りまとめも進められており、アッと言う間の1年ですが、それでも一歩づつ進化しているかなと自己評価しております。 ほぼ予定どうり200部(前回50部合わせて)が出来上がりましたが、後100部必要です。 完成後、計画していた忘年会を学生を交えて実施しました。 お一人様3500円の鍋コースで食べ放題(鍋)、飲み放題です。 追加することはなかろうと思っていましたが、若い学生の事なんと3回お代わりしていました。 飲み放題にしてはそこそこの銘柄の日本酒が並んでおり、しかも人手不足を補うためか、冷えた1升ビンをそのまま置いてゆきましたので、いささか飲みすぎの状態になりました。 若いお嬢さんたちデザートが欲しいという事になり、Nさんの一言でヒルトンホテルに行くことになりました。 久しぶりにホテルのロビーでブランデイーなどを頂き、Xmasムードを楽しませて貰いました。    |
| NO.409 平成17年12月11日 記 |
オペラ”CARMEN カルメン”観劇しました。
|
 フィナーレの場面です 昨日10日、「200年度愛知県立芸術大学大学院オペラ公演」 於:長久手町文化の家に行って来ました。 百姓学校のメンバーの娘さんが出演するとの事で、チケットを購入しました。 なにぶんオペラなどというものにご縁がありませんでしたので、どんなものかと興味を持ってまいりました。 会場の”文化の家の「森のホール」”には数度、知人の演劇を観劇に行ったことはあります。 初めて行った時 町というには贅沢な箱を作ったものだ、その後の運営はよいのかなと心配もしていましたが、時々目にするパンフレットや情報で「なかなかやっているわイな」と感心しています。 今回も昨年に続いての主催が長久手町と愛知県立芸術大学です、初めての観劇ですのでレベルや評価は出来ませんが、正に総合芸術でした。 オーケストラは同じ大学の管弦楽団、指揮は同大学の講師、合唱も舞台美術も同大学の学生達でした。 改めて、身近に大学があることの意味と価値を知らされました。 申し添えますが、公演中はもちろん携帯電話は切りましたし、カメラを作動させるようなことはもちろんいたしませんでした。 今、思い出したのですが、開演前、何処の会場でもあります「携帯電話はお切りになるか、マナーモードに切り替えてください。 公演中は写真撮影などはご遠慮ください」というアナウンスはありませんでした。 当たり前のことですが、この「文化の家」ではいちいちそのようなことを言わなくても良い常識とマナー・習慣がついているのでしょうか。 |
| NO.408 平成17年12月9日 記 |
春日井都市緑化公園(グリンピア)
|
| この飾りつけは「パセリクラブ」というボランテイアの方々によって、年に10回ほど植え替えや飾り付けがなされています。 入場が無料のこともあり、幼児から小学生の親子や年配の方が良く訪れています。 裏山は東海自然歩道でもあり、一年中を通してリョックスタイルの方々を目にします。 では、今年のXmasの飾りにご案内いたしましょう。  左に見える鉄骨の建物の中にご案内します。(このツリー夜は点灯されます)    このツリーはパンとカンパンで出来ております。  マカロニツリーです    マカロニで出来た人形達です。   ヘチマツリーです 少しボケました、ヘチマです  貝のツリーです。 貝のツリーです。    テーブルの上に 大人でも十分に腰掛けられます 最後は小人の町でしょうか。    真ん中にXmasプレゼントを置いて、輪になって踊っていました。 |
| NO.407 平成17年12月08日 記 |
年賀状の印刷をしました。 |
| 今日は中部大学の学園創立記念日で授業は休講です。 この日を除くと12月24日までに投函しようと思いますとユトリのある時間がありません。 8回目となる「プリントごっこ」を取り出すことになりました。 製版したら一気に印刷をしなければインクが乾いてしまいます。 今年も250枚です。 毎年、同じパターンですが、数日前に寝床で浮かび、メモしたものをそのまま書く事にしました。 たとえ一言でも書き添えようと、空欄を作りましたがどれほど書く事が出来るでしょうか。 宛名は今年も自筆で書こうと思っております。 本当にアッと言う間の1年でした。   印刷を終えて都市緑化公園「グリンピア」のXmasの飾り付けを撮ってきましたので、明日にでも掲載します。 |
| NO.406 平成17年12月08日 記 |
これで本年最後です。〜木立(皇帝)ダリヤ冬眠〜 |
| 今年の春4月から何度登場したでしょうか「木立(皇帝)ダリヤ」、今年は早い寒さの到来で、冬眠に入ることになりました。 真夏前に2〜3メートルの背丈となり、真夏の間は成長がストップしていましたが、秋風の感じる頃より、再び背丈が伸び4mを越しました。 其れゆえに、花を紹介する頃には4メートルを超えていましたので、見上げる画面ばかりの紹介となりました。 昨日、根元から切り倒されました。   球根はそのまま地中で冬を越しますので、籾殻がかけられ、鉢が被せられました。   「しまったこと」をしたと悔やまれている事があります。 12月3〜4日鳳来寺に行っていたときのことです、鳳来寺の上り口の駐車場に、この「木立ダリヤ」の株立てがなんと11本で見事な姿をしていたのに、撮影を忘れてきた事です。 我が家の木立ダリヤがあのようになるには、後どれほどの年月が必要なのでしょうか。昨年は越冬できました事に安堵していたのに、早くも次に期待が移っています。 |
  東照宮 東照宮の神殿の両脇に狛犬が鎮座しています。   そこにはこんな短歌が添えられていました。左右の狛犬の意味がお解かりいただけると思います。 「戦場に召されし兵の守りとて 身を削られし 狛犬のわれ」 「戦争の絶えし世ならば神護る 身をば削るな 狛犬のわれ」  高き鐘楼を見上げて、兵の安らかに眠らんことと、平和を祈念しました。 |
||||||||||||
| NO.401 平成17年12月04日 記 | ||||||||||||
鳳来寺、”いろいろあります会”の忘年会へ
|
||||||||||||
| 鳳来寺、参道沿いの門谷地区やその周辺の地元の方々、更に都会からのメンバー、近隣の小中高の学生を交えて様々な活動が行われています。 「いろいろの森」と銘うった植樹から始まり、下草刈りや子供中心の木工工作など幅広く、しかもかなり本格的な内容で、その関係筋では全国的に注目されているようです。 その活動の中から本格的に森林技術を身につけようと、プロの方が講師となって昨年12月に「森林真剣隊」が生まれました。 今年に入って更に「NPO法人森林真剣隊」と発展しています。 また、これらのメンバーと一部重複もしていますが、千枚田の維持、復活の活動を始めて3年目、お米の収穫をしている「千枚田プロジェクト」もあります。 私は6年前に植林に参加し、その後「千枚田」のほうにも仲間に入れさせていただいていたが、今年はほとんど百姓学校とダブリ千枚田の方は全休、森林関係も2回しか参加していません。 が、例年楽しい忘年会が開催されるのでそれには参加させてもらうことにしました。 30数名の参加者の食事用意のお役にでも立てばと12月3日、午後1時半に到着しましたが、午前中でほとんど終了しましたとの事、それではと「鳳来寺本堂」まで、1425段を登る事にしました。 では出発します。   一の門、午後2時ごろ  国指定重要文化財 建物鳳来寺仁王門、 この門は、両脇の仁王像・鳳来山東照宮とともに、徳川3代将軍家光の命により、慶安3年(1650)着工、翌年4代将軍家綱の時完成した。 この華やかでドッシリとした門をくぐった後から、なぜか崩れかけているもの、朽ちかけているものにカメラが向かいました。 〜NO1〜   「医王院」 「松高院」 「医王院」が万治元年(1658)、徳川家綱の建立。 「松高院」の創建年月は不詳とされているが、ほぼ同格というからその前後に立てられたものだろう。 「松高院」は代々東照宮の守役をしていたが、この地が廃寺(増道院)となって参道中腹の現在地に移されたとあった。 徳川全盛時代には将軍家綱の側室の仮寓といわれている。 「医王院」が真言学頭で百石、「松高院」は天台学頭で百五十石となっているが、鳳来寺は、真言・天台兼併の寺院であったから、松高院と医王院が交代に3年づづ学頭を務めていたと紹介されていました。 写真からは分かり憎いかと思いますが、草むらの中にある「医王院」です。 「松高院」は戸が閉められていましたが、石垣をよじ登って中に入ってみました。 思い描いていたのとは格差がありましたので、かなりの造作の山門を紹介する事にします。   仮本堂 現在の本堂 カメラアングルと背景の関係で、仮本堂のほうが大きく立派に見えるかもしれませんが 、背景を見比べてください。 大きさは問題にありません。 が、華やかな現在の本堂より風雪に耐えた仮本堂のほうが私にはありがたく見えました。 そのためでしょうか、仮本堂と現本堂の中間にある朽ち始めている建物に気が入り込みました。   同じ角度ですが、背景に紅葉を配置すれば雰囲気が変わるのかと思いましたが・・・ この建物の裏手に回ってみました。   漆喰が剥げ、窓は吹き飛ばされていました。 その側には廃材が野積みされていました。 多分250年以上前の建物と推測しました。   何を登場させたか、お解かりになるでしょうか? 大きな岩の下に並んだ石仏群です。 右の写真はその大岩が崩れてこないように、鉄柱が支えているのです。 こんな鉄柱でこの大岩が支えられるとは思えないのですが、最近「耐震強度偽造」による欠陥建築に比べれば、信頼が寄せられるのではとおもいましたが・・・ その証拠に、石仏さんは安心しきった様子で晩秋の陽を浴びておられました。  約2時間半で、元の「一の門」に下ってきました。 山の向こうに陽は沈み、急に気温が下がってきたのを感じました。 |
||||||||||||
| 前のページはこちらからどうぞ |















