 |
|
||
| 平成17年12月26日 記 |
お知らせ |
| エッセイ F「文化、スポーツ活動(講演会、勉強会)に 『中部大学「オープン・カレッジ」の聴講生、1年を終えて』を掲載しました。 エッセイなどというものではありません。 いやこういうのもエッセイというのでしょうか? 長いであります。 |
| COLUMN1ーD NO.420 平成17年12月25日 記 |
百姓学校、本年最後の定例会は”餅つき”です。
|
| 忘年会でも、Xmasパーテイーでなくとも、毎回アルコールの量は変わりません。 それでも忘年会という事で、今年の夏から豪華「恵比寿ビール」が定番のビールになりましたが、今月は更に上を行く「イギリス産」と「ドイツ産」が加わりました。 350ミリリットル換算で、450円のビールでした。 やはりそれだけの事はありましたと、お酒の話から入りましたが、今冬最低気温マイナス9度を記録した、瑞浪・日吉です。 ノーマルタイヤですので、もちろんチェーンを持参いたしました。 山に入りユルユルと走って学校の導入路までは到着しましたが、ここでチェーンを掛けることになりました。 この雲空を見ていただければご理解いただけるでしょう。  さて、田も畑も全て雪ノ下です。 本日は「餅つきの手順」を紹介することにします。    ①水に浸す ②水揚げをする ③蒸篭です。 ①「餅米の水洗いと水浸し」←これは前日の作業です。 水洗いは最初シッカリと押し洗いします、その後3回すすぎをして、約12時間水に浸します。 ②翌日、蒸す前に水切りをします。→今年はここで失敗しました。 水切りをしないまま蒸篭(せいろ=蒸し器)に入れたため、時間もかかりましたし、上手に蒸しあがりしませんでした。 →2臼目からは正常に。 ③蒸篭を用意します。   ④蒸し専用のフキンです ⑤水揚げした米を入れます ④蒸し専用のフキンです。 このフキンが重要な役割を果たしてくれます。 ⑤蒸し器に入れますが、真ん中を掘り下げ、縁を盛り上げます。蒸気の廻りよくなる。  ⑥蒸します 炊き上げの時間は火力の状態によってマチマチですが、このように重ねて蒸しますので、調子が出てくれば早いのですが、平均40~50分でしょうか。 蒸し上がりの判断は活字では伝え難いのですは、指で軽くすり潰して柔らかい粘りを感じた頃です。   ⑦搗きます ⑧今回は袋で延ばしました。 ⑦搗き方、手返しは現場で体験してください。何でも力任せに搗けばよいというものではありません、初めから強く搗けば米が飛び散ってしまいます。 杵の重さにもよりますが、杵自身の重さに任せれば充分です。 ⑧今回は市販で板伸し餅専用の袋で大半を仕上げました。 伸し板は撮影を忘れてしまいました。   ⑨固めます ⑩切ります ⑨⑩一昼夜寝かせてから切ると上手く切れますが、本年の気温でしたら搗きあがって4時間経過のものでもキレイに切れました。 以上ですが、この間搗きあがった餅を食べたり、寒いのでイッパイやりながら「おつまみ」を摘まんだり、自家製の小豆の餅いり善哉を食べたりで「今日は空腹感を覚える暇がなかった」と出っ張った腹を摩っていました。 もちろん夜は囲炉裏を囲んでの談義は相変わらずでした。  |
| COLUMN1ーD NO.419 平成17年12月23日 記 | |
今冬4回目の積雪です
|
|
約束していた計画がこの雪では出掛けられません。 それではと長靴に履き替えて雪の降る中に出てゆきました。 祝日のことでもあり交通量が少ないためでしょう、道路には雪が積もってます。 幹線道路に出るとチェーンを巻いたJRのバスは運行していました。 カメラを片手どころか、三脚を持ったアマチュア・カメラマンが緑化公園・大久保池周辺で5~6人と出会いました。 私はジックリと言うよりは目に止まる、アッいいな!と思えばパチパチです。(今はパチパチとは言わないのかな?)   大久保池 グリーンピアのXmasツリー 園内に入ると門松が雪を被っています。   管理棟前の門松です 管理棟内の花モチ    名前忘れました 園内の池にはカモたちが アケビです  カモたちが泳いでいる池です。橋の上は、まだ誰も歩いていません この後、10時ごろ雪が突然止みましたので、”ヨシャー!”と久しぶりに西高森山に登ることにしました。 狭い道の両脇から雪をイッパイ乗せて、木々が道を塞いでいます。 私が本日、最初の登頂者です。 春日井市から名古屋のJRツインタワーまで見通せるかなと想像していましたが、再び降り出した雪でそれどころではありませんでした。 それでも、真っ白な世界を誰かに届けたくなり、携帯電話を取り出しました。 西高森山の映像はありません、どうぞ目を閉じて想像してください。 最後は少年自然の家の作業道を歩きました。 「トリム」(広辞苑で調べたら、<心身の調和と健康増進のための各種の心身運動を行うこと。 トリムうんどう>とありました)の遊戯場では雪を被った遊具がヒッソリと寂しげに見えましたが、撮影を終えた時に、小学生の兄弟が雪投げをしながら走ってきましたので、キットこれからここで遊ぶのでしょう。    2時間は歩いたかなと思っていましたが、何と3時間,時計は正午を回っていました。 |
| COLUMN1ーD NO.418 平成17年12月22日 記 | |
「野球の何が好きか」と問われたら何と答えます?
|
|
| 今週で中部大学の講義が終了します。 昨日は「アフリカを知る」の最終講義に、「JICA(国際協力機構)中部の・提携促進チームのリーダー・友成 晋也さんがこられ、お話を聞かせていただきました。 彼は学生時代(高校~大学)から野球が大好きでした。 大学の時は補欠にもなれずベンチに入れなかったということです。 卒業後、1996年から8年間、アフリカ・ガーナのJICA事務所に勤務され、ガーナ・ナショナルチームとの出会いがあり、その体験を通じて国際協力観が劇的に変わったお話を聞かせてくれました。 ナショナル・チームと書きましたがこの国には1チームしかありません。 ガーナからはキューバ(世界的に野球の強い国です)に技術研修に行ったメンバーが帰国後、野球チームを作って楽しんでいた。 友成さんにコーチをしてほしいと依頼があった。 土・日曜日が練習日となった。 <なを、この話は数年前、フジテレビが1998年から3年間バラエテイー番組「アンビリバブル」で取り上げられていたそうですから、視聴された方もいるかと思います> さて、色々と興味のあるお話が聴けたのですが、その中での最高のお話が、「野球の何が好きか?」と問われた少年が何と答えたかということです。 この後を直ぐに読まずに一度考えてみてください。 答え「バッター・ボックスが好き」と答え、其れはバッターボックスに居ると皆が応援してくれる、皆が注目してくれる。といったそうです。 また、このようにも答えたそうです。 「Baseball is democratic sport!」 野球は「民主的」なスポーツだ。 皆がヒーローになるチャンスが公平に来る。というのです。 彼らの父親は50%が失業している、だから子供達は学校にやれない。故に子も知識不足で就職できないという「貧しさの連鎖」が続いているという事です。 話は少しそれますが、その子の家を訪ねたら1家族は父母、祖母・祖父、兄弟にとどまらず親戚・知人まで同居していたとの事です。 失業率が50%なのでこうして共生社会の構成になっているとの事でした。 また、豊かな家庭は少子で高等教育を受ける事が出来ますが、貧しい家庭は乳児死亡率も高く、多産ということです。 友成さんは”スポーツの持つ可能性と恵まれない地域の子供達こそスポーツを”と帰国後も様々な活動をされておられます。 道具がなくても出来る「三角ベース」の普及プロジェクトやアフリカ野球の自立発展のための野球道具の生産をアフリカで産業化するということなどです。 最後に「アフリカの2ウエイ アプローチ」という事を語られました。 「開発」其れは「人権問題」と「環境問題」。 開発問題で見逃していけないのは「人間らしさ」という視点であると。そして人間の安全保障=人間が生きてゆくためには 「人間として生きてゆく権利」と「人間らしく生きてゆく権利」、 これが、2ウエイ・アプローチと。 以上のような素晴らしく・良い話を掲載した後に載せるのは気が引けるのですが、聴講生には提出義務はない、『「アフリカを知る」の講義を聴いて、新たに発見したことや感想を書きなさい』と宿題が出ておりましたので、教授にお礼の意味をこめて以下のような一文を提出しました。 アフリカを知る B 1、 氏名 加藤大喜 2、 学籍番号 YG05047 3、 「新たに発見したアフリカ」レポート A) アフリカはやはり大きな大陸である。 今春期と秋期、“アフリカを知る”を受講したが地理的にも、時間軸に換算してもほんの一部を撫ぜたに過ぎない。 正に「群盲象を撫でる」の如し。 愛・地球博のステージで単調な太鼓のリズムに乗って体全体で表現された力強いダンスから感じた感覚が思い出される。 其れも時間の経過とともに薄くなり、忘れ去られてしまうのだろうか。 B)サハラ砂漠以北のアフリカは、地中海に面した地をギリシャ(オリエント文明)、ローマ帝国、そしてイスラム勢力が通過し、拠点化した都市・国とは全くサハラ砂漠以南のアフリカは別ものであることを改めて感じた。 C)そのサハラ以南のアフリカはきっと外部の勢力が押し寄せてくるまでは、数知れない民族と言語からなる人々が穏やかな生活をしていた事だろう。 また、海の海路を中心として友好的な交流を通じ、豊かな文化が育まれていたことだろう。 西欧の膨張が押し寄せてきた時、殺戮と収奪によってその様相は一変する。 其れは売買の対象としての奴隷貿易の時代にとどまらず、先進国の利害・利権丸出しの政策が、アフリカ民族同士の対立と抗争にと尾を引いてゆく。 →余り意識せずに講義で使用された同じ番組を見ていたが、授業で取り上げられたことにより、その意味するところを考えさせられることとなった。 D)日本とアフリカの関係についても新たな発見をしました。 文明開化に続く「富国強兵」の下に、アフリカが研究され、地元豊橋の中村直吉なる人物の事も初めて知りました。 大恐慌前の大正10年には「からゆきさん」が存在したことも、日本商社の進出の事も今回初めて知ることになったことです。 E)「ジンバブエ遺跡」のことも発見でした。 「アフリカは人類のゆりかご」という単語は使っていたものの、実態は「暗黒の大陸」「未開の地」「奴隷の国」という言葉で教えられた事以上のことは知りませんでした。 ジンバブエ遺跡のことは驚きでした。 きっと、まだまだ知らない事、発見されていないアフリカが眠っていることなのではないかと思います。 既成概念でことを判断してしまう事の危険を教えられました。 ありがとうございました。 |
| COLUMN1ーD NO.417 平成17年12月21日 記 | |
「シャキュ・ジュ・キュッ・キュッ」
|
|
| 20日の夕方散歩に出掛けました。 その時、落ち葉の上の雪を踏んだり、小石と落ち葉の組み合わせの雪の上を歩いたりしました。 本日明け方(4時半)目覚めた時、昨日の散歩時、雪の上を歩いた時に感じた音をメモしてみましたが、「本当に、そんな音だったかな?」と疑ってしまいました。 ストレッチと掃除、そして礼拝を終えました。 本日は1週間の内で一度、放送大学の授業がない曜日でしたので、メモした音を確かめにゆきました。(AM・7時半~8時半)  まづは、「「コンクリートの上に残った雪の上」を歩きました。 寝床でのメモより→「ビュシャッツ、ビュシャッツ」 本日の感じ→踏まれていない雪の上→「シャキュ ジュキャッツ」 →踏まれた雪の上→ →「バリュジュ バリバリ」 昨日は夕方、陽が沈もうとしていた頃です。 以下、同じ条件です。  ・「落ち葉と小石が混ざった道の上に雪が残っています。 ・寝床メモより→「パシュ パッリ、バシュ パッリ」 ・本日の感じ→「シャキュ バリバリ 、シャッキュ バリバリ」  ・『落ち葉のみ、その上に雪です。 ・寝床のメモより→「ギュギャッバッ、ギュギャッバッ」 ・本日の感じ →「シャシュッバ シャシュッバ」  ・「橋の上」です、まだ融けていません。 ・寝床のメモより→記録なし ・本日の感じ →「キュッ キュッ」でした。 私の記憶というのでしょうか、思い出して想像したものと、本日の感覚はかなり異なりました。 きっと音を文字で表すと、その時、異なった人間が同じ体験をしてもきっとかなり異なる表現がなされる事でしょう。 また、同じ人でも、その時の精神状態や体調によっても異なる事でしょう。 昨日と本日は3日ぶりの散歩でしたので気持ち良かったです。 普段のスピードの80%、歩幅も80%というところで、しかも大変汗をかきました。夜はグッスリでした。 今朝の散歩の帰り道に撮影したものを紹介します。   地生え(自生)のシデコブシ 17年4月7日(NO238)で紹介の同じ場所   シデコブシと同じ「少年自然の家」にあります、テント村   少年自然の家の宿泊棟と事務所の前です。 横綱「春日井山」です。 |
| COLUMN1ーD NO.416 平成17年12月20日 記 | |
大雪の次の日、中部大学にて |
|
| 放送大学は半期の講義が15週あり、12月28日が今年最後の講義ですが、年明けにも1月5日より2週あります。 中部大学は半期が13回ですので、今週で終了です。 一番興味を持って聞いていた教授が13回では少ないと言っておれれましたが、来年からは半期15回となるそうです。 13回も15回も休んでばかりの学生には関係ないでしょうが、真剣な学生には内容が濃くなり、歓迎の事だろうと思います。 私は真剣な方になると思っていますが、モウこの辺でボツボツかなという講義もあります。 正月休みをしていると再び意欲が湧いてくるのではと思っています。 本日のキャンバスにはアチコチに昨日の大雪の跡が残っていました。   御馴染みの噴水池。凍っています。 人工芝のグランドです 噴水池に学生が大きな塊の氷を投げ込むのですが、北向きなので張った氷が厚く割れません。 人工芝のグランドでは何時もキャッチボールやサッカーをしておるのですが、本日は誰一人居ませんでした。 その代わりにカマクラが造られていました。   画面右の奥がカマクラです 高さは1・3Mほどです カマクラの反対側には階段が出来ておりまして、表彰台のように登ってゆけるようになっていました。 |
| COLUMN1ーD NO.415 平成17年12月19日 記 | |
今冬3回目の積雪です。 |
|
| 報道によると名古屋は昨夜から今朝までの積雪が23センチメートルとの事ですので、目測で見る限り今回は我が家付近より名古屋市内のほうが多かったようです。 風の流れの性でしょう、恵那・多治見方面からの時がこの辺りは積雪が多いようです。 何度も紹介しましたが、我が家から車で出る時はチェーンをかけました、ニュータウンの中心地まで2Km走るとチラチラ、国道19号線に出たら何もなしという事が、車通勤していた頃、数年に1~2回ありました。 さて、毎度の事ながらカメラを手に庭に出ました。 (今回は遠出はやめました)   何時もなら、シャッターが向けられることのない「一本杉」(左)です。 夏場を過ぎ頃はボウボウと茂っていますが、晩秋の剪定の時期になりますとバサリです。 庭師の腕がいまひとつなのか姿・形は褒められませんが、本日は雪をのせておりましたので目に止まったということでしょう。 右の写真もただ1箇所、庭が真っ白になっているのに「ユズ」だけが輝いていましたので掲載対象になりました。   春日井三山方面を 春日井三山の隣 左は道路の雪が融けて車が走り出した頃に 右は毎度御馴染みの書斎からですが、本日は春日井三山の更に右方向です。 普段ですと「砕石場」の赤肌が見えますので敬遠するのですが、本日はダンダン状のところに雪が積もって見苦しくありません。(写真左奥と右の白いところです) 一般的に見て、シャターアングルとしては遠慮するところですが、遠くシベリヤから運ばれてきた寒気団のもたらした雪によって私の目に止まったモノが掲載される事に成りました。 時代が変わり、環境が変わると見過ごされていたものの価値が見直されたり、捨てられていたもの・見向きもされていなかったモノが脚光をあびたりすることがあります。 今という時代、変化する状況や環境の中、身近なところに転がっている宝石があるのかなと積もった雪の下をかき分けて見ました。 |
| COLUMN1ーD NO.414 平成17年12月18日 記 | |
「波動の会」東海ブロック・インストラクター忘年会
|
|
| 『観察の重視や技術的な工夫の進展が顕著に現れはじめたルネッサンス期、さらに17世紀の科学革命といわれる時代、これらを経てヨーロッパでは、科学的な実験や発見が積み重ねられてきた。 大まかに拾ってみると~ ・17世紀後半の農法の技術改良、農機具の改良実現、家畜の品種改良、干拓や排水事業の推進→食糧事情の好転ー飢餓という危機からの脱出開始された。 ・プロト工業のカ=本格的な工場における工業生産の前段階→動力を用いた機械制の工場→動力を正確に伝えるしくみや作動する機械→ユニットとアセンブルの正確さと分業→→”機械時計生産”の手工業←『時計産業』が産業革命を用意した。 18世紀後半にイギリスで、開始された「産業革命」=ものの生産が機械によって行われる。 その機械も動力の機械を使い自然力以外の力によって供給。 機械制大工場。 新エネルギー石炭の火力で蒸気を作る機械→ジェームス・ワットによりピストンの往復運動を回転運動に(1781年) この間に、政治・経済・社会システムも新時代の到来を告げる変化をしていた。 特に技術的な先進性と優位とが、19世紀を「ヨーロッパの世紀」とする大きな意味を持っていた。 科学技術の発展と工業化の進展は切り離す事はできない。 19世紀後半、科学技術の進歩は急展開、現実の社会や経済を大きく変貌させた。→人々の暮らしのあり方、行動の仕方、ものの考え方という面も大きく変え始めた。→人間生活や価値観の世界まで変える、文明的な変化が生じた。→「産業文明の成立」と呼んだ。』 以上は放送大学「近代ヨーロッパ史」 福井憲彦教授の教科書より引用した。 上記のとおりの記述がなされていたのではありません、私が選択し、あるいは割愛し、つなげ合わせたものです。 よって真意を正確に伝えていない事もありえます。 文責は私です。 さて、放送大学の後期の試験を1ヵ月後に控えておりますので、少々試験勉強をしたわけではありません。 「波動の会」の説明をするために書き出したのですが、どのように関係つけるかいささか思案中です。 いま少し教科書からの引用にお付き合いください。 と言いますのも、これは現在私たちが心の片隅で、あるいは人によっては現代社会の矛盾や弊害の現象化に憤りやアキラメを感じている。 先行きに希望が感じられないと感じたり・思っていることと、いささか関係があると思えるからです。 科学一辺倒、あるいは福井教授の言葉をお借りすれば『「産業文明」から次の段階へと展開する文明史的な転換期にあるのが21世紀と言う、今』と言うことになります。 『科学技術の進歩と応用」 ・「電気の実用化」からみましょう→ランプやガス灯から「電灯」、家庭製品の全て、コンピューター、携帯電話の充電、動かないオモチャ。鉄道のスピード、船舶輸送に置ける大型化と安定度、 ・19世紀末「自転車」もスピードのある快適な移動手段として登場。 ・自動車は言うに及ばないでしょう。 ・海底ケーブルは地球上のあらゆるところに→そして宇宙衛星による携帯電話。 「見えないものを見る」 ・細菌→殺菌法の開発、予防接種←1880年狂犬病の予防接種 ・結核菌、コレラ菌の発見と対策。 ・上記の伝染病の対策にから「社会衛生」に→健診による身体衛生、上下水道などの社会衛生、→其れを支える合理的な考え方、行動の仕方、道徳心という、社会に対しての近代的な思考や行動を説く、近代的な思考の伝道者の役割(パスツール、ゴッホ) ・精神分析の試み→フロイト「夢の解釈」→人間の深層心理を捉えることの出来る、普遍性を持った理論が可能である=合理的な説明原理をたて、不可知論にはならない。 ・放射線、原子核物理学→目に見えない働き、ミクロの世界へと進歩→分子生物学、遺伝子学へ』 さて、このように「科学技術の時代」は進展、進歩してきたのですが、人類の悩みを解消することが出来ただろうか。 出来た部分もあるが、更に一層見届けられないところにもぶつかり、もがいていると言うことも出来るのではないだろうか。 更にこの先、今までの延長でこのまま進む事の危惧を抱かないわけにはいかない。 仮に、其れが現代社会を生み出した「科学技術の発展」に端を発する、ものの見方、価値観、それにもとずく政治・経済・社会のシステム・仕組みであるならば、その根本から見直さなければ輝き希望の21世紀はならないと言うことになると考えます。 さて、「波動の会」との関係ですが、ここまで入力してきまして、今まで「波動」と言う単語は聞いた事はあるが内容は知らない、あるいは「波動」なんて言葉は聞いた事もないと言われる方に、私のイイカゲンな知識や体験では到底理解していただけないと思います。よって本日はここまでといたします。 「波動」の事、「波動の会」の生い立ち、活動状況、これからのことなどをお訊ねになりたい方には適切な著書や写真集、集会等のご案内を差し上げるに適任の方を紹介しますので、連絡ください。 12月17日「波動の会・東海」に参集したメンバーは見えない世界の事を本気で話しても、不思議がりもしませんし、否定もしません。 逆に其れはありうることと肯定するメンバーです。  そんなメンバー達と年に約10回程、メンバーの一人が所有する名古屋、伏見のマンション12階でお酒を飲みながら日本・世界の政治・経済・社会について談義をしております。 人生相談もありです。ご興味がありましたら気軽にどうぞ。 |
| COLUMN1ーD NO.413 平成17年12月17日 記 |
このような方々が学んでおられます
|
| 年に4回、放送大学の愛知学習センターの事務局から「しりあい」というタイトルの情報誌が送られてきます。 その54号に平成17年度2学期 の在校生の概要が掲載されています。 紹介してみましょう。 教養学部は「全科履修生」(一般に大学卒業を目指す)方、1771人、選科履修生(私はこれです)806人、科目履修生360人、特別聴講生7人の合計2944人です。 大学院は238人です。 総トータル3182人です。 1992年は2学期が合計で481人ですから6・6倍という事になります。 住所別を見ますと、もちろん名古屋在住の方が多く1130人(内訳、千種区192人、緑区133人、天白区125人、少ない区は、熱田区の24人、港区の34人、南区の38人です。 名古屋市以外では春日井の166がトップ、続いて岡崎市の159人、豊田氏の150人です。 郡部の北設楽郡にも4人おられます。 岐阜県86人、三重県64人。 教養学部の学生の種類別を見ると、男女比が男40%、女性60%です。 年代別では20代16・4%、30代30・6%、40代25・6%、50代16・4%、60台以上11・7%です。 科目登録ランキングはテレビ科目では①「人体の構造と機能」 ②「食品の成分と機能」 ③「感染症と生体防御」 ④「基礎看護学」 ⑤「在宅看護」で。 ラジオ科目は①英語の基礎 ②「リハビリテーション」 ③「心の健康と病理」 ④「発達と教育の心理学的基盤」 ⑤「家族のストレスとサポート」となって居ます。 コメントはありませんが、お読みになってどのような感想をお持ちになりましたか。 私はここでも女性の数の多さを発見しました。 其れと60台以上がもう少し多いのかと思いましたが、1割強でした。 学位を取得された方は平成3年3月でに全国で1223人、平成17年9月で2315人 この間の総数は37429人、うち愛知学習センターは641人とありました。 |
| |
| COLUMN1ーD NO.412 平成17年12月16日 記 |
晩酌がほろ酔い程度ならよいのですが・・ |
| 11月購入のボージョレ・ヌーヴオーがまだ半ダース程残っています。 初めはいつも朝飲んでいる箱ワインと代わりがないのではと感じていましたが、本日飲み比べるとやはり美味しいです。 大事に飲まなくてはと思っているのですが・・・ 私、百姓学校の嗜好品の調達係をしております。 夏場は私もビールはいただくのですが、秋が深まるのつけてビールは遠ざかります。 その夏場でも発泡酒や第3のビールで充分なのですが、ビール好きのメンバーから本物、しかも出来る事なら「エビスビール」がよいという注文が参りまして、8月よりエビスビールおよび本物ビールに切り替えました。 エビスビールあるいは本年から登場のサントリーのプレミアムは1本当たり特売の時を狙うのですが200円いたします。(ちなみに発泡酒は約100円です) 本日の朝刊に愛・地球博を機に復刻された「カブトビール」が23日、かって同ビールが製造されていた半田市榎下町の国登録文化財「赤レンガ建物」で販売される。との記事を読み、早速電話中なのですが、話中ばかりです。  話しかわって、晩酌時のことでございます。 大抵は日本酒から始まりますが、時にワインから日本酒、(ジントニックやブッラデイーマリーもあり)、そして焼酎、梅酒(2~3年もの、自家製)~最後にブランデイーかウイスキーのロックで寝床です。 この間に、時折間違いが起こります。 といいますのはこの時期、今までに購入した醸造元から次々に進物用や今年のお酒品評会で上位入賞を伝えるパンフレットが届きます。 何を、何処にファックスしたのか、電話をかけたのか忘れてしまう事です。 ファックスはまだ残っていますから良いのですが、電話がいけません。 1週間の間にダブって配達されてきます。 其れはそれで大変嬉しい事なのですが、置き場所に困ってしまいます。 今年は大変寒気が厳しいので助かっていますが・・・ という事で、注文品の記録を残しておくことにしております。  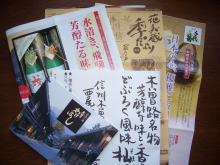 納品書、請求書、配達証明など 各種蔵元からのパンフレット 今週も明日から再び寒気到来とのこと、冷酒、燗酒、にごり酒を楽しみます。 |
| COLUMN 1-D NO.411 平成17年12月13日 記 |
今冬2回目の雪が降っています
|
今年の12月は寒いと言われていましたが、6日の朝に続いて今冬2度目の積雪です。 今回は現在午前10時ですが、粉雪が舞っています。  COL COL書斎からの春日井3山の大谷山方面の角度ですが、『コラム1-D NO404』と比べてください、雪が舞い大谷山が写っていません。 前回はスリッパで庭に出る事が出来ましたが、今朝は長靴に履き替えました。 まだ青い青木の実をヒヨドリでしょうか、啄ばんだために3^4個、玄関先に転がっていました。    沈丁花 ロウバイ ミニばら 1・5坪の庭の隅の畑からスズメが飛び立ちました。 残飯でも漁っていたのでしょうか。 電線にとまったカラスがそれを眺めていました。    松です。 魚の鋳物にも。 ミニシクラメン 車にはチェーンを積み込みましたが、雪の降るときは出掛けたくありません。 3年前に、充分注意して徐行していたのにスリップしたことを思い出しました。 皆さん、御気をつけて。風邪にもご注意を |
| 前のページはこちらからどうぞ |