COLUMU1−D NO469
平成18年3月3日 記
雛祭りというのに、最後の寒のもどりでしょうか。
|
「灯りをつけましょボンボリに、お花を上げましょ桃の花・・・」とラジオから流れてきました。 というのに南北のドアーを開け放ってのストレッチ体操ですが、身体が温まるまでに時間がかかりました。
体操を終えて庭に出てみますと、乳鉢(戦前から昭和30年代まで、薬屋の我が家で大量調剤のために使用していた、くすりの攪拌道具です)に薄っすらと氷が張っておりました。 咲き時を間違えた「雪柳」が一輪寒そうに震えていました。
 
乳鉢に薄氷が・・・ 咲き時を間違えた雪柳一輪
周りの春告げ蕾の情況はと申し上げますと、以下のようです。
  
ハナカイドウ 希少種シデコブシ ボタン
庭に出たのはこれが紹介したかったからです。
 
ソラマメ 絹さやエンドウ
昨日、今までは鳩やカラスから新芽を防御するために、横に張ってあった網を縦に張り替えました。 特に絹さやエンドウが日増しに成長して、横に倒れるようになっていたからです。 持ち上げてみればそれほどに成長していなかったのですが、これから日ごとにドンドン背を高くしてゆくことでしょう。 4月末か、遅くとも5月初旬には新鮮なエンドウが朝の味噌汁の具となって浮かんでいる映像が浮かびました。
|
COLUMU1−D NO468
平成18年3月2日 記
サンシュが春を呼び込んできてくれました
|
梅の花は間違いなく2〜3週間遅れています。 昨年12月と今年に入って1月が寒かったせいでしょうか。 2月に入り気温が平年並みになると、開花予想の出たソメイヨシノも平年並みとの予報です。
我が家の庭のサンシュも遅れを取り戻したどころか、日増しに蕾をふくらませ、昨年は3月17日、「コラム1−D NO217で、満開のサンシュ」と掲載されていますが、それよりは早く開花するのではないかと思います。
 
昨日(3月1日)雨の中、脚立を持ち出して撮影しました。
下から見上げていますと、とてもこんなに蕾が膨らんでいるようには見えません。
ベランダから眺めてみますと、間違いなく色づいているのが分かりました。
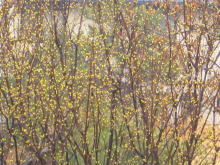
 
左、街路樹のナンキンハゼ&サンシュ 左から「花の木」「桧」「サンシュ」「栗の木」
毎年同じことを書くのですが、春は「黄色」=太陽の色から始まります。 |
COLUMU1−D NO467
平成18年3月1日 記
雛飾り またまた増えていました
|
昨年は2月22日、コラム NO200で紹介しました雛飾り。 今年はやっと2月26日ごろに全員揃ったようです。 と申しますのも、昨年のものと比べてみましたら、その数が増えていました。 確か、昨年は12組と思いましたが、今年は少なくとも16組はあります、写真に登場仕切れないものもあります。
しかも昨年あったものが、今年は見当たりませんので、この間数組は増加していると思います。 画面にあるばかりでなく玄関入り口にもお花ともども一対ありますので、少なくとも20組以上の内裏様とお姫様でございます。
昨年の写真を今から拾い出して見ます。

2005年、平成17年2月22日

2006年 平成18年3月1日 撮影
それよりは、思いがけない写真が撮れました。暖房の効いていない部屋においていたカメラを持ち込んで、生け花の花を撮影したところ、霞がかかった春のお花となりました。
 
麦とフリージア 麦
 
桃の花とフリージア 菜の花
たくさんシャッターを押していますと、思いがけないものが得られます。
|
COLUMU1−D NO466
平成18年2月28日 記
雨模様の2月28日、2月最後の日に整理
|
朝から曇り空です。 まだ散歩に出かけたわけではありません。 こんな時もあろうかと記録だけ残しておいたのですが、既に(たった数日ですが・・)パソコンの何処にしまっておいたのか忘れています。
多分2月24日「コラム NO464」の日に撮影したものだと思います。
たった4日前で、時が過ぎ、忘れ去られていることに驚きます。
 
植物園内のドングリ植樹地 室内用のファイヤーストーム器
知人から「室内用のファイヤストームとはどんなものか?」との問い合わせがありました。 ご覧のとおりの器?、クド?、カマド? です。
植物園内のドングリの植樹は確か199?年、秋の東海豪雨で崩れた跡地です。
昨日の散歩のときに「元気牧場」の4匹の馬達です。
 
高台より逆光で撮影 近づいて
珍しく4頭が揃って厩舎から出て、柿ノ木の側にいました。 暖かくなったとはいえ、まだ外套(マント)を羽織っていました。
追記
エッセイーC 「自然との交流」2月27日・記で、材木運び後の疲労度のことを書いた。
本日がさらに痛みを伴った症状が出るかと心配していたが、日頃のストレッチと散歩の効果によってか、ほとんど疲労感も違和感もなし。
続けることの大切さを教えられた。 此処に其のことを記して怠惰になることを監視していただくことにする。 よろしく |
平成18年2月27日 記
お知らせ
|
エッセイ C 「自然との交流」に掲載しました。
「農閑期・2月の百姓学校 2月25〜26日
〜無農薬、有機栽培の小麦粉による煮込みうどんは・・・・」 |
COLUMN 1−D NO465 平成18年2月25日 記
気づいたり、気づかなかったり、此処にも春が・・・
|
暖かさが増せばやはり気分よく散歩に出かけるのが一層楽しくなります。
大分前から植物園の管理棟の玄関先に置かれていたそうですが気づきませんでした。 「愛・地球博」のときグローバル・ロードを走っていた身障者用のエコカーが展示されていました。(春になれば園内を走ることでしょう)
  ・・ ・・
2月26日中日新聞・朝刊に『愛・地球博の”足跡”どうぞ』と・グローガル・ループで使用していた材床で作った置物2500個の無料プレゼントが発表されたと紹介されていました。 早速、返信用葉書5枚で応募しましたが、当選するでしょうか。
園内の小さな梅園の開花はまだのようでしたので、竹林に向かう通路を反れて枝打ちされて明るくなった数本のヒノキの丘に向かう石段を登ってみました。 直ぐに行き止まり、雑木林を掻き分けるとほとんど水枯れした小さな沢を渡ることになりました。。
飛び越せそうでしたが足でも挫いてはと一度沢底に降りて、むかえの土手に足をかけたとき、そこに枯れ葉に埋もれた「ショウジョウバカマ」の姿を見つけました。
枯葉を払って撮影です。
 
カメラに収めた後、枯葉のフトンを再びかけてやりました。
枯葉に埋もれたり、梢高くソッと芽を吹き出している春は余程注意して観察していないと見落としてしまいます。 |
COLUMN 1−D NO464 平成18年2月24日 記
正に、梅一輪咲きました
|
コラム1−D NO221(2月21日付け)で、春日井植物園の蕾の梅を紹介しました。
22日、23日と暖かい日が続きましたので、今日当たりは開花しているだろうと再び訪問しました。
 
どれだけ探してもこの八重寒紅(ヤエコウバイ)の一輪のみでした。 左はフラッシュなし、右はフラッシュありです。 その日の中日新聞夕刊に、名古屋城でも1ヶ月遅れで開花と紹介されていました。 写真の技術は相当違いましたが・・・・
其の隣に「ベニマンサク」が咲いておりました、マンサクは枯葉を全て落として咲いているのですが、このベニマンサクは枯葉をイッパイ付けていました。
梅林の中に移植されてきたものだからでしょうか。

ベニマンサク
何時ものコースを歩き終えて、自然ばえのマンサクの木のところに引き返し、写真におさめました。 ベニマンサクは背丈がまだ2メートル弱、接写で撮影しましたが、自然ばえは遠くからズームで撮影です。
  |
COLUMN 1−D NO463 平成18年2月23日 記
気持ちよい散歩をしたいのですが・・・
|
以前にも書きましたが、瑞浪市から多治見〜内津峠〜春日井〜大曽根〜熱田の港に通じる、庶民の街道・”下街道”(大名が通る中仙道に対して)があります。
内津峠(うつつとうげ)を下ったところで左折して、昔(江戸時代?)春日井の坂下に通じる間道でもあり、瀬戸・水野の代官所への重要な街道でもあった西尾(さいお)街道があります。
道幅6メートルで、しかも曲がりくねった危険な県道ですが、ダンプカーや通勤の車が走り朝晩は特に通行量が増えます。
年に2度ほど老人会と子供会が道路の清掃をしていますが、道路の両サイド共に雑木と竹やぶで、車からのポイ捨てで直ぐに汚れてしまいます。 特に冬場は葉を落としますので塵が目立ちます。 清掃されたばかりの頃は袋持参で少しは拾ってきますが、直ぐに追いつかなくなります。 中にはテレビ、冷蔵庫、布団やマットレスまで捨てられています。
 
街道に沿ってマンサクの木のあったのですが、今はまったく見当たりません。
西尾街道の峠のところから山道に入ります。 気持ちの良い散歩道になります。
西高森台の近くまで来ればマンサクの花が咲いています。
 
このマンサク、東北地方の「まんず咲く」がなまって、「マンサク」と呼ばれるようになったと聞いていますが、兎に角、汚れた空気のところでは直ぐに枯れてしまいます。
この辺りにはところどころに自生のマンサクが群生していまして、この時期の楽しみです。 西高森山に2ヶ月ぶりに登ってきましたら、こんな標識がありました。
 
三角点には確か「1等三角点」から「3等三角点」まであると聞いたことがあります。
此処の標識には「3等」も、まして「1等」もありません、それでも「三角点」の標識が立てられたのはキット何かの目印として大切な地点だからでしょう。
春日井市から名古屋のセントラル・タワーまで(冬場の空気の済んでいるときには息吹山まで)眺められます休憩小屋の横の朴の木に、ミカンとグレープフルーツが枝に差込まれていました。 グレープフルーツはほとんど啄ばまれていません。ミカンは上手にくり貫かれていました。
この三角点、野鳥のための三角点ではないと思いますが・・・・・・?

|
COLUMN 1−D NO462 平成18年2月22日 記
此処にも春がやってきた
|
もう直ぐ卒園、卒業の季節がやってきます。 通学路にもなっている我が家の西側の道路には「焼き物のプランター」に”桜草”が淡い花を咲かせ始めました。
 
昨日からもう一輪、大きな花が飛んできました。 次男が恋人を連れてきました。
私はその前夜まで何も知らされておりませんでした。 納戸として使っている部屋(私の着替え室にもなっている)に息子たちの部屋から、様々なものが運び込まれています。 「これは何だ!」と一言、「帰ってくる」とだけの返事にしては、普段何も手が入っていないところの掃除を始めるではありませんか。
結果はご覧のとおりでした。

これも春の花ですね。
|
COLUMN 1−D NO461
平成18年2月21日 記
春を探しにグリーンピアへ(春日井植物園)
|
我が家の庭の小梅の蕾が膨らみ始めました。 ベランダから見下ろすとサンシュの蕾も心なしか黄色に色づいてきたように感じました。
ならば、早咲きの植物園の梅ならきっと咲いているだろうと出かけてみました。
 
紅冬至(コウトウジ)、野梅系の極早咲きと紹介されていますが、上記が一番蕾が膨らんだものです。
  
八重寒紅(ヤエカンコウ)この品種も極早咲きと紹介されていましたが、やっと3枝の蕾を撮影できたのみでした。
植物園の梅で判断する限りは例年より2週間ほど遅いのではないかと思います。

馬酔木(アシビ)も負けずに色づいてきていました。
  
沈丁花(チンチョウゲ)科のミツマタです。 枝がすべて3本に分かれているところから名づけられたようです。 左右の写真は綿帽子のようです。

最後は夕日に照らされた柑橘です。名前は分かりません。
植物園の中のものですので、皆さん拾って行かないのでしょうか、それとも美味しくないのでしょうか。 私の口にはしませんでした。
前のページはこちらからどうぞ |
|




















