�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̃y�[�W�ȑO��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�����͂����� |
�@�b�n�k�t�l�t�@�P�|�c�@�m�n�V�Q�O
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����19�N�X���Q�W���@�@�L
|
�@�@�@��߂݂����i�Ƃ̑O�̏��w�Q�N���j
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@����A���莆�����Ă���܂���
|
�@���T���A�V���Ƀs���N�̕����������Ă���܂����B
�@�Ƃ̑O�̂�߂݂����ł��B
�@�@ �@�@ �@�@
�@���e�̓J�g�E�T���ւƏ����ꂽ���[�ւ̕��ʂł��B�u�����A��������قǂ��̂��肪�Ƃ��B�@���������B�@�����������I�I�v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�����āA�����ɂ́u���Ȃ��̂Ƃ��A���肪�Ƃ��B�@���̂���������I�I�v�@�@��߂݂��
�@�����̕\�����ɁA�h�w�Z�ŋߏ��̐l�ɂ��z���Ă�����Ƃ������ƂŁh�ƒf�菑���������Ă���A�@����������̂��ē����������Ă���܂����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@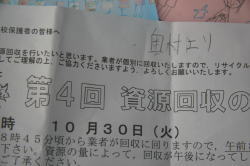
�@��S��ڂƌ������ƂŁA�����Ԓ��f����Ă��܂������A�e���������̉��z�̍����ɂ��A�P�N�O����ĊJ����܂����B
�@��ʂ̌��S��̍s���ɂ�����ƐV���z�B���̉���Ƒ��܂��āA�䂪�Ƃɂ͌ÐV���E�ʁA�r���ޓ��̍ɂ͏�ɋ���ۂł��B
�@�n�������ƊW���āA�������Ɉӎ������܂��Ă䂭���Ƃ��A�Ƃ̑O�̎����i��ʂ̐o���܂߁j����ꏊ�̏ŕ���܂��B
�@�ǂ��炩�ƌ����ƁA�����̂�߂݃`�����ł����A�q���͎q���Ȃ�Ɂi�C�₻��ȏ�Ɂj�A��l�̍s�����ώ@���Ă��邱�Ƃ��ǂ��킩��܂��B
�@�{�����A�v���Ԃ�̓����ł��B�@�@����̌f�ڂ͂P�O���Q���ȍ~�ɂȂ�܂��B
�@�X���̉��{������������ݍ����āA���N�͂܂���ˋ��R�̌I�E���ɂ��s���Ă��܂���B�@���������ĂƂ͌����A������R�̌I���҂��Ă���̂ł͂Ȃ����ƋC������ł��B
�@
�@�䂪�Ƃ̒�̌I�̖́A��N�Ǝ҂Ɏv��������荞��ł��炢�܂����̂ŁA���͗�N�̂P�O���̈�ŁA�܂��قƂ�Ǔ��H�ɗ��Ԃ��Ă��炸�A�����C�Â��̂�Y��Ă��܂����B�@�������͌I�̕����S�z�ł����A�����͂��ꂩ��̐��E�E���{�̕���ł��B�@ |
�@�b�n�k�t�l�t�@�P�|�c�@�m�n�V�P�X
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����19�N�X���Q�T���@�@�L
|
�@�@�@�F�l�̑��������ɁA���Ȃ��܂���
�`�����͍D���ȉԂ́u�֎ꍹ�v�A���N�͉ԏ��Ȃ��`
|
�@���͒��H�̖����߂ď��ɏA�������߂��B�@���邢�́A�˂��J���Ė���A�����̃q�����Ƃ����������ׂ��A�n����̉��K�ȑ̒��ł���܂��B
�@������̃R�����̂m�n�@�V�P�W�ɁA�F�l��肷�����܂̕ԐM���[�����͂��܂����B
�@
�@�u�M�N�̍��N�ɓ����Ă���́A���ɑD���A�C���h���s�Ȍ�̏�������ǂ݁A�A�܂����ŃC�b�p�C�ł��B
�@���̏�A�������ň�甍�����ƌ����A�I����Âɑ���ӎv�\������⌾�A���V�̎菇�ȂǁA�A�b�P���J���Ə��������A������R�����Ɍf�ڂ��Ă��܂��s�ׂɁA�A�܂�����ʂ�z���ċ������A���㉽����яo�����Ɠ����͐S�҂�����C�����ł������A�{���̃R������ǂ�ŁA�����g���ƂĂ��l���A�p�ӂ��Ă��Ȃ������̂ŁA�u���Ă��ڂ��H���Ă���悤�ȋC�����ɂ������Ă��܂��B
�@�܂��A����ȏ�ɂ��������I�I�J�~��ƌ����Ĕ�������Ă������Ƃ��A���ɎQ�c�@�I����ɁA���{�Ɍ��炸���E�̐����E�o�ρE�Љ�̂����鑤�ʂɒ���ƌ������́A�n�b�L���ƌ��ۂ�����Ă��܂��B�@
�@���̂��Ƃ��܂��܂��M�N�����ď������ʂ��ɑ��A���M���������Ă��邱�Ƃł��傤�B
�@���̏\���N���𗘂����A�傫�Ȋ炵�ĈВ����Ă����l���������C���Ȃ��Ȃ����A�����ɑ��l���ƍ��������Ă��������̐l�X���A���ʂ̕s�M��s���ɉ����āA���̐�ɕs�������n�b�L���Ǝ����o�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�i�����F�l�������ł��j
�@���̏�́A����ȏ�������Ȃ��ł��������B�߂Ȃ��Ƃ����Ȃ��ł��������B����Ȃ��ł��������B�@�ł��邱�ƂȂ�A�����Ƃ��͐S�x�܂邨�b�����Ă��������v
�@�@
�@�v��ƈȏ�̂悤�ȃ��[�����܂����B
�@����ɂ���������Ƃ����p�ӂȂǂ��Ă��܂���B�@�܂��A�����̂��Ƃ��u�I�I�J�~��v�ƌ����āA��������Ȃ����ƁA�N��������Ȃ����Ƃ��U���ɒ����Ԍ��ɂ��Ă������Ƃ͎����ł��B�@�F�l�E�m�l���Y�������Ă���Ɠǂݔ���Ă����悢�Ǝv�������Ă��܂������A��L�̂悤�ȃ��[�����Ƃ��������A���Ȃ��Ă��܂��B
�@
�@�܂��́A�����̂킪�Ƃ̒�ɍ炢�Ă��܂��D���ȉԂ̂ЂƂ��f�ڂ��܂��B�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����āA������́u�V�I���v�ł��B��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@���ꂩ��̂T�N�ԂŁA�����ł��߂Â������ڕW���������Ă��炢�܂��B
�@�����ɁA�r���ʼn���������������āA���~���܂��ƌ����o�����Ƃ�x�炷�ׂɂ��A�����Ɍf�ڂ��A�I�I�J�~�ꂪ���\�����ڕW��Y��Ȃ��ׂɊŎ��̖ڂ����点�Ă������������ׂł��B
�@�܂��Ȃ��āA���̈ꕶ���������Ă��炤�C�����ɂ����Ă����������A�F�l�w����ɂ���Ɗ��ӂ�\���グ�܂��B
�@�u�l�̘b����l�ԂɂȂ�v�ł��B
�@�������g�̂��Ƃ�U��Ԃ�܂��ƁA��ԂŁA�����S�����A�����b����D���ŁA�l�l��蔼�������C�Â��Ď���b�������鐫�i�̎�����ł��B
�@�P�W�O�x�܂łƂ͍s���܂��A�u�l�̘b���A�o������Ȃ���̐l�ɐg�ɂȂ��āA������~�߁A�����ł���悤�ɂȂ�v�A�ƌ����A���ɂƂ��Ă͂��Ȃ荂���n�[�h���ł��B
�@�����O�A�m�l���炱��Șb���܂����B
�@�u���̒n��ł͌����҂̘V�l�ł������B�@�������A�W�Q�Łh���V�����ԕ��݂̕��ώ�����������A���̕ӂŎ��炷��h�Ƃ����āA���E���ꂽ�v�ƌ������Ƃł��B
�@���E�����O�̐��N�Ԃ́A����܂ł̕s�l�C�̕]���͑傫���ω�����Ă����ł��B
�@���̕����A����������Ƃ��낪����A�F�X�ƐS�|���A�w�͂��ꂽ���Ƃł��傤�B
�@�V�S�ŁA�ւ��Ȃ�̎��͂��̂悤�Șb���ƁA�h�Ō�̍Ō�܂ŁA���炸����@���A�������ɓ���h�ƍA�܂ŏo�|�����Ă���܂����A���������ނ��Ƃɂ��܂����B
�@�ȏ�A������̃R�����Ɍf�ڂ��܂������ƂɁA�������ܕԐM���[�������������w����ɉ��߂Č���\���グ�܂��B�@���肪�Ƃ��������܂����B
�@�`�����܂ŁA�����܂��āA�����璆����w�̒��u���Œʊw���ԂƂȂ�܂����` |
�@�b�n�k�t�l�t�@�P�|�c�@�m�n�V�P�W
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����19�N�X���Q�T���@�@�L
|
�@�@�����z�����A��甍�����Ɗ��������̌�̂���
�@�@�@�@�@�@
�`�c�������[�܂����X���u�S���w�Z�v�ŁE�E
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�X���Q�R�ƂQ�S���`
|
�@�C���h���s�ׂ̈ɂQ�����Ԃ�̕S���w�Z�ł����B�@�挎�A��������Ē����Ă����H��͏����ɐ������Ă��܂����B
�@�Ō�̎��n�ƂȂ�J�{�`���ƃi�X�A�s�[�}�����u��荞�݂𑁂����Ă�v�Ƒi���Ă���悤�B�@�J�{�`���A�^�}�l�M�A�l�M�����ĉԔ��̐Ւn�͉đ������ꌩ�悪���Ƀ{�E�{�E�ł��B
�@�܂��͏H��̑��ނ���Ɠy�A���̍�Ƃ��I���悤�Ƃ��Ă������ɁA�����Ȃ肾�����B�@�Ђƒi�����������������̂ŁA�J�r�������Ȃ�O�ɑ��߂Ɉ����グ�܂����B
�@����@���A���ւ��ďh�ɂ̑����J���ăr�[�����X���Ȃ���A�ڂ̑O�̐[��̎R���݂ɂڂ���Ɩڂ������Ă��܂����B
�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�]��ɉf�����Â��̂ŁA�ꏊ���ړ����ĉ_�Ԃ��璼�ڐ�����̗z�����������ŃV���b�^�[�������ƁA��ʂɂ͕��i�ǂ���̖��邳�̉f���ł��B��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@���̈ʒu�ɖ߂�A�Ăѐ[��W���߂Ă���܂�����A�������C���P���A�����ɂ����������̂��Ƃ��]�����삯�Ă䂫�܂����B
�@�D����A�������u��甍�����Ȃ��`�v�Ɗ����Ă��邱�ƁB
�@�Q�c�@�I���̌��ʂ�������āA�u������͉z�����ȁv�Ɗ��������ƁB
�@���������āu��x�͒ʂ�߂��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����v�Ƒ肵�A���Ă̊W�̕ω��̎��������A�l����͂��߁A���ȐӔC�Ŏ�̐��A���含�����߂��A���s���낪�n�܂�B
�@�C���^�[�l�b�g���n�߂�����A�����Ă��������������ސE���ꂽ���ƁB
�@�\���N���A��Ƃ��Ă��铡�����Ƃ���A�������コ��̍ŏ��̂��Ƃ�̃C���N�������n�߂��t�@�b�N�X�ʐM�̂��ƁB
�@���̒ʐM�����̐��������n�߂����ʁA�u���R�����w�Z�v�ɖ{��e�[�v�����Q�������ƁB
�@���̊w�Z���s��Ɠc�ɂ̐ړ_�ƂȂ芈�������n�܂�B�@�s��̐l�X�̎M�ƂȂ�A��҂̐�������Z�p�����Đ�����E�C���w�сE�������Ă䂭�B
�@�v�����܂܂ɍD������ɏ����A���ɂ��Ă��閈���ɑ��A�������蒲�q�ɏ�肷���Ă���̂ł͂Ȃ����ƁA�u������o�ł̍��N�̉^���v��ǂ��ƁB
�@�����ɁA�t�@�C�����O���Ă���Q�O���N�O�́u�R���s���[�^�[�ɂ��l�������^�����f�v��
�@��������o���ēǂݒ��������ƁB
�@�Ō�ɂ́u�e���̎��ɍۂ̂��Ƃ��L�^�Ɏc���v�A�����́u�I�����̉������ÂɊւ���ӎv�\�����v�ɉ��߂ď������A���̂ق��ɂ��u�⌾�v��u���V�̕����A���̌�̒m�l���ւ̎ӎ��Ƃ��當�v���̈ꎮ������������ƁA�C�����X�b�L�����A�������炩���C���N���ė����悤�ɂ������Ă������ƁB
�@�u�I�I�J�~��v���X�ɋC�y���Ɩ��ӔC�Ȕ������J��Ԃ��Ă���̂ł͂Ǝv�����A���܂�Ȃ������B
�@�Ǝv���Ă�����A�u�����ӐM�I�ł͂���܂��v�Ƃ̃��[���������ƁB
�@���������C�ɂȂ�u�ӐM�v�Ƃ�������u�L�����v�Œ��ׂĂ݂���A�u�킯���킩�炸�ɐM�����ނ��Ɓv�@�u�������E�E����v�@�u�E�E���ċ^��Ȃ��v�Ƃ���܂����B
�@
�@����Ȃ�ɁA�����A�l���A�����̈ӌ��E�ӎv�������Ă����ς�ł��������A�l�l�ɂ͂��̂悤�ɉf����̂��ƁA��O�ɓW�J����[��̎R���݂ɓo���čs�����_�߂Ă��܂����B
�@���Ԃ̌o�߂Ƌ��ɁA��������̏W���̕��i�ƂȂ�܂������A�[�Ŕ��艽���������E����S�Ă������A���̌�͐[���̑��������������Ă��܂����B
�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
�@���A�����A�����A��܂����X�N�i�J�{�`���A�i�X�A�s�[�}���A�H��i�_�C�R���̔����A�`���Q���T�C�A���̔����A�l�M���ł��B
�@�@�@�@�@ |
�@�b�n�k�t�l�t�@�P�|�c�@�m�n�V�P�V
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����19�N�X���Q�R���@�@�L
|
�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�T�M�����ނ�ŁE�E�E
|
�@����A�[���̎U���̎��ł��B�@�����̂悤�ɒz���r�̎��H�ɓ����O�ŁA�Ζʂ̃u�b�V���̂Ƃ���ŎU���A��̕��������|���Ă��܂����B
�@�C���|�[�����O���ĕ������𗧂Ă܂��ƁA��������������ƌ����Ă����܂��B
�@��ꔭ���҂̕��́A�U���ɘA��Ă��������A�}�əႦ�n�߂��̂ŋC�Â����Ə�������Ă��l�q�ł��B�@
�@�߂��̐A�����ł͏����������炵�Ă��܂��̂ŁA���Ƃ��Ȃ�Ȃ����Ɛu�˂�ƁA�u�쒹�̒��͈���Ȃ��B�@�����҂̑P�ӂ��A�b��̑P�ӂɗ��邵���Ȃ��v�ƌ����B
�@����������̉����Ǝv���A����܂ŎԂɏ悹�Ă����Ă��������A�_���{�[���ƕߊl�p�̃l�b�g��ςݍ���ōĂь���ցB
�@��قǂ܂ł͉H���o�^�o�^���Ă����̂ɁA�l�b�g���g��Ȃ��Ă��߂܂����_���{�[�����ցB�@
�@�߂��̏b��@�ɘA�ꍞ�ށB
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@���̏b�コ��A�쒹�̎�舵���̋��������Ă�����ƌ������ƂŁA�A�I�T�M�̕��̕ӂ�ɐG��Ă��܂������A�����������̂ł����ɂ����̂ł͂Ȃ����ƌ����Ă����܂����B
�@�����Ŋw���Ƃł����A�b��ł��쒹�̎�舵�����i�������Ă��Ȃ��ƁA�����邱�Ƃ͖{���o���Ȃ����ƂɂȂ��Ă���Ƌ�������B
�@��͉����ŕی삳�ꂽ����u�˂��A�쒹�͎s���S�̂̕�ƌ������ƂŁA����ȍ~�͎����Ή����܂��ƌ������Ƃň����グ�܂����B
�@�������A���̊ԂR�O�`�S�O���ł������A�A�I�T�M���h���h������Ă���悤�ł����B
�@�쒹�͐l�Ԃ��a��^���Ă����ɂ��Ȃ��A���̂܂ܖ����܂ŗl�q�����đΏ�����ƌ����Ă����܂����B�@
�@�����͖쌢�ɏP��ꂽ�̂��Ǝv���Ă��܂������A���������Ɖ������܂܂ł��̂ŁA�Ԃɂł��͂˂�ꂽ���Ǝv���܂������A�ǂ���Ⴄ�悤�ł����B
�@�쒹�̐����Ă䂭����������������w�т܂����B
�@������A�S���w�Z�ł��B�S���w�Z�̒r�ɂ��쒹�̃J�����Ԃł���Ă��܂��B
�@�������Ƃ͈قȂ�ڂŒ��߂Ă݂�ς�ł��B
|
�@�b�n�k�t�l�t�@�P�|�c�@�m�n�V�P�U
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����19�N�X���Q�Q���@�@�L
|
�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�P�N�O�̎ʐ^��������
|
�@�����O�A���̑|�������Ă���Ɩ{�̊Ԃ���Q���̎ʐ^�������܂����B
�@���ʂȎʐ^�ł��Ȃ��̂ŁA���̂܂܊��̏�ɓ����o���Ă����܂����B�@���A�����ɂȂ��ĉ�����Ɏd��������ł���A���o���̂��Ƃ��v���o���܂����B
�@�Q�O���ȏ゠��̂ł����A�������N�͎��o���Ă݂邱�Ƃ�����܂���B
�@�A���o���̔w�ɂȂɂ��L�^�����Ă�����̂�����܂����A�قƂ�ǂ͖���ł��B
�@�u�I����ÂɊւ���ӎv�ؖ����v�u�⌾���v�u���V�̓��e�E�菇�E���當�v�Ȃǂ��A�p�ӂ��I���܂����̂ŁA���̉�������ɂ��邩�Ǝv�������āA�{����������o���������邱�Ƃɂ��܂����B
�@�q���̍�����̃A���o�����܂߂�ƂR�ӏ��Ɏ��[���Ă���܂��B�@�傫���敪���Ă݂܂��ƁA
�@�`�j�a�������w�̑��Ƃ܂łł����A���̊Ԃ̋L�^�͏��w���܂ł̎ʐ^����ԑ����ł��B�@��O������̕��̖�������ł������A�ʐ^�����͌��\�c���Ă��܂��B
�@���w�`���Z�̍��͂��܂��܂ɂ�����x�A��w�Ƃ��Ȃ�Ƃ܂������ƌ����Ă����قǂ���܂���B�@�@�A�E�����̂Ƃ��̎ʐ^���炢�ł��B
�@�Љ�l�ɂȂ��Ă��L�^�ɗ��߂Ēu�����ƂȂǍl�������Ă��Ȃ��������A�܂��ʐ^���Ă��A���o���Ɏc���Ă����ƌ�����Ƃ��S�����Ă��Ȃ������̂ł��傤�B
�@���a�S�T�N�A���j�����܂ꂽ������́A�q���̋L�^�Ƃ��ẴA���o�����A���j�̂��܂߂P�O���ȏ�ɂȂ��Ă��܂��B
�@�a�j�Љ�l�ɂȂ��Ă�����Q���Ƃ��܂��ƁA��L�ɏ����܂����悤�ɑ����͂���܂��A����ł����a�S�V�i�P�X�V�Q�j�N����A�C�O���@�����N����A���̊Ԍn�̋L�^�����Ȃ�̗ʂƂȂ��Ă��܂����B�@����ȊO�͎v���o���Ă��L���ɂ͗]�肠��܂���B
�@�@�����āA���������A���a�U�P�i�P�X�W�U�j�N�̎ʐ^���o�Ă����̂ł��B
�@�@ �@�@ �@�@ �@ �@
�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�d����ŁA����Ă��܂��@�@�@�@�@�@�@�@�~�x��ł��i�E�ɂP�X�W�U�N�ƌ����܂��j
�@���̔N����A�}���ɃA���o���������Ă䂫�܂��B�����U�i�P�X�X�S�j�N�܂ł́A��Q�O���ɏڂ����N���ƁA�ʐ^���e�̋L�^��悤�ɕ\�����܂����B
�@�����������R�́A���̔N���獁�`�ɕ��C���܂����̂ŁA�N�ɂQ�`�ɂ���Ă���Ƒ����A�ߗ��Ɉē�����悤�ɂȂ�������ł��B�@�������ł͂Ȃ��A�����A���������ɍ����ʼnƑ����s�����Ă���܂����B
�@�@�����R�i�P�X�X�P�j�N�A���`����A���������܂ł̎��Ԃ����߂������ׂ��A���_�I�Ȕ�������������߂��A�C��̂悢�t�E�H�Ȃǂ͌��ɐ��x�̃h���C�u�Ȃǂ̋L�^���c���Ă��܂��B
�@���A����������U�i�P�X�X�S�j�N�܂łŁA����ȍ~�̋L�^�ʐ^�́A����܂ł̐����̈�ƌ����ʂɂȂ��Ă��܂��B
�@�b�j�ƌ������Ƃ́A�����U�N�ȍ~�͑�R���ƌ������ƂɂȂ�̂ł��傤���B
�@�������P�R�N���o�߂��Ă��܂����A���ɁA�����S�`�T�N�A�����p�\�R����������悤�ɂȂ��Ă���́A�B������B�邱�Ƃ̕��ɋ������ڂ��Ă���܂��āA���̃z�[���y�[�W�Ɍf�ڂ��邱�Ƃ��y���݂ƂȂ�܂����B
�@�u�сv�u���C�v�u�Q��v�̓��A���̂Ƃ���сE���C�͏�ɗp�ӂ���܂����A�Q�邱�Ƃ̕z�c�̏グ�����͎��O�ł������Ă���܂��B
�@�ܘ_�A����̎�z�Ƃ��̒�����ǂ�����̑I���������g�ł��B
�@�̎ʐ^��������A�܂��ЂƂ������i�݂܂����B |
�@�b�n�k�t�l�t�@�P�|�c�@�m�n�V�P�T
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����19�N�X���Q�P���@�@�L
|
�@�@�Ђ�����炭�@���炵�����ԁ@�h�i���o���M�Z���h
�@�`�������c���̔ފ݂̓���A�X�b�J�����ϊ����`�@�@
|
�@�v���Ԃ�ɏt����s�s�s�Ή��A�����ɓ��ꂵ�܂����B
�@�X�X�L�̍����Ɋ��Y���悤�Ɂh�i���o���M�Z���h�������F�̏����ȉԂ��Ђ�����ƍ炩���Ă��܂����B
�@�@ �@�@ �@�@
�@���̉Ԃ͗t���މ��L�Z�������������������\�͂��Ȃ����߂ɁA�X�X�L��T�g�E�L�r���Ĉ��N���B
�@���^�̉Ԃ��L�Z���Ɏ��Ă���Ƃ��납�疼�Â���ꂽ�B�@�I���C�O�T�Ƃ��āA���t�W�ɂ��o�ꂷ�邻���ł��B
�@�����ł̓X�X�L�̊Ԃɍ����P�O�Z���`�قǂɐ��������i���o���M�Z�����Q�����Ă��܂����B�@
�@�����ׂ𐂂ꂽ�����ȉԂ��c�����������A�H�̖K������o���Ă��܂����B
�@�����́u�O�����s�A�̊ٓ��v���`���Ă݂܂����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@ ���@�@�@ ���@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����̒ʂ�A�H�F���C�b�p�C�ł����B
�@�@���̌�������U�������A�����Ɏ�������A�d�����Ɏ�𐂂�Ă��܂����B
�@�@�@�@�@ |
�@�b�n�k�t�l�m�@�P�|�c�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����P�X�N�X���P�X���@�L
|
�@�@���m�点
�@�@�x���Ȃ�܂����B�@�����h���R���h�̂��ƈꕔ�f��
|
�@�@���Ñ����肪�Ƃ��������܂����B
�@�ꕔ�A�p�\�R��������ԈႦ�Ă���܂��āA�x���Ȃ�܂����B
�@�u�G�b�Z�C�@�����L�v�ɁA�X���P�V������P�W���̂��ƁA�ʐ^���ڂŌf�ڂ��܂����B
�@�����͉��R���ŏH�F�Ɍ����邩�Ɗ��҂��Ă���܂������A�����͂R�O�x�߂��C���ł����B�@�������A�������������݂܂��ƃX�[�Ɨ������Ȃ�A�S���A�������̖��Ƃň����߂����܂����B
|
�@�b�n�k�t�l�m�@�P�|�c�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����P�X�N�X���P�V���@�L
|
�@�@���m�点
�@�@
�@�@�@�@�@����1�T�ԁA���x�݂��Ă���܂�
|
�@�@�ǂ��ƌ������Ƃ��Ȃ��̂ł����A���̃R�������܂߂āA�S�Ă̍��ڂɊւ���5���ԉ����f�ڂ��Ă���܂���B
�@���߂āA���f�肷�邱�Ƃ��Ȃ��̂ł����A���܂ł�U��Ԃ�܂��ƁA�����f�ڂ����ł���5���ڂ��o�߂��邱�납��A�u���C���H�a�C�ł����Ă���̂��H�@�܂��܂��A���@���H�v�ȂǂƁA�F�l����̃��[�������Ƃ����������̂ŁA�{�����C�ɖ������߂����Ă��邱�Ƃ����`������ׂɓ��͂��܂����B
�@�܂��A�{�����u���R�����w�Z�v�ɎQ�����܂��̂ŁA��ԑ�����9��20���Ɍf�ڂƂȂ�܂��̂ŁA���f��ׂ̈Ɂu���m�点�v�Ƃ����Ă��������܂����B
�@�s��ƈقȂ�A��A���v�X�ƈɓߎR���̒J�Ԃ̉��R���͂��������H�F�����������Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���A��������o�����܂��B
|
�@�b�n�k�t�l�t�@�P�|�c�@�m�n�V�P�S
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����19�N�X���P�P���@�@�L
|
�@�@�@�@�c�����������A�H�̕�Q��ɂ䂭
�@�`�����̎o�ƁA����̂��ƋC���˂Ȃ����k���`�@�@
|
�@�ފ݂ɂ͏����������A�L���ɕ�Q��ɍs���B�i�X��10���j
�@���̂Ƃ���A�w�⌾���x����������A���̎v���o��A���ɍۂ́u���t�v�Ƃ��̏���������A�u�I����ÂɊւ���ӎv�\�����v�������A���̂ق��ɂ�2~3�ʂ����Ɋւ��邱�Ƃ����A�����ɂ��A�����Ƃ߂����Ƃ��A���߂ɐ�c�̕�Q��̂��U�������̂ł��낤���B
�@ �@�@�@ �@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�s�c�ё���n�͑�����1300�ƕ��̕�n�ł���A1��3�i���H���܂ށj�Ƃ��āA500�O��
�@�L���s���̓��Ɉʒu����u�ё���n�v�́A�����Ă͍��������ɖ��Ƃ͌�������ł������A�₵���ꏊ�ł������B�@���ꂪ���x�������̌㔼�i���a40�N�㔼���j���珙�X�ɁA�s�X�n����A�ё��̒n�ł��铌�̕�����A�L���̓�ɓ����鈭�������̕����Ɍ������ĐV���Z��������сA�Z������łȂ����X�W���ړ����A���͎s�X�n�͒��ԏ���܂܂Ȃ炸�ŁA�����̒n�ɂ�����悤�ɍx�O�����W���Ă������B�@
�@���̎��Ƃ������C���ł���A�g�c��̏鉺���i�D�ؒ������֒����A�����������������A�b�蒬����������A�Ȏڎ蒬���^���X�E������j�ł������̂ŁA����̐i�W�Ƌ��Ɏ��Ă������B�@���ł͒ʂ�̃A�`�R�`�����ԏ�ƂȂ�A���X�Ƃ��Ă͑̂��Ȃ��Ȃ��Ȃ���
�@���܂��Ă���B
�@ �@�@�@ �@�@�@
�@��n�̈�p�ɉ����Ƃ̕恁�u�y���̕�v������܂��B�@���A�͂ꂽ��A�E���ւ�����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�����ẮA�u�y���̕�v�ɕ���ŁA�ʂ̕悪���Ă�ꂽ���A����́u�y���v�݂̗̂\��
�@�@�@ �@�@ �@�@
�@�@�@�u�y���v�̃��S�i�H�j�����ۊ쥏��@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�y���v�̃}�[�N�A�O�ۂ͐�F�A���̓����͒n���������E�ΐF�A�����͑��z���Ԃŕ`����Ă����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@�ۊ삪�������������c��X�̕恄
�@���̉��c�͉����Ƃ��番�Ƃ����c�ɁA���̌�Ɠ������p�����̂��r�₦�āA�����Ɩ{�Ƃ������E�ۊ�̒��Z���瑊����v������Ĉ����p�������̂Ƃ̋L�^����܂��B
�@�N�X�A��ɍ��܂ꂽ�����������ʂ����Ȃ��Ă����B
�@���̌�A���������Ńs�A�m���t�����Ă���A�����̎o�Ƃ��ꂩ��̂��Ƃ�b���������B
�@����܂ŁA���̉������ɘV��̂��Ƃ�b�����邱�Ƃ��S�O������̂����������A����͉��̂��߂炢���A�C���˂��Ȃ��A�S�Ă̎����ɂ���5���Ԃɘj���Ęb���o�����B
�@���x�������Ă��邪�A���N�ɓ���A�����āu101���Ԃ̐��E����̑D���v���I�����ォ��A�������������悤�Ɋ����Ă��邪�A���̉�������ɂ���悤�Ɏv�����B
�@ |
�@�b�n�k�t�l�m�@�P�|�c�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����P�X�N�X���X���@�L
|
�@�@���m�点
�@1�������Ԃ�ɁA�u�s�|�X�{�[�g��D���̍u���f��
|
�@���e��
�@�@�u���E���a��f���v�h���{�����@�h�a���̔w�i�A�ȂǁE�E
�@�A�u���[���b�p�����@�`�M���V���������N�_�Ƃ��ā`�@�ł��B
�@�f�ڂ́@�@http://taiki.blog16.jp/
�@��ɂ���āA�ԈႢ���炯�̓��͕����A������3�����o�ߌ�ɏC���E�Z������̂ł�����A�L�����A���t���ǂ��납�A�u�S���L���ɂ���܂���v�Ƃ����ӏ��������ł��B
�@�������A�ו��͕ʂƂ��āA���ǂݒ����Ă��������N���Ă��܂��āA������x���������A�����ƒ��������C�����ɂȂ�܂��B |
�@�b�n�k�t�l�t�@�P�|�c�@�m�n�V�P�R
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����19�N�X���W���@�@�L
|
�@�@�@�@�Ė�̎c�[�����ƐV�����I��
�@�@�@�@�`����̖���2���Ԃ͂���̂��ȁH�`
|
�@����A�����������̃��[���̒��ɁA�_���S����T����A����̐K��@���āA�^�}�l�M�̐A���t�����������Ƃ����Ă��܂����B
�@�䂪�Ƃ̒�̋��ɂ���1�5�̔��́A���ɉĖ�̎��n�͂Ƃ��̐̂ɏI����Ă���̂ɁA���̏����ׂ̈Ɏ肪�������Ă��܂���ł������A��L�̋L�������č����グ�Ȃ���Ƃ����C�����ɂȂ�A�������ɌX�����U���̎��ԂɂȂ��Ĉ�C�Ɏ��|����܂����B
�@�匙���ȉ�̏P���ɑΏ�����ׂɁA���̍��ɉ��������_���܂����B
�@�@ �@�@ �@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@1���Ԕ���ɂ́A���H�̗��t�͔���������݁A��y�ΊD��͔���^�b�v���A���x�́u�^�q�{���̏o���炵�v�A����ɖ{�N�͋ߏ��̕����璸�������R�D���������݂܂����B
�@�o���オ�������͂����̒ʂ�ł��B�@
�@������ɁA�_�C�R���ƃT���G���h�E�̎�܂������܂��B
�@�����A9��8���̒��ł��B
�@����̉Ԃ͈�����������͂Ȃ��Ǝv���Ă��܂������A2���Ԃ͂���̂ł��傤���B
�@�ƌ����܂��̂́A����i9��7���j��118�̉Ԃ��炫�܂����B�@����Ȃɍ炢�Ă��܂��Ɩ{�����i9��8���j�̓[���ł͂Ȃ����ƐS�z���܂������A9��7���Ɠ��l�ȉԐ��ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�������A���Ԃ������́A�ǂ������Ă�100�ɂ͖����Ȃ�����ł��B
|
�@�b�n�k�t�l�t�@�P�|�c�@�m�n�V�P�Q
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����19�N�X���V���@�@�L
|
�@�@���炪���āi���H�j�A�ō��̉Ԑ������܂���
�@�@�@�@�`�䕗�X�����֓����������̒��Ɂ`�@�@
|
�@��ӁA�_�ސ쌧�̏��c���t�߂ɏ㗤�����䕗�X���́A�֓�����b�M�z�ɔ�Q��^���Ȃ��瓌�k���ʂɖk�i���̂悤�ł��B
�@����͑䕗�i�H����Ƃꂽ�䂪�Ƃ́A���炪���āi���H�j�ō��̉Ԑ������܂����B�@
�@�@���̐��P�P�W�ł��B
�@�@�@ �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ �@ �@
�@�@ �@�@�@ �@�@�@ �@�@�@ �@�@�@
�@���A����ȂɉԐ���t���Ă���܂������A�炢�Ă���̂͂������P���݂̂ł��B
�@�����͑䕗������̂�����Ă��Ĉ�C�ɍ炢���̂ł��傤���B
�@��������̉ԉ�͎c���Ă���̂ł��傤���B�@�S�z�ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̂悤�ɁA�P���ŗ��Ԃ��Ă��܂��܂�
�@���������A���Ăُ͈�ȓV��E�����̂��߂������̂ł��傤���A��̉ԁX�̍炫��Ɍ��C������܂���B
�@�Ƃ̑O�̊X�H���ɍ炫�n�߂��Ǝv���Ă����u�g���m�I�E�v�ł����A�S�ċ��݂Ő����Ă��܂����B�@�S�D�����ԃh���{�E�Ǝv���܂��B�@���̕��������O������ɐ�����Ԃ��Ȃ������̂ł��傤���B
�@�@�@ �@�@�@�@ �@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�䂪�Ƃ̒�ɍ炢���A�����Ȃ��u�g���m�I�E�v�ł��B
|
|
�@�b�n�k�t�l�t�@�P�|�c�@�m�n�V�P�P
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����19�N�X���U���@�@�L
|
�@�@�@�@�@�g���R�l�̒m�l���o���������B
�@�@�@�`���X��̐V�z�H������ł̏o��`
|
�@���̃R����NO�P�S�O�A�P�S�X�A�P�U�R�A�P�V�S�A�P�X�R�A�Q�O�Q�A�Q�Q�Q�B�����P�U�N�P�Q���R���iNO140)���畽���P�V�N�R���Q�O���iNO�Q�Q�Q�j�̍��v�V��ɘj���āA�����P�O�O���[�g���̏��ōH�����n�܂�����V�O���̐V�z�Z��݁E��P���̒��H����v�H�܂ł̗l�q���f�ڂ��܂����B
�@�����͂S�`�T�N�Ŋ����\��ł��Ɣ̔��ӔC�҂������Ă��܂������A���߂̍��͔���s�����F��������܂���ł������A���̌��C�Ɋ����̒��莆�������Ă䂫�܂����B
�@���ǁA���̌�H���͋x�ނ��ƂȂ��h���h���i�߂��A��N���ɂ͂Q�N�ԂőS�Ă������Ƃ������ɂȂ�܂����B
�@
�@�~�n�ʐϖ�U�O�A���z�ʐς���R�O�ؑO��ŁA���ς���S�O�O�O���~�Ƃ������z�ł����̂ŋ����܂����B�@��E�k�̕t���Y���Ă���p�͌������܂������A�w���҂͂قƂ�ǂR�O��̕��ŁA���܂��̏Z���n�̒���ʉ߂��܂����A�q�����قƂ�Ǘc�t�����w�O���珬�w����w�N�̎q����ł��B
�@�\���H������ŎߑO�A���m���̐E���Z��̐Ւn������o����܂����B
�@���̒n���̔����їD�ǂł������������z��Ђ����D�����A���N�̂U�����H���ɓ���܂����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@ �@�@�@ �@�@�@
�@�{���A�莆�𓊔�������ɍH������ɉ��A���x�݂ŐH�������Ă�����ɐ����|���܂����B�@
�@�O������̕��Ƃ������܂����̂ŁA�uWhere are you from?�v�Ɛ����|���A�����Ɂu�������痈���܂������H�v�Ɛu�˂�ƁA���ɗ����ȓ��{��Łu�g���R���璅�܂����v�Ƃ̕Ԏ��B
�@�u���N�ɂȂ�܂����H�v�@�u�P�X�X�P�N����ł�����P�U�N�v�@�u�o�u������ォ��ł��ˁv�u�n�C�A�ł����̍��͍����A���[�ƌi�C�͍D�������ł��v�Ƙb���e�݂܂����B
�@�ƌ����܂��̂��A���N�̓C���h�̂ق��ɁA�l�p�[�����g���R�ɍs�������Ǝv���āA���ɃC���^�[�l�b�g����F�����ăg���R�̎����t�@�C���͍���Ă��邩��ł��B
�@�Z��ŗ������A�Ƒ����ĂъĖ��É��̎�R�ɏZ��ł���B�@����̓g���R�ɂ���B�@���C�ɖʂ����t�@�^�b�T�iFatsa)�ł���B
�@���̌�A���h���ƁA�Z��Łu�C�i���H���X�v�Ƃ����Z���b�H���̉�Ђ��o�c���Ă���悤���B�i�������ł͂��낤���A�Z��A���̖��h�ł������j
�@ �@�@�@ �@�@�@
�@�������N�A������w�������w�̍u���Ń��X�����i�C�X�����j�̂��Ƃ͏����w�сA���Ƃ��Ă͍D��ۂ������Ă����̂ŁA���̂��Ƃ�b���ƃj�b�R�����A�X�ɉ�b�͎��X�Ɣ��W�����B
�@���̌��z�̘b������܂������A�ǂ��̉�Ђ̌����͍w���ł��邪�A�������̉�Ђ̂��͔̂����Ȃ�h������ƁA���̒m���Ă����Ђ̖��O���|���|���Əo�Ă���̂ŖʐH������B�@
�@���A���Ƃ������̂ł��邩��ԈႢ�Ȃ����낤�Ǝv�킸�ɂ͂����܂���ł����B
�@���x�e���I��肻���Ȃ̂ŁA��x����ɖ߂������A�J�������Ԃ�čĂєނ�̂Ƃ���ɗ��āA��L�̎ʐ^���B��܂����B
�@���ꂾ���ł͂Ȃ�ƂȂ�������Ȃ��āA�u��x�H���ł��ꏏ�ɂǂ��ł����v�Ƃ��U������ƁA�u�����ł���A��R�̎���̋߂��Ƀg���R����������܂�����v�ƕԎ�������A���h��n���ꂽ�B�@��������ɖ߂��āA�́E�̖̂��h�Ɍg�ѓd�b�̔ԍ������������ēn���܂����B
�@�Z���ԂɁA�����ɂ͏�������Ȃ��قǂ̉�b���܂��v���N�����܂��B
�@���ɃC�X�����̋����Ɋւ���ނ�̎~�ߕ��A�l�����B�@�܂��V���������킵�Ă��鎄�B�̓e���ƌ����Ă���s�ׂɊւ��鑨�����◝���̎d���B
�@
�@�X���j�h���V�[�A�h���������܂��u�˂Ă��܂���B�@�g���R�̐��Ɠ��i�ނ�͍����n�тƔނ�̎��Ƃ̂��鍕�C�̊C�ƕ\�����Ă����j�Ƃł͑傫�ȈႢ������ƌ����Ă��܂����B
�@����ނ�Ƃ�����A�b������ɂł��A�܂Ƃ߂ďЉ�邱�Ƃɂ��܂��傤�B
�@����܂������ł��ˁB�@�����ƌ����Ă��A���琺��������Ƃ����s�����N�����Ȃ���Ύn�܂�܂���B�@������ߎ����ɂ��Ă���u���s����̍s���̈�[�ł��傤���v
�@�ǂ̂悤�ȏo��ɐi�W���čs��������܂��A�܂��܂��y�������Ԃ����Ă����ł��B
�@ |
|
|
| �@�@�O�̃y�[�W�͂����炩��ǂ��� |
|
|


 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@
�@�@

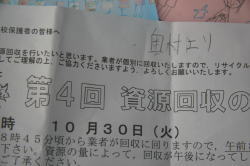
 �@
�@




 �@
�@


 �@�@
�@�@ �@
�@ �@�@
�@�@

 ���@�@�@
���@�@�@
 �@�@�@
�@�@�@

 �@�@�@
�@�@�@

 �@�@
�@�@

 �@�@
�@�@



 �@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@ �@
�@ �@�@�@
�@�@�@ �@�@�@
�@�@�@

 �@�@�@�@
�@�@�@�@