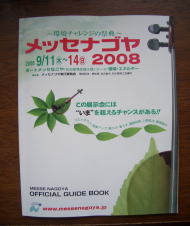COLUMN 1-D 860
平成20年9月24日 記
|
これからのリーダーに求められるもの・・
|
|
昨日(23日)紹介の曼珠沙華は午前9時半に撮影したものでした、昨日の夕方になれば花弁が開いているかと思って8時間後に行って見ましたが、ご覧のとおりです。↓

霞がかかっているのは逆光を避けた結果です。8時間では無理でした。

「サワギキョウ」です。 と言ってしまえばそれで終わりなのですが、法面の湿地帯に咲いています。 この周辺の自然保護をされている「弥勒山を守る会」の方々によって守られ今年は花を咲かせました。
この場所、春のころは法面から染み出したチョロチョロ水に産み付けられた蛙の卵があり、オタマジャクシまでには成長を見届けました。 その後は草の茂みに隠れていましたが鳩、カラス、スズメなどに食べられてしまったのではないでしょうか。
何とか生き残っていても今年の日照りでしたので、カエルに成長する前に干からびてしまったのではないでしょうか。 その跡に咲いたサワギキョウということで私には意味があるのです。

サワギキョウとは対照的な真っ赤なフヨウが夕日に向かって咲いていました。
ところで急に、「これからの組織のリーダー、特にトップリーダーに求められるものは何だろうか」 との問いが脳裏を走りました。
①兎に角、これからに時代は今までの延長線上には答えはありません。 教科書もなければ、教えてくれる人もありません。 そこで求められるものは「ヒラメキ」でしょうか。
そのヒラメキはどこからやってくるのでしょう、自省をこめて言うのですが”我欲が強く・損得で物事を判断するのはダメ”。 ”素直に世のため・人のため”を思って行動している方のところに天から降りてくるのでしょうか。
②とはいえ、これまでの体験、知識はゼロと言うことにはならないとも考えます。
専門分野も大切でしょうが、もっと求められるものは当分(10年ぐらい?)乱世の時代・戦時体制ですからその場、その時の瞬間での判断が求められます。
それには広範は知識、体験が瞬時に絡み合って答えが飛び出てくるDNAをもった方でしょうか。 一人では限界があります、知人・友人のネットワークを持ってあらゆる力を包含する能力を持った方でしょうか。
③流してよいもの、先送りしてよいものとダメな事柄を瞬時に処理する能力を持ち、気分転換が早く、ストレスを溜め込まない方でしょう。
と思いつくまま書いてみましたら、これまでの政治家と言われる方々は全部ご苦労様です。 政治は権力闘争というのですから、それを否定するような基準ですからいたし方ありません。 数回の選挙で淘汰されてゆくことになることでしょう。
『弥勒の世』のリーダーということになります。
この自問は継続です。
|
COLUMN 1-D 859
平成20年9月23日 記
|
この秋、3度目の曼珠沙華の登場です
|
|
昨日(22日)お墓参りを終えて帰宅した時にはまだ十分西の空に明かりが残っていたのに、築水池を廻り圃場整備された岩船神社の前の田圃のところに出ると太陽は沈んでおりました。

田圃の畦に一夜の内にスーと首を伸ばしたように曼珠沙華の影を見つけることができました。 数日前に草刈がされておりましたので、一緒に刈り取られたのではないかと心配していましたが、その時は地中で潜んでいたようです。
今朝、同じ場所に車で出かけてみました。
 
ご覧のようです。 一夜に内に茎の先端では蕾が膨らみだしておりました。 再び、今夕に通り過ぎればあの賑やかなボンボリのような花を咲かせていることでしょう。
こんな風に↓

今年の秋も曼珠沙華の球根を晒して食する心配はなさそうに稲がたわわです。
事故米(汚染米)だの、粉ミルクに毒物だのと安心できない報道が続きます。
自民党の総裁も麻生さんの茶番劇的な勝利で決まりました。 補正予算を通過させてからの衆議院解散でしょうか。 当面、目の前の対応も必要ですが、時代はそんなことや程度では済まされないところに間違いなく立たされています。
海の向こうのアメリカ大統領選挙も足元の金融不安から産業崩壊そして生活不安と息抜く暇なしの状況です。一休みして10、11月には更なる暴落となるのではないでしょうか。
スー伸び、パッと花咲かせ、そして明日には枯れ落ちる曼珠沙華の華やかさ。
その後には深緑の葉が根元を覆うように密生し、寒く・霜の時を潜って来年に備えます。
見た目の華やかさに目を奪われて、かの華を見ていると本当のところを知ることができないのではと感じています。
|
COLUMN 1-D 858
平成20年9月22日 記
|
我が家の庭の栗、一粒落下しました
|
|
一昨年思い切って太枝を切り詰めて、昨年は実り少なかった。 今年はその分をカバーしてあまるくらいのイガを付けています。
朝の壁当てキャッチボールの頭上から栗が一粒落下してきました。 半分虫に食われていましたが、今年の落下第一とすることにしました。

それを撮影しても絵になりませんでしたので、口が開けかけたイガを並べて見ました。
例年より遅れての落下かと思っていましたが、日記帳をくくるとほぼ例年通りです。
栗の木と藤棚の周りを赤トンボが乱舞を始めました。 雨上がりの空の様子が一気に変化してきたように感じます。
今日はこれから豊橋に墓参りです。
|
COLUMN 1-D 857
平成20年9月20日 記
|
「君は選挙と政治の野次馬か」
|
|
友人からのメール「君は選挙と政治の野次馬屋か」と頂いた。
このところこのコラムで花を紹介しても、鳥が映し出されても、野菜が登場しても最後は選挙・政治がらみの話になっているとのご指摘でした。
確かに読み直すまでもなくご指摘のとおりです。 仕舞い込んでいたわけではないですが、心の隅に溜まっていた、煮え切らないでいた不満心理が発酵し吹き出ているのかと自己認識しないわけではありません。
素直に今・この時代の流れを見ていれば、大きな転換期であると言わざるを得ません。
あらゆるところで、様々な形で転換期を示す相似形の現象が現れています。
それらのエネルギーが徐々に絡み合い、一体化して爆発するのではないでしょうか。
それは決して悲観することではなく、その先に新たな希望に満ちた世界の展開の前触れと思っています。
友人からのメールの中にもう一点の指摘がありました。 「政権交代を唱える意見は理解するが、その後に続く小沢政権には期待が持てるのか」との問いかけです。
正直言って長く続く政権とは思っていません。 その理由は①小沢さんが福田首相との間で大連立の話を進めたことです。 政権交代こそ彼の生命線でしたのに信用ゼロです。
②点目は国連の承認があればアフガンに自衛隊を送るという、確か今年7月の月刊誌「世界」への投稿記事です。 日本国憲法よりも国連決議が優先するなどという主体性・自主性のない姿勢は許されません。
別な観点から言えば「戦争反対、平和国家」の根本に反します。
③これは私の穿った考え方ですが、長年自民党のしかも中軸の権力者の立場にいました。 後ろめたい事柄をたくさん身につけているのではないかと推測できます。
それをアメリカの情報局あたりはガッチリと握っていると思います。
命かけて政治家小沢が、それらを振り払い・打ち捨てて新たな時代の日本の第一歩を踏み出す勇気があるかどうかです。
以上の3点から大きな期待は持てないという理由と同時に、その点を払拭したならば新生日本の出発の大功労者となり歴史に長く名お残す政治家となることでしょうが・・・。
そこまでは望まず、当面は政権交代の実を達成してほしいのです。
|
COLUMN 1-D 856
平成20年9月19日 記
|
中部大学 平成20年秋期(第14期)が開講しました
~ウロウロ・オロオロしていないか自問です~
|
|
2002年(平成14年)に開講された中部大学のオープン・カレッジは受講生が38人から始まったと聞いています。
私は2005年(平成17)の春期(第7期)からの聴講生で、今期を終了すると4年間ということになりますが、昨年の春期は船旅をしていましたので第7期目となります。
今期の受講生は263人とのこと、春期とほぼ同数であったと記憶します。

校内の「太陽の詩」の銅像が初めて目に入りました。
時折「受講の動機は何だったのですか」と尋ねられることがあります。 10年前、離職してから、これからの世界はそして日本はどのようになるのだろうかと考えていまた。
そんな時、”歴史に学んでみよう”と思い立ったのが動機です。 NHKの放送大学とあわせて中部大学の聴講生となりました。
放送大学のラジオやテレビからの一方通行の講義より教授の生の声が聞こえ、若い学生の意見も聞ける聴講生は大変刺激的でその後も続けているという状況です。

2008年秋期の開講式の様子
開講式のオープンセレモニーとして『組織人としての経験を理論に変換
~「組織の病気」への迫り方』と題して、同校の経営情報学部の教授の記念講演がありました。
経営学と経済学あるいは会計学との違いをお話いただきました。 プロ・ボクシングの実技経験をもたれている教授のスピード感溢れる60分でした。
私が現職にあったころ、失敗の連続の一端を理解・納得できました。
ところで、高い空の上から鳥瞰したマクロ経済、アメリカはそして連鎖しての世界の情勢は恐慌と言って良いのではないでしょうか。 少なくとも恐慌前夜です。
成金も貧乏人も同じようにウロウロ・オロオロしているように見えるのですが・・。
特に成金の狼狽のほうが大きいようです。 が、小さな利権にしがみ付き惰眠をむさぼっていた中産階級と思い違いしていた層もうろたえている姿を見ずにはいられません。
(この期に及んでも、そんなことはないと言っている方に驚きを通り越して、ヒョットしたら大人物かと見直してしまいます。 尻をまくったのでしょうか)
それにしてもリーマン・ブラザースの破綻の発表と同時に、私物をダンボール箱につめて大きなビルから去ってゆく後姿に唖然としました。金の切れ目が縁の切れ目とは良く言ったものだと思わざるを得ませんでした。
今、この状態はほとんどの方にとって逃げ場のない状況ではないのではないでしょうか。
大金持ちも、小金持ちも、スッカラピンもどこで死ぬかの場所を決めなくてはならないのではないかと感じているのですが・・・
どうせなくなる・失う(インフレで価値がなくなる)、あるいは騙され奪い取られるなら意思を持った判断と行動をしたいものだと思わざるを得ません。
こうなると友人・知人・親類縁者との関係が大切だと改めて思っています。
少なくとも世界の歴史を学ぼうとしてきた4年間、意思ある行為=修行をしたいとの思いです。
|
COLUMN 1-D 855
平成20年9月18日 記
|
白鷺にとっての安全距離は約15メートル
|
|
老舗証券会社・リーマン・ブラザースの破綻が報道されて、次は大手保険会社AIGの崩壊と思いきや、アメリカ金融当局は民間会社の救済に公的資金は使わないと言っていたのに、その翌日には日本円で9兆円の巨額融資を実施しました。
日本のバブル崩壊後の金融危機に対し、アメリカは公的資金の投入に馬鹿の・チョンダのと言い、潰すものは潰せばよいと脅迫・威圧をかけて奪うものは奪っていった彼ら。
今回の体たらくにどのような言い訳があるのだろうか。
一極支配をしていたアメリカの軍事と金融の崩壊は新たな時代の到来の何者でもない。
昨日の散歩の時、廻間町の田んぼで白鷺に出会った。
 
どこまで近づけるかカメラを構えてソロリソロリ。 その距離は15メートルまででした。

性能の鈍いカメラでしたので、ご覧のようにやっと飛び立った姿を隅でキャッチです。

再度、カメラを向けた時には、西の空に消えてゆきました。
私のこれまでのアメリカへとの距離はどれほどだったのでしょうか。
湾岸戦争が起こった時までは日米安保を疑うことなく、その存在に価値を感じていました。
9・11事件そしてアフガンへの軍参入以降疑いを持ち始め、イラクとの戦争に突入した時にはハッキリと反対の意思を口にするようになりました。
その後の対アメリカへの安全・安心・信頼の距離は離れるばかりです。
様々なジャーナリスト、識者、評論家といわれる方々がマスコミに登場してこられますが、親アメリカというのでしょう胎の底からアメリカの非を口にされる方はいません。
「アメリカの核の下で日本の安全が守れれているのだから当たり前だ」という前提です。 私にはどうしてもあまりにもアメリカ追随におもわれます。 言いなりです。
その傘が外れた時には思いがけない雨・風に煽られるかもしれませんが、自主性・主体性の欠如した考え方・姿勢ではこの大転換の時代を乗り切ることはできないと思うのです。
白鷺はシズシズと近づいたつもりの私に対して15メートルの距離で飛び立ちました。
こと、対アメリカのみならず、近隣の東アジア、そしてアジアの国々、ヨーロッパ、アフリカ、南アメリカとの関係をどのようにするのか、どの距離感覚で付き合いのかを自らの意思で決定しなければならない時にあると思います。
それにしては自民との総裁選を見ていると、そんな考え方はどこにも見当たりません。
といって、野党の筆頭民主党からも伝わってきません。
私たち国民に関心がないと見てのことでしょうか。 目先の御利益を求めていると誤りの見透かしをしているからなのでしょうか。
まずは政権交代、その後の情勢を判断して民意を明確に示すべきと思っています。
既得権益にしがみついている政治家と官僚の一掃、リストラしか施策のない大企業、それらの利権を擁護するのみのマスコミ・・・。
天は見ている、知っているとしか言いようのない、この憤りを創造的なエネルギーへ転化しなければと今日も反省の一日です。
|
COLUMN 1-D 854
平成20年9月17日 記
|
我が家の庭にも彼岸花が咲きました
廻間町(岩船神社)周辺の稲も大豊作です
|
|
新聞やテレビ・ラジオを視聴していると事故米だの、不良米だの、汚染米などと毎日口にするものの安全について不信と不安が増すばかりです。
中国では赤ちゃんの粉ミルクまでが汚染されているとの報道に唖然とします。
一方、アメリカ発でついにリーマンブラザースの破綻であり、続いて保険大手のAIGが次の疑念と報じられています。 10数年前の日本のバブル崩壊後のことと重ね合わせて見ますと、対応が早く、厳しいアメリカの金融界といえども道半ばということでしょう。
日本国民にお祭り騒ぎで目くらまし食らわし、総選挙を乗り切ろうとしていた自民公明与党の戦術は大破綻をきたすことでしょう。
 
我が家の庭に秋の花シオンが咲きました

少し遅れましたが、トマト、きゅうりの夏野菜のあとに大根の芽が元気に発芽しました。

大根と彼岸花の撮影は強い秋の蚊の襲撃に会い、ほうほうの体で逃げました。

1・5坪畑の隅では彼岸花が満開となりました。
昨日散歩しながら、<今度こそ日本国民はだまされないことだろう>と思ったりしましたが、この10数年の期待はずれの結果に気落ちしたこと思い出し今度も私の先走り、思い込みになるのだろうかと思い直したり、それが民意であり、国民の政治意識なのだと思ったりしました。
が、常にその民意を裏で、またその裏でリードするフィクサーの存在を感じない分けには行きません。 今度はその彼らもヨタヨタしている感じがします。
小さな年金という既得権益、健康保険という付回し、そして直ぐそこでご厄介になるだろう介護保険などを食い散らし、汚しまわってオサラバするには少しの後ろめたさを感じます。
政権交代をしても直ぐに問題解決などはしないが、少なくとも大きな既得権益にしがみ付く政官業の癒着構造を断ち切らねばならない。問題先送りし、司法を歪め・あるいはグルで機密・秘密の隠滅の企みを明らかにしなくてはならない。
民が汗し稼いぎ納税した富はいったい誰のためどこに消えていっているのだろうか。
それに比して、築水池に蓄えられた天の恵みの水は間違いなく潤いを与えている。

築水池の取水口、ここから廻間町に流れ下って行きます。

いつもの築水池ですが、最後の給水のために水位がさらに下がりました。

遠くから眺めればこのように素晴らしい収穫の時期間近を感じさせてくれます。

近くで眺めれば↑、↓と手入れの違いはありますが、天の恵みは同じ。

様々な意見も思いもありましょうが、思い、願い、行動してきた結果の秋が来ました。
|
COLUMN 1-D 853
平成20年9月15日 記
|
秋ナス、秋ササゲが豊作、直ぐ収穫せよ!
|
|
今朝、百姓学校の奥さんから電話が入りました。 「秋茄子、秋ササゲ」が鈴なりで、収穫しない遅れてしまうと電話が入りました。
明日のでも行こうと思っていましたが、本日の夕方から雨が降り出し、明日も雨模様とのこと。 午後から出かけることにしました。

ご覧のようにササゲ、牛蒡、にんじん、ナスが収穫できました。
特にナスとササゲは大収穫です。 帰ってきてから女房が近くの子供公園で夕方のおしゃべり会をしている、お子さんが小学校入学前の乳幼児の若い奥さんたちのところにお裾分けしました。
お裾分けといってもナスは7~8本、ササゲも小さな鍋ならあふれるくらいあります。
5軒分ですから結構な収穫量でした。
我が家の今夜のおかずは茄子尽くしとなることでしょう。 大好物ですのでかまいません。 子茄子も収穫してきましたから、明日の朝は一夜漬けの茄子が食べられます。
|
COLUMN 1-D 852
平成20年9月15日 記
|
~環境チャレンジの祭典~
メッセナゴヤ2008に行きました
|
|
今年で3回目となる「メッセナゴヤ」、テーマ・環境とエネルギーに行ってきました。
昨年も行きましたが内容がいっそう充実し、参加企業も変化しておりました。
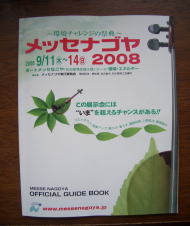
10年ほど前からタイトルは異なりますが、やはり環境問題、省エネルギーをテーマとした展示会が開催されていたと同行の方が言っておられました。
当初は開発した企業がその製品を売らんかなの展示会であったそうです。
今回も自社開発製品の販売ルート開発の姿は中心でしたが、企業イメージ向上を狙った出展企業のブーツや展示内容も目に付きました。
確か昨年参加したときにはほとんどが第二次産業のしかも開発型の企業ばかりが目に付きましたが、今回は大学、銀行・証券、卸・小売業、など第3次産業の企業も出展しておりました。
資源の有効活用、自然環境の保護と修復、環境浄化、環境との共生、環境への取り組みなどの分野別に展示されており、5時間ほどかけて見学やら出展企業の方のお話を伺って勉強しました。
この展示会に行けば、今どのようなことが注目され、どのような技術や研究が開発されているかなど目にし、手にとることもできました。
既に来年の出展者募集のパンフレットが出来上がっており、テーマは「安全、安心、信頼」とあります。
世の中の出来事を見ておりますと、”不安、不信、不満”が満ち溢れている中、テーマとしては実に的を得ております。
テ-マにふさわしい内容の「メッセナゴヤ2009」を期待します。
追記
その会場で衝動購買してしまいました。
疲れて一休み、ウトウトしておりました、綺麗なサウンド、臨場感ある映画音楽が聞こえてきました。 そのブーツの前はひっきりなしに人だかりです。
オーディオを「楽器」に変えた「匠の逸品」という看板の前で、しばし聞きほれました。
店頭販売はしていない、年に数回このような展示会で限定展示・販売しているのみとの説明を聞いている間にほしくなってしまった。
クラシックを嗜む、何々系の音楽が好きだといえるようなものは持ち合わせていません。
が、きっと良い音色に包まれれていれば、この変革期・転換期の時代をを心穏やかに過ごせるのではないかと期待したと後付の理由の衝動購買でした。
それはVICTOR・JVC WOOD CONE EXーB1です。
|
COLUMN 1-D 851
平成20年9月13日 記 |