
| このページ以前の コラムはこちら |
||||||||||||||||||
大学の講義も年内はほとんど今週で終わります。 受講している講義の中で、ある教授から年明け後・第1回目の講義の後で、「社会人聴講生の皆さんとの懇談会」を開催したいとの印刷物が配布されました。 現況の時代背景の中、ここ数年大学生の質は決して上昇しているとは言えず、学校経営者も教授も、関係者も苦労しておられるようです。 私の基本的な認識は、時代の乗り遅れている組織、集団の一つに大学をあげております。 今頃になって何をオロオロしているのかと言いたいです。 が、それでも真面目に「デモしか教授」から脱皮しようとされている教授の講義や姿勢には、声援を送りたいと思っています。 批判だけでは私も同じ穴の狢と考えて・・・ 教授から頂いた印刷文を読んで参加する予定でいます。 が、その場になると、一言どころか二言三言、しかも大きな声になる事は分かっていますので、以下のようなことを活字にしました。 当日は口を慎む予定ですが、どうなりますでしょうか。 08 秋期 世界史概論 懇親会に参加 平成20年12月17日 加藤 大喜 後、3回となりましたが、「世界史概論」の聴講ありがとうございました。 12月17日に“社会人聴講生との懇親会」のご案内を頂きました。 その直後に、思いつくままを書きましたものを提出させていただきます。 <講義について> 1、教科書がありますので、教科書から取り上げる章、節をあらかじめ15項目を設定する。 毎週、宿題として指定項目についての要約をしてくる。(まったくの抜書きでOK) (この方式は小島亮教授が一部の講義で行なっておられます。 私自身、読みきらなかった書を読み終えることと成りました。 しかも抜書き・要約をしますので、知らぬ間に記憶に残ります。 余談→其のことから、いまどきの若者の気質を知る場面に出くわしました。 仲間の一人が要約したものを、一部変更しコピーしたのでしょう。 其の日は指定項目(章・節)が飛ばされていましたので、当日の講義とは異なる要約の提出となりました。 しかも、講義後には其の日の講義の感想を書くことになっているのですが、講義中全て居眠りしていたのでしょう。 当日は講義をしていないのですが、「ポルポトのことが良くわかりました」とメモされていたということで、笑ってしまいました) 2、講義終了後に ①本日の歴史から学んだこと ②その事件、事柄の背景となったものは何か(先生のいう“つながり” ③その後の歴史に影響した事、その後の歴史の展開、あるいは予測できること ④当事国のみでなく他の国へ関係したこと。 そして⑤講義の感想、疑問点、質問事項など、上記の中から選択あるいは指定して宿題の裏に書く。 <要望したいこと> 1、複数論(意見)を紹介していただいた後、先生の自説を可能な範囲でお話いただく。 2、時代は正に転換期です。 しかも、先生の専門分野である現代アメリカは歴史の岐路に立っています。 今後を予測することは、容易にはかなわぬことでしょうが、過去の恐慌(チューリップ恐慌以来)の例を挙げて、あるいは対比して資本主義の本質、その限界、課題を解説していただけたらと希望します。 また、時代転換、新たな世界秩序の形成、覇権国の変化の過程には、そこにキーファクターがあったと思います。 そのキーファクターは何だったのでしょうか。そして新たな世界秩序の形成にどのように影響していったのでしょうか。 <その他> ・『国際関係学部の教員は、学生の面倒をしっかり見ること、覚えるよりも理解させる授業を行なうことを心がけております』と記されていました。 本日の講義ではありませんが、 資本主義―個人―自己責任―現実と社会主義―社会―健康保険制度―理想 とお話になられました。 個人的には年齢を重ね、今日の日本の社会情勢を見て、先輩としての反省を込めて築いてきた社会の制度・仕組み・構造に社会主義的な要素をと考えていますが、先回提出しました中に書きましたように 「ロハスで持続可能な低エネルギー社会」を見つめると異なる道の模索をあるのではと思っています。 そして、貧学生であった私は「気のない学生は眠らせておけ」と言う思いもあります。 以上です。 一般的には、社会人聴講生が参加することによって、学生が刺激されよい結果になっていると言われていますが、私には其の実感がありません。 時代は時間の経過とともに、言うならば昭和20年の終戦後の状態になろうとしています。 私の基本認識は全てが見境もなく破壊された愚かな戦争とは異なる。 次の方向性と目標を持って立ち上がれば、まったく問題ないという認識です。 その方向性と目標の共有化の前に、様々な立場から意見と希望が語られているのにいま少し時間を要するようです。 今しばらく続くのではないかと思っています。 直ぐに、分かったようなことを言いたい性分ですが、このところは自重です。 と既に先走り発言をしております。
 ↑なぜ「ボケ」と言うのだろうか。 寒空になってきた頃に、地面を這うような曲がりくねった枝振りに花を付けるからなのであろうか。 良く良く観察していると、何か語りかけてくるようで親しみがある。 それは、私はこの花の名前を知っているからではないように思えるのですが・・・・  ↑、このボケの花の蕾を見てください。 桃にも、梅にも、見えるではありませんか。 私が「ボケまじか」を意識して、この花に心を寄せ始めているのでしょうか。  ↑数十メートル先には、夕陽に照らされた南天の実が輝いていました。 正月飾りの南天のようでした。 本日は、朝と夕方で、気持ちと心根に少しばかりの違いを感じた一日でした。
昨日(12月14日)にNHK大河ドラマ「篤姫」が終了しました。 篤姫役「あおいさん」の演技力が良かったのか、それを取り巻く役柄・演技人がよかったのか、久しぶりに高い視聴率のようでした。 (脚本が素晴らしいと思った) 今から遡ること140年前、日本にとっては250年の眠りを覚まされる時代であった。 欧米にロシアも加わってアジアの、そして日本の植民地化の危機の時代で、力に任せた世界秩序へ組み込まれる危険の中にあった。 鎖国の中にあったとはいえ、中世の封建制度の中にあって、充分とはいえないまでも日本では資本の蓄積が出来ていた。 また、幕藩体制下の藩体制化ではあったが、海洋に包まれていたことにより国民国家とまではいかないが、南アジア、東南アジアそして中国の状況を知りうる立場にあり、先進的な情報を入手したリーダーの中には、国家への危機感を持っていた。 当時の状況を「篤姫」という一人の女性を中心として展開したことが、ヒットの背景にあったと思います。 振り返ってみますと、このドラマは140年前・1968年で終了していますが、その後の世界は「戦争の20世紀」と言われるように、世界中が戦いの中にありました。 その戦いの背景には様々な要因がありますが、1910年代の第1次世界大戦、 そして1940年代の第2次世界大戦の中間・1930年代には「世界恐慌」がありました。 今現在・その世界恐慌以来の”100年ぶりの恐慌・世界危機”と言われています。 「歴史は繰り返す」と言いますが、愚かな・進歩のない人間の営みなのでしょうか。 国・国民を上げての戦いは、それまでと異なり直接・間接に女性を戦力化しました。 その後、戦いが女性を強くしたのでしょうか。 それとも、女性の持つ忍耐強さや優しさや細やかさが求められたのでしょうか。 今の時代、来年の大河ドラマは男社会でしょうか、それを影で支える女性が主人公でしょうか。 両者のバランスなのでしょうか。  ↑活字とは何の関係もありません。14日のカメラには納まらなかった築水池のカモの波紋 以上のような硬いことを書こうとは思って入力を始めたのではありません。 今年は中日ドラゴンズが夏場不振で、早々と優勝戦線から脱落しましたので、「ドラマ・篤姫」を年間通して視聴する機会が多かったとただそれだけを書くつもりでした。 それに、昨夜70分の番組を見終わって、床に就く直前に頭をよぎったことをメモしていましたので、それを紹介するつもりだけだったのですが、長い長い前文が着いてしまいました。 どんなことが頭に中をよぎったのでしょうか。 『汝に与えん ”割れ鍋に綴じ蓋”、 汝よ学べ”艱難、汝を玉とする”』でした。 そして、今朝の礼拝時に「魂」を磨くための10か条がありました。 1、常に感謝と反省を忘れるな 2、自分にふりかかる一切のものは最善と思え 3、境遇に不足を言わず、今を足場として生きる と10か条の中の上記の項目が、特に心に残りました。
  ↑ 我が家の南西の角にある栗の木です。 敷地内には三分の一しか実が落ちないこと(路上に落下です)を前に書きましたが、今は枯葉です。 既に街路樹のナンキンハゼは全て落葉していますので、我が家から数軒離れた玄関先には、この栗の落葉しかありません。 朝晩、掃き掃除をしますが、そんなことでご迷惑を取り除くことは出来ません。 「夏は日陰を提供してくれるから・・、時には落ちた実を拝借しているから・・」と言ってくださる方もいますが、風が吹くたびに舞い落ちる落葉を恨めしく思っていることでしょう。 本日登場しましたのは、約50%の落葉で、青空が透けて見えるようになったからです。    ↑ 春日井植物園のグリンピアの飾りが変更になりました  ↑「少年自然の家」では、ツリーロック(正式な名前知らない)の講習会が開かれていました。 「冬空三題」と名づけましたが、植物園は暖房が効いています。 其の他も大変暖かな陽気の12月中旬です。 本日より、年賀状の宛名書きをはじめました。 息子がパソコンで出来るといいますが、今年も240枚自筆で頑張ろうとしています。
 築水池にカモが来ました。 築水池にカモが来ました。上記の枯葉と逆さ丘並みです→  残念ながら、カモの姿は映せななかった。 堤防のところはまた違った枯葉の図柄 ↓→   冬枯れと言いますが、気持ちが落ち着いている時は、何処かの何かに反応するものですね。 手にはラジオを持ったり、世界情勢勉強のためにウォークマンをぶら下げたりです。
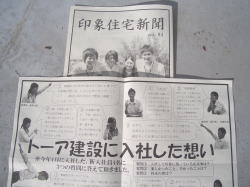 ↑A4紙に「印象住宅新聞」と印刷され、3枚組みの新聞(広告)がポストにありました。 何気なく開いてみますと、写真が多くしかも明るい感じの笑顔がイッパイの紙面でした。 コラム1−D NO886で紹介した鑑賞菊、これは斜め前のKさんからの頂き物でした。 そのKさんの続きも土地に息子さんが、ブランド?「印象住宅」を建設中です。   来年の2月末が引渡しと書かれていますので、今のところは内部のことは分かりません。 が、工事が始まる前のご挨拶、そして建築中に顔を出し大工さんに色々尋ねますと、心良く・丁寧に答えてくれました。 駄洒落でなく「印象がよかった」。 そして、今回の「印象住宅新聞」です。 きっとこの会社は明るく・風通しの良い社風の会社ではないかと想像しました。 どこの業界も厳しい状況ですが、住宅産業も同じことでしょう。 が、私がほんのチョット出合ったこの住宅の関係者からの印象は、今度、家を建てる事があったら、候補の一つに挙げることでしょう。 ところで、1年前までは考えられないような高給料を取り、自家飛行機で飛び回っていたアメリカのGM、クライスラー、フォードの自動車産業をはじめ、大手の保険会社が実質倒産の状況にあるようです。 アメリカに限らず、ヨーロッパも日本も、MORE&MOREが許された時代に、大量生産・大量消費を前提とした産業、業界、組織がノタウチはじめた様子です。 どうも大小ではなく、見えるお客様に、心こめた品を届ける商いの時代と言えそうです。 一丁上がりの離職高齢者ですが、反省をこめてお役に立てることがあるのでしょうか。 ”邪魔をしないでくれ”と言われないように、心しなければと思っています。
 ↑ 本日の収穫物、白菜、赤カブ、大根、ネギでした。 帰宅後直ぐに、ご近所にお裾分け。 女房の遊び相手になってくれている幼児の家。 ここ1年以内に新築住宅に入居してこられた近くの若いご家庭へ数軒に持参したようです。 若いご家庭にも決して負けない「フレッシュ野菜です」  ↑これは大根、白菜、赤アブの葉っぱです。 牛糞を製造していただいた牛君へのお返しです。 ところで、牛君はどれほどの量の牛糞を提供してくれているのでしょうか。 一日の排泄物は親牛1頭当たり6Kgです。6×3頭=18Kg 18×365日=6570Kgです。 私の通っている百姓学校では、これを全部捨てることなく活用しています。 上記の運搬機で1回当たり約40〜50Kg運ぶとしまして、年間150杯以上は運び出します。 ところで、牛君は1日当たりどれほどの飼料が必要でしょうか。1頭当たり30Kgです。 子牛の段階で競に出します、飛騨牛(?)の何等級になるまでに、どれほどの飼料の量が必要なのでしょうか。 そして、何キログラムの牛肉となるのでしょうか。 私は牛肉はそれほど摂取するほうではありません。 野菜たっぷりのほうです。 牛君には到底かないませんが、頂く牛肉となるための飼料の量よりは、間違いなく野菜の量が多きことは間違いありません。 これが健康の元です。 ところで、私の排泄物は如何ほどの量でしょうか。 何グラム・・・・ またまた、尾篭は計算になりそうなので、この辺で止めます。 数日前、何処かで子供の頃、肥溜めに落ちた話が持ち上がりました。 当時の体験が今日の私に活かされているのかな? 目の前に展開される100年ぶりの出来事にも、対処できる元なのでしょうか。
「恐慌の行く末を考える」 平成20年12月10日 初稿 〜これは「世界史概説」の第11回の復習の後に書き始めた。以下の視点を整理することによって自説が出るか? 1、世界情勢の分析→①アメリカの立場・希望 ②ロシアの立場・希望 ③EU=特に英・仏・独の立場と希望 ④中国の立場と希望 ⑤新興国=インド、ブラジルの立場と希望 ⑥資源国=インドネシア、オーストラリアの立場と希望 ⑦その他 ・上記複数の中で、キーマンとなるのは何処か?→① ② ③ ④そして⑤か。⑤は弱い。 →そのキーマンたちの過去の歴史・実績と現在の力、影響力から判断をする。 又、今回の大変革期においては、ハード・パワーのみでなく、ソフト・パワーも斟酌しなければならないだろう。 2、避けて通れない主要課題の一つは、今日まで進められてきた戦後の経済、金融の世界秩序=「ブレトン・ウッズ体制」、「IMF」[世界銀行」は今後も機能するのか。→どこをどのように変更すれば継続可能か、根本的な変更が必要か。 →①ドル体制の維持 ②新しい体制 ③ ①と②の中間か妥協 ・アメリカの弱り度合と妥協度合い。 内部が纏まるか。産業再生に力が注がれるか。 ・中国、ソ連の勢いの持続度、野心はどこに。 ・EUがアメリカ、及び中、ソの間でどのようなスタンスを取るか。仏・独は連携できるか。 ・日本を①②③④はどのように取り込んでゆくのか(日本はどのように取り込まれてゆくのか)日本の自主性? 3、2008年、12月10日の段階での状況 ・アメリカもEUも経済・金融恐慌がどこまで進展、変化して行くのか見当も付かない状況である。 兎に角、大きいもの(企業・金融機関等)に、国は潰せないとばかりに何でもありで資金の裏付けなしで大盤振る舞い。 ・アメリカの無謀な・馬鹿騒ぎの借金による需要が、世界の国々を満たしてきたが、それが崩壊した。→中国、インド、日本も、ブラジルも、資源国も、発展途上国も、全ての国が・・ ・金は間違いなくダブ付く、しかし実需要はない(特に米国の消費者には預貯金なし)のであるから企業の復活の見込みはなし。→金融機関も実体経済につられて資金繰りが出来なくなる。 ・正に、金融恐慌から産業恐慌へ、そして既に現われ始めた失業から来る生活恐慌へと進む。 ・この落ち着く先がどの辺りとなるかが見えない限り、答えは見つけ出せない。 ・この先、更なる混乱の中で、上記のキーマンたちの駆け引きが繰り返されることだろう。 ・“あるべき論”を提案しても、今のキーマンたちは聞き耳をまたない。 ・混乱し、疲弊し、疲れ果てた先に、天意が示されるのだろう。 ・天意を待つと言えば聞こえは良いが、思考を止め、主体性・自主性のない人頼りだけはしたくない。 思いを書き留めて、日々の反省と行為としてゆきたい。
  ↑ ① 1977年か? ↑ ② 1981年の記述あり  ↑ 全車揃って、一番奥のものが、最後に購入 全てアメリカに研修旅行に行ったとき買い求めてきた、子供達への土産品です。 ②に製品の裏には1981年(昭和56)9月12日とボールペンで記入してあります。 ①が一番最初に購入してきたものです。(多分1977年) 古くなって色変わりし茶色になったのではなく、多分艶出しのために私がミシン油を塗ったからでしょう。 アメリカ旅行で困ることは、適当なお土産品がないことです。 ブランド品がないわけではないですが、収入と見合いません。 この木製品についても確かな記憶はありませんが、一個5〜6ドル程だったと思います。 当時の換算レートはいくらだったのでしょうか。 200‾250円/1ドル? と言うことで、昨日、息子の勉強机を私の書斎への移動に関連したことでした。 COLUMN 1−D 911 平成20年12月9日 記 |
||||||||||||||||||
尾篭な話ですが・・・
|
||||||||||||||||||
| 海外旅行をして、少しぐらい食事内容が変化しても便秘などになることはありません。 もちろん、普段よりは常に少なめな食事量として、体調管理といつ・なんどき思いかけず美味しそうなものが出てきても対応できるようにしているためです。 このところは秋〜冬野菜の収穫で、ジャガイモ、サトイモ、大根、白菜、赤カブラ等を毎食いただいていますので、少し調子に乗りすぎではないかと自分に言い聞かせているほどの体調万全の毎日でした。 それ故に、本日の便秘には驚いてしまいましたと言うよりは、気持ちが悪くて朝から定例の流れで時間がまったく進みませんでした。 普段なら、4時半から6時の間に起床、ユッタリとトイレで新聞を読んで、その後血圧を測ります。 その後、40分のストレッチ、そして20〜30分の掃除。 次が冷水摩擦と進んで最後は15分間「神棚への礼拝」です。 お下がりのお神酒を頂いた後は、箱ワイン(ポリフェノールを頂くと言っています)を飲みながらの朝食です。 本日はこのパターンがまったく狂ってしまいました。 便意はもようすので、其のたびにトイレには行くのですが、ダメなのです。 食事後、これまた定例の「壁あてキャチボール」をしましたが、全然気乗りしません。 遂に、薬屋さんに走ることにしました。浣腸を購入してきました。 何年振りでしょう、記憶にありません。 気持ち良くというほどではありませんが、通便しパソコンの前です。 この間、なぜだろうの疑問の繰り返しです。 昨日の食事内容は・・・。 思い当たることがありません。 女房に尋ねましたが、普段どおりということです。 最後は、何時も「感謝と反省」と言っているが、口先ばかりとご神と意の現われ。 世の中、大変化する、予測のほかであるなどとこれまた口にしながら、私自身の「決心と覚悟」が出来ていないとの、ご警告を頂いたのだろうと思い至りました。 |
||||||||||||||||||
| 前のページはこちらからどうぞ |