
| このページ以前の コラムはこちら |
||||||||||||||||||
本日は春本番のような陽気です。 昼食を庭に出てとりました。 書斎の中でも(暖房は効かせていません)21度ありましたので、直射日光の下では、24~5度位にはなっていたことでしょう。 風も穏やかで、時折通り過ぎる風の流れも肌に心地よく感じられました。  ↑ 福寿草、今が満開でしょう。一斉にお日様に向かって花弁を一杯広げています。 「自分史」の整理のスピードが大分遅くなりました。 ついつい、それを書いた頃のことを思い出して、後先のことを読み比べるからです。 後先くらいなら良いのですが、当時の写真はないかとアルバムでも引っ張りだし始めると、その日はそれで終わりです。 本日は、一番新しい記録ノートを取り出しています。タイトルは 『豊かな老後を過ごす為に』 65歳~75歳は準備期間 その心構えと教え ・手帳に挟まれた手帳内ノートは平成17(2005)年9月30日に作成されました。 ・その表紙には、哲学とはフィロソフィーの目的「真善美」を探求することと書かれています。 そして、真とは、何が正しく、何が間違っているのか。 善とは、何をなすべきか問う。 美とは、何が美しいとされるかを問う。 とあります。 第1ペ-ジは下記のものです。 平成17(2005)年 9月29日 コラム 2-N NO147 より 「自立の“新老人”のために」 日野原 重明 「成功加齢」を重ね 「新老人」 75歳になったら老人と呼ぼう、「新老人」と呼ぶことにしました。 65歳から75歳までは人生の最終段階を迎えるための準備期間ととらえる事にしました。 「成功加齢」のために必要な事 ① より良い習慣を身につけること ②心と体の働きを出来るだけ良い状態に置く事 ③積極的に社会と関わる事。 ④希望と信念を持ち、不屈の精神と生きるたくましい行動力を身につけること ⑤常に愛する心と感謝の気持ちを持つ事 ⑥勇気を持って新しい行動を始める事 ⑦若い世代と蜜に交流する事 ⑧過去にこだわらないで、上を向いて歩こう。 次のページが下記のものです。 大変おこがましい言い方ですが、私が自分のことを「修行僧」と称していますが、その考え方と似通っていると思って、書き留めたことでしょう。 平成17(2005)年 12月 HADO 12月号より 比叡山 千日回峰 大阿闍梨 藤波 源信 ・ 修行とは自ら歩いてきた道ということ 私という人間を形成する為の千日回峰のカリキュラムがある。 自分に与えられた仕事によるカリキュラムで人間形成すればよい。 僧侶だけが修行し ているわけではない。 毎日生活していることが修行なのだ 子育てのお母さんも修行中、 残業をしているお父さんも修業中。 千日回峰された方と比較することは、恐れ多いことですが、日々これ「修行」と言うところの考え方は同じかなと思います。 今、「シュギョウ」と入力すべきところを「シュゴウ」と間違って入力し、変換しましたところ「酒豪」と表示されまして、「オ~、パソコンは分っているな}と感心してしまいました。
お手紙やメールをいただきありがとうございます。 私としては伊勢神宮を参拝出来たことによって一休みの気分です。 「その後の掲載が少ない、遅い、どうした」と、奨励とも冷やかしとも受け止めれるお便りです。 その間を縫って、約10年前の「創作フォーラム・演劇ワークショップ・春日井」の仲間から 電話をいただき、其の頃の資料などを探していたりして時間はどれ程あっても足りません。 と、弁解していても仕方ありませんので、書斎の本棚の奥から引っ張り出した、記録を掲載します。 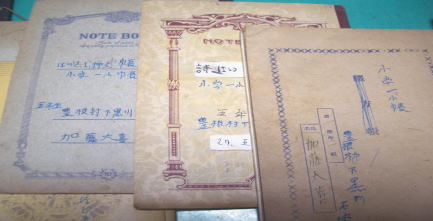 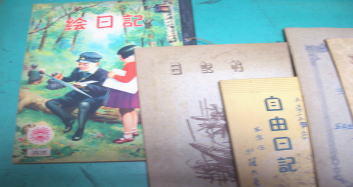 ↑ 以上2点は、小学校時代の「詩」「短歌」「俳句」、「自由日記」です。 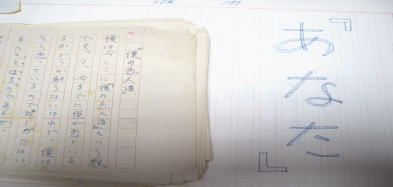 ↑中学時代のものはありません。 上記は夜間高校生時代に書いたものと思います。 「僕の恋人達」とか「あなた」などとタイトルが書かれています。 内容を読めばどの年代のものか分るのでしょうが、今は其の時間がありません。 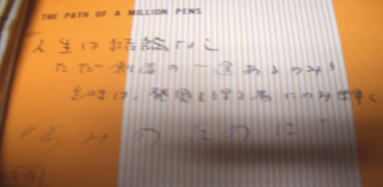 ↑「大学時代」です。 ”人生は結論なし ただ創造の一途あるのみ” 意味は発見し得る者のみに輝く と書かれています。(当時から汚い字です)  ↑「大学時代」 「幸せ 愛 なんだろう」、「望郷 放吟」と書かれています。 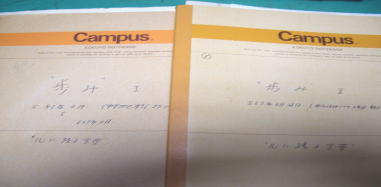 ↑「社会人時代、昭和51年と読めます」 と、こんなところです。 読み出せばきりがないことでしょう。 パラパラとめくるだけで、”よし! 今からだ!!”と感じています。 以上で、報告になったでしょうか。
昨日のコラムで”これからの「自分史」”の第3弾として「五十鈴川の川面を眺めながら」を掲載しました。 御質問、ご指摘は第3弾というのなら、第1弾と第2弾が掲載されていないのではないかとのことでございました。 結論から申し上げますと、既に掲載されています。 ただし「これからの「自分史」」としては、表題をつけていません。 私の目次としては、コラム 1-D NO935(1月8日)からコラム 1-D NO937(1月10日)の「腹下り(腸内一掃)」が第1弾であります。 第2弾に相当するものが、コラム 1-D NO952とNO953(1月28日と29日)「夢と勇気とサム・マネー」でした。 そして、第3弾に該当するものが今回の「五十鈴川の川面を眺めながら」という事と成ります。 2月1日、コラム 1-D NO961も「これからの「自分史」」と、考えましたが、書き留めた年月日が平成16年1月30日でしたので、見送りました。 以上のように報告し、お答えとさせていただきます。 今後も、「自分史」の整理が続き、時間・空間は幼児期のことになったり、働き盛りの家住期になったり、はたまた林住期になったりと、既に作成した大まかな目次をアチコチに飛びます。 其の中から選んで、このコラムに掲載しますので、今後も同様なことが発生しますのでよろしくお願いします。
2月 8日 松坂 2月8日は「波動の会」、と映画「ウォーター」とIHM江本勝氏の講演(映画解説) この映画はロシア発のドキュメンタリー・映画”水”で、ロシアでは大ヒットし、現在米国に上陸して注目されている。 その日本語版が出来上がり、現在全国を江本氏の解説付で巡業中。 近々、DVDで発売される。 人間にとってなくてはならない水について、科学者を初め、医師、農学者、宗教家など、21人が登場する。 凄い情報量です。 2月 9日 伊勢神宮から鳥羽へ   ↑ 現在20年ぶりの架け替え工事中の「内宮」の”宇治橋”  ↑五十鈴川お手洗い場から上流を眺める。 帰宅後、”これからの「自分史」”(過去のことではなくこれからのことを記録する)の第3弾として「五十鈴川の川面を眺めながら」と題してこんなことを書きました。 「これからの「自分史」 “伊勢神宮・五十鈴川の川面を眺めながら” 平成21年2月11日 記 ・ 少子高齢化社会の日本はこれまでに貯めた個人資産の1500兆円の運用の時代といわれる。 (ここでは企業の内部留保資金0000兆円については触れない。ただし、バブル崩壊後、新資本主義思想の下、人材派遣法は何度か改定され、其のつど企業に都合の良い人間を物として扱うがごときの首切り・リストラ自由の内容と変更された。 また、株主配当はこの間数倍と成り、役員報酬も大幅に引き上げられたが、10数年間に労働分配率は低下し、総人件費も数パーセントしか上昇していない。 国際競争に勝ち抜く為にと制定された法律と社会制度の実態は、人間を大切にすると評価された日本的経営の影さえも見られない。) ・果たして、個人資産は効果的に運用のされうるのだろうか。 100年に一度の出来事と表現されている今回の「金融恐慌」から「産業恐慌」へ、そして今や「消費恐慌」にまで至り、為政者や権力者は大衆のマインドを冷やし、不穏な動きを恐れて「大恐慌」という単語を使わずに来たが、もう「大恐慌」といわざるを得ない状況になったと考えます。 ・100年に一度の出来事ではなく、中世・封建社会が大航海時代、宗教革命を経て、やがて産業革命と続き近代と呼ばれる社会へ変革していった数百年の及ぶ潮流に匹敵するものと感じています。 ・いま少し我慢すれば、忍耐すれば元の流れが戻ってくるというような時代ではないと考えます。 ・何時か(当面3~5年、本格的には10年)この流れのトンネルは抜け出すのですが、トンネルを抜け出した後の景色は、これまで経験・体験していたような風景とは一変していると考えます。 ・私を「狼爺」と呼ぶ周りからは、馬鹿なことを口にするものではない、イイカゲンにしておけと忠告してくれる方もおられますが、トンネルの出口の先は全くこれまでの考え方、価値観、生き方では通用しないと考え言い続けています。 ・具体的に考えて見ました。 学者ではありませんから論理的なことは分りませんが、これまでの日本は様々な世界の政治・経済・社会環境に恵まれて、「金融立国」、「貿易・輸出立国」として、世界の歴史上見たこともない我が世の繁栄の中、金満生活を可能にしてきました。 が、30年にも及ぶアメリカの借金経済・生活が行き詰まりました。 日本同様にアメリカに輸出して急速な発展をしてきました中国もアジアも陰りが出ます。 ヨーロッパも同じことです。 資源国といわれるロシア、ブラジル、中近東、新興国といわれる国々も、アメリカの、そして世界の消費が落ち込むのですからこれまでのようには行きません。 それらの国々に輸出していた特に代表的な日本の自動車、家電製品は落ち込むのは目に見えています。 もう一度言います、我慢している、耐え忍んでいればまた何時かは元に戻るという状況ではないと考えます。 ・発想を変えなくてはいけないと考えます。 食糧自給率40%を切ったと騒いでいる私達の足元には、豊かな農地が捨てられたままになっています。 かってと比べれば、安価な農業機械も開発されています。また、農薬、化学肥料、添加物の少ない健康に良い農産物の生産技術が次々に研究・開発されています。 何よりも、其の地に立っているだけで大地からエネルギーが体内に吸収され、ストレスが解消されます。 其の上に、額に汗した農産物を手にした時、どこからか自信が湧き、勇気が生まれ、未来が見えるように感じます。 ・これからも人々の生活は続きます。 その人々が求めるものは何か、必要なものは何かと考えるところから、「新しい産業」が生み出されてゆくのではないでしょうか。 日本、日本人のこれまで培ってきた、歴史、伝統、文化、技能、技術を組み合わせれば、これまで以上に世界に貢献し、喜ばれるライフスタイルの提案、提供が可能と考えます。 人々はどんな暮らし向きを求めているのか、それを具体的にイメージするところから始まると考えます。 ・人頼りの心根や額に汗する精神や行動が失われると、自主性や主体性も失われウロウロ・オロオロの考え方や生き方になってしまいます。 少子高齢化社会は貯めた個人金融資産で安心と豊かな老後を過ごし、子孫にも幾ばくかを残すなどと考えていると、この時代のトンネルの出口で待ち構えているものは、曙ではなくて、閻魔様が待つ地獄となるのでは・・・。 ・「心配無用、そんな個人資産はないから」と噛み付いてこられた方が居られました。 こんな返事をしました。「それは、素晴らしい。安心で安全で元本が無くならず・減らさず、可能ならば増やす方法はないものかと気をもまないですむ」と・・・ 「金融資産で豊かな老後を」と様々な銀行・証券・保険会社等が勧誘に来ますが、どれもこれもこれまでの考え方、価値観の延長線上のものばかりのように見えます、思えます。 これまで苦労して今日を築かれたのですから、「安心で豊かな老後を過ごす」と互いに望まれることは理解しますが、同時に、運悪く、あるいは踏みはずして今も苦労されている方々も居られますし、毎日報道される社会情勢を見ていますと、決して安心し自慢できる社会を築いてきたと胸を張れない私達の過去でもあったと反省しなければ成りません。 これからの生活を「不労所得で暮らす」(個人資産の運用と年金)だけの発想では、どこかに寂しい気持ちが湧いてきます。 人様の迷惑にならず、どこまで、何が出来るのかが問題ですが、まずは「国民健康保険」を利用しないこと、あるいは減らすことが第一、そして何か一つでも人様のお役になることをしてみたいと伊勢神宮・五十鈴川の川面を眺めながら考えていました。  ↑外宮「豊受大神宮」がお祀りされています 2月 10日 伊勢~伊勢湾フリー~渥美半島へ 翌日は伊勢湾フェリーにて鳥羽港から渥美半島の伊良湖に渡りました。  ↑恋路が浜周辺は整備されて見違えるほど綺麗になっていましたが、 「恋路が浜」という名前と記憶からはもっと自然豊かであったのですが・・・ 気づかった自然石の防波散策路なのですが、何か記憶とは大違いで・・・ 同じ愛知県と言っても春日井市から伊良湖岬までは一番遠く、時間もかかります。 テレビ、新聞で何年も前から「伊良湖の”菜の花畑”」を視聴していたことでしょう。 10数年ぶりに、現地に立つことが出来ました。  昨年・2月は友人がいて、暖かな沖縄でした。 今年の2月にはニュージーランドを計画していましたが、取りやめました。 今回の計画コースが待っていた必然性だったのでしょう。
2月8日、午前1時半に目が覚めました。 床の中で「コールド・レーザー」をチャクラ等に照射させていましたが(この件は、「腰痛」に間違いなく効果を発揮しました。 あと少し実験したところで報告します)、脳裏に浮かんでくることを枕もとのメモ用紙に書き記していましたが、午前3時、遂に起きてしまいました。 ワイン(私には健康サプリメント・ポリフェノール)をグラスに注ぎ、書斎です。 子供の頃の「運動化」、「遠足」の前日から当日のようです。 そうです、本日は三重県・松坂市で「波動の会」主催(?)の講演会とドキュメンタリー映画"水”を鑑賞し、その後「波動の会」のメンバーと食事会となっています。 翌日は「伊勢神宮」に参拝の計画で、何か引き寄せられている感じを抱いておりますので、「何を感じるのか」、「何を思うのか」、「何が起こるのか・起こらないのか」ウキウキしています。 2月9日、松坂の次男の家に立ち寄り後、1月24日の中日新聞・夕刊に掲載されていた、「陶芸楽園”虹の泉”」を訪問。 其の後は、1月22日、中日新聞・夕刊で”ライトアップの菜の花祭り”と紹介され、それを切り抜いておきましたら、今度は中日新聞2月1日に全面広告で「爽快・伊勢湾クルーズで結ぶ渥美半島・伊勢時、1日大周遊の旅」が目に飛び込んできました。 松坂のことから始まり、次々と計画が進展しました。 伊勢神宮も10年以上、御無沙汰していますので、楽しみというよりは引き寄せられているようです。 ということで、本日から3日間、この「イイカゲン 修行僧日記」は休刊です。 例によって、キャンピングカーの旅ですので、シッカリとお酒は積み込みました。 厳に慎むべきは「飲酒運転」ですので、飲んだらその場でご休憩ということに相成り、その後何日の旅になるかは、不明です。 では、もう一眠りさせていただきます。
昨日に続いて「心に生きていゐ言」の綴りノートを読んでいます。 中学生の頃までは疎ましく感じていた父が、改めて身近に感じると同時に、あの戦争を境に価値観が180度回転し、2度目の妻を失い、その後3度目の結婚をした40代男の心境を思いやっています。 今この時代、私の身近にも小学生のお子さん(私が小学生だった昭和20年代前半))を持った40歳前後の知人達を知っていますが、 倒産、リストラに会い、更に病魔に侵されている方もいる。 昭和20年代前半とは異なり、今は食べるものはありますが(飢餓状況ではない)、人情の機微、助け合いの実体などはどのように対比したら良いものでしょうか。 その後、高度成長時代の「MORE&MORE」ともがき・駆け上がった日々のつけは、間違いなくやってきています。 が、私はこの状況を後ろ向きに捉えていません。 今を、「ゼロからのスタート」と捉えています。 社会制度や仕組みの欠陥のよって強制的に立場を失った方々の大変さを感じないわけではありません。 (状況は異なりますが、自分が離職したときの事と気持ちを思い出しています) 強制退去に追いやられた人々よりも、まだ何とかなると先行きの見込みのない状況にしがみ付いている心根や精神の方よりは、ここでスッパと切り替えるチャンスと捕らえ直しすならば、かえって早く気づかせてくれたと感謝して受け止めたらとも思わないわけでもありません。 話は飛びます。昨日春日井市総合体育館で開催の「第2回 かすがい 発見 ビジネスフォーラム」に行きました。 JR・中央線沿線の多治見・中津川からも含め124ブースの「知恵と技」が発信されていました。 「製造業」、「商業・サービス業」、「その他飲食ブロック」もありました。 看板だけ見ていては、何の業界・業種なのかも分らないものがありましたので、一つ一つ質問して回りました。 一様にと言って良い程に、業績の急速な悪化を口にされておられましたが、なかなかどうして強かな踏ん張りを感じさせてくれるブースも少なくありませんでした。 その中には既に芽が吹き出している方もあれば、今、吹き出さんとしている方もあると感じ嬉しくなりました。 話を戻します。 「心に生きている言」と、「春日井発見 ビジネス・フォーラム」がどのように私の中で結びついているのでしょうか。 「よし、今からスタートだ!!」という、気持ちになっていることです。 中部大学のオープン・カレッジでお話をさせていただくチャンスを頂きました。 そこから始まって、3年後に「自分史」を書き上げると決心しました。(何故、3年後かは、過去のことしか記録しない「自分史」にはしたくない。これから始まる3年間の自分も記録したいと考えました) 60年前、父が書き残してくれた「心に生きてる言葉」を読み返し、活字化し、一方、これから始まる「新たな世界・時代の展開」に私自身も加えさせていただき、新たな修行をさせて頂こうと思っているからです。
昨日パソコンを2台使いこなしているようなことを書きましたが、大間違い。 一部のことはできましたが、これまでのパソコンでやっていたことを実行しようと思うと、サッパリです。 本日も、改めてパソコン先生のところに行くなりました。 今のままでは「携帯用パソコン」で伊勢神宮参りはムリです。 ところで、話は変わりまして、「自分史」に戻ります。 ヒッパリ出したノートや書き物を手にしているうちに、以下の記録を活字化しましたので、掲載します。 父の教え?、母・末子の教え?、姉・かほるの教え?」と「心に生きていゐ言(ことば)」 ・私が誕生した昭和17年1月の時には、父は42歳、母・末子は33歳(当時としては遅い出産である)、姉・かほるは15歳である。 よって、誰によって教えられた「ことわざ」、「言葉」なのかは分らない。 ・「石に上にも三年」 どのようなスポーツでも、文化活動でも、要領が良くて・機転が効き、手先の器用な私は、ある一定のレベルの達するのは人様と比べて早かった。 が、それ以上にはならなかった。 体力がなかったことと、飽き性の性格がさせたことだろう。 ・そんな私の性格を見越して、「石の上にも三年」と言う、“ことわざ”を植えつけたことだろう。 飽き性のDNAは今も変わらないが、植えつけられた“ことわざ”によって、我慢する、続けると言う意識され・コントロールされた精神によって、幾つかの事柄が持続されている。 ①朝の拝礼 ②ストレッチ ③掃除 ④散歩 ⑤日記を書く ⑥毎朝のワイン(ポリフェノール)毎晩のアルコールです。 このところは、昨年末購入した「コールド・レーザー」の活用(この効能については、いつか紹介します。今のところ、腰痛に抜群の効果です) ・「成せば成る、成さねば成らぬ 何ごとも、成せぬは 人の成さぬなりけり」 父が私の6歳の暮(昭和23(1948)年・12月)に作成した「こころに生きてゐる言(ことば)」と題された綴りノートわざがあります。 其の中に、「成せば成る 成せねば・・・」の“ことわざ”が書かれているだろうと、探してみたがなかった。 が、私にとっては子供の頃何度も何度も聞かされたこと場であり、飽き性の私が投げ出しそうになると、必ず飛んできたことばであった。 今も、何かに取り組む時、挑戦する時に思い出す“ことわざ”です。 「心に生きていゐ言(ことば)」綴りノートから拾い出してみましよう。 ・「大地の恵」 大喜6歳の暮。この言葉が発せられて、この綴りノートが作成されることとなった。 ・「仁者無敵」 と「大地の恵」と並んで書かれてある。 昭和23年1月14日(大喜7歳誕生日に)『大地ふみ 大気をすいて はつらつと 七つになって 御芽出度ふ』と父読む。 ・昭和23年4月5日 大喜君 黒川小学校に入学の日なり 赤御飯をたきて祝ふ 『梅の咲く 川道そいて黒川の 学びやにゆく 今日こそよけれ』 ・昭和23年7月9日 『「みんな いいこ」 おはなを かざる みんな いいこ きれいな ことば みんな いいこ なかよし こよし みんな いいこ』 これは小学1年生・国語の教科書の最初に学ぶ、ひらがなであった。 この後も、「一茶」、「ドイツ語のことわざ」「一實」「「徳」「芋」「帰る所」「生き返る」などと題された父の文字が続く。 大喜の記録ノートというよりは、父自身が子を思い、眺め、願っての記録といったノートとなっている。 昭和25年8月9日付けで、私の筆によってこのようなことが書かれている。 『人はおばけである。 ゆうれいである。 大喜は大地の恵がばけた。 しょくぶつをたべてばけた。 くうきや水やお日さまがばけた。 私は目にみえない「ゆう」からうまれてきた。 わたしには からだではない 心の「れい」がある。 それだから わたくしは「ゆうれい」である。』 と書かれていました。 どうやら、私は9歳の時に「幽霊」であると認識した。 30数年前「修行僧」などと称し始めたが、其の前は「幽霊」であるようだ。 ↑「心に生きてゐ言」綴りの表紙 ↑ 大喜が発した言葉「大地の恵」が一行目に ↑ 「わたしは おばけ」を書いた時の記録 残念ながら、只今ウエブデザイナーがトラブル中。写真は本日・夕刻より掲載します。
新しいパソコンが到着した。 これまで使っているパソコンにトラブルが起こった分けではないが、時折操作間違いでストップしてしまう。 「何処かで物忘れをする」、「それが、思い出せない、出てこない」、「落し物をした」となると見つけるまで、あるいは遺失物の届けをし、ハッキリするまで気が落ち着かない。 カード紛失ならカードの無効届けを済まし、次のカードが届くまではイライラする。 という性格ですから、パソコンにトラブルが置きますと「直ぐにパソコン先生のところに持参して回復してもらっています」。 この性格対応ための予備パソコンです。 もう一つの理由は旅に持参するにはこれまでのパソコンは重過ぎる。 これまでが3Kg,、新パソコンは1・5Kgです。 軽くて・機能アップ・スピードアップは性格上は合格だったのですが、動かすまでの初期セットアップができない為、宝の持ち腐れ。 昨日、先生のところを訪問し、初期操作を済ましたので、本日は朝から2台のパソコンが動いています。 今も、一台で「インターネット・ラジオ」を聞きながら、このコラムを書いています。 机の周りは、ラジオ・コンパクトコンポーネントの配線、携帯電話の線、印刷用の配線、デジタルカメラ配線と、2台のパソコンとCCTV・ケーブルを接続する配線と何がどこに繋がっているのか分らないような状況です。  ↑ 我が家の松の下、「龍のひげ」の間から芽を出した「フキ」   2月4日午前9時の福寿草 其の1時間後 今年の年明け後から、これからの時代はどのようにななるのかに関心をもち 、①「1930年代の恐慌に関すること」、 ②「新たな世界と日本の課題」、 ③「新しい思想・理念・秩序」、 ④「新たな米国・オバマの発言と評論」などの新しいフォルダを作成して、資料を貼り付けたり、自分の意見を書き込んでいた。 その後、「昭和40年代・前半はどんな時代だったのだろうか」にも関心が重なった。 と言うのは、多分この時代の頃の生活レベルを想定すれば、「ロハス=LOHAS=健康で持続可能な社会=『少』エネルギー社会」の一つのモデルが画けるのではないかと考えたからです。 其の作業をしている時、中部大学のオープン・カレッジ開校式で聴講生の加藤さんが話をしてくれないかと打診があり、お引き受けしたところから「自分史」へと発展しました。 連日、寝床の枕元に置いたメモ用紙に書きとめたたことを、パソコンに入力してきました。 父が用意した幼児の頃の綴りノートから始まり、小学校の作文と俳句、短歌のノート、中学は飛んで、夜間高校生時代の書き物、そして大学時代から社会人になってからのノートも出てきたことは既に紹介しました。 本日は少々飽きてきたと言うか、疲れてきたのか、それらの資料を読む気になっていません。 2月8日からの松坂、翌日は伊勢神宮訪問頃で、一息つくだろうと予測していたようになりそうです。 久しぶりの車旅ですので、更に翌日はフェリーで伊良湖岬に渡り、10数年前から新聞に掲載されると一度出おかけ手みたいと希望していた『菜の花畑』に行く計画です。
書斎の戸棚の奥の奥に手を伸ばして引っ張り出しました。 子供の頃の記録(小学校入学前)「心に生きている言」と題が墨で書かれた父・丸喜が作成した幼児期の綴りノートから始まり、小学校時の俳句・短歌集~中学は何もなくて~ 高校生から大学時代の”幸せってなんだろう Ⅰ” 、”幸せ 愛 なんだろう”、”心の記 録”、”望郷 放吟”などとタイトルが書かれた大学ノート4冊と、
大学で勉強をした記憶はないが、それでも大学のレポーティング・ノートが8冊。 そして社会人になっての”複の中の個として(原則をしって曲線とせよ!!”
COLUMN 1-D 961 平成20年2月1日 記 |
||||||||||||||||||
「住む世界が違うから」と言った日に
|
||||||||||||||||||
| 平成5(1993)年から「十年日記」を愛用しています。 一日4行程度ですので、簡単な其の日の行動をメモし、纏まったことを書くときは、日記帳の後半に用意された「補足欄」に書きます、がここ数年は「補足欄」はほとんど利用していません。 「十年日記」ですので、毎年同じ日付になると、前年や其の前の年のことなどに目を通すことになります。 今回は平成16(2004)年1月30日に書かれた「補足欄」をめくることとなりました。 そのタイトルが「住む世界が違うから」でした。 なるほど、5年前のこの時期にこのような会話があったのかと改めて認識すると同時に、人間60年も生きてくると、それぞれに個性がハッキリしてきるのだなとも確認しました。 プライベートなことですので、ここに掲載などするのは止めようと考えたのですが、今年の1月の初めに書きました「腹下り(腸内一掃)」に読者の反応がありました。 人は「他人様の不幸や夫婦の痴話ケンカ」には反応したり、面白がるのだなと改めて確認し、自分も同じと思い直しました。 そこで、もう時効になっている、5年前の”住む世界が違うから”の日記を掲載します。 お読みいただき感想など送信いただければ、当方も改めて楽しめるのですが・・・ 「住む世界が違うから」 平成16(2004)年1月30日の日記から ・今、PM11時30分。この時間に起きていることは年に数回あるかなしです。 が、床入りして「住む世界が違うから」と言う言葉が脳裏を離れない、明日なんと記録しておこうかと考えているうちに、日記帳を2階の書斎に取りに行き、再びフトンの中です。 彼女の「住む世界が違うから」と何気なく発せられた時の状況から記録しておこう。 “牛乃宮・ウイークリー”より「牛乃宮プライベート・クラブ」の入会FAXが送られてきた。 それを丈博(長男)に送付した。 其の前に、二階の書斎で1月29・30日の修行僧日記を入力していた(PM10時近かった) 南遊の会(注・ベトナムでの植樹の会、女房は2006年から2008年まで参加している。多分2009年も、2004年までは私が行っていた)の今年のツアーと牛乃宮の夏合宿のことをカレンダーで日程を見ながら、一言・二言交わした後に彼女から「住む世界が違うから」との言葉が発せられた。 この言葉を聞いたとき、私は驚きもショックもなかった。 逆にかえって「やはり彼女もそのように思っていたのか」と心やすまった。 このことの前に、(本日、午後の3時から3時半頃に、姪のY子にメールを送った <注・Y子の夫はガンの治療をしていた>)。 本日のメールの前、1月27日に、私がガン手術入院のときのことを書いた。 「流動食」の時、見舞いに来た女房がパンと菓子を買ってきて、私の前でパクパクと食べたことを・・・ 女房は気を許し、安心していたからとった行動とも思うものの、やはり私は「帰ってくれ」と言ったと書いた。 別にそのときのことが、大きな基点とも思っていないが、このように記憶しているところをみると、やはり大きなエポックだったのかもしれない。 結婚して35年、時間の経過と共に、互いにチグハグになっていることがハッキリしてきているあらわれであろう。 私も彼女の機嫌をとろうという気持ちや、私の生き方、やり方を変更する気持ちはない。 彼女も私に遠慮していることもない。 でも、どうして同じ屋根の下にいるのだろうか。経済的理由だけなのだろうか? 既に、1年以上和室と居間で扉一枚区切られた別居生活である。 食事と洗濯はやってくれるが、掃除は私がやっている。 家計は年金が振り込まれる通帳とカードは彼女が持ち、文句なし。 私は別な通帳より小遣いを出し入れしている。 今年の4月には残高が各種税金の支払いには不足する状況になる、そのときの彼女の態度を見てみたい。(今までは事前に入金) 話戻って、特にこの5年間(1998年4月以降~)共に過ごす時間はあっても、徐々に共有する価値が離れていったと思える。 車旅にしても、散歩にしても・・・・。 近頃はテレビ映画の好みにおいて大いに差がある。彼女は推理小説をほとんど毎日読んでいるし、私はパソコンとテレビ映画である。(ケーブルテレビの契約で、いつでも何かある) 人間は一人で生まれて、一人で死んでゆく。 ここから更に体力が弱まり、互いに助け合うなりしなければならない時が来るのであろうが、いまのところの感触では、3~4年は更に溝が深まるのであろう。 体力が弱まるか、精神力の弱まりとなって、打算的な援助を求めることになるのだろうか? それとも、更に溝は深まって、そんな援助や介護は求めないと言う態度になってゆくのだろうか? 大変興味があるところである。 今、話すべきことの全てを書きつくせないが、今この時でないと記録しておけないことを書き記した。 柱時計が12時を打った。 「 住む世界が違う」 ①朝の礼拝 ②整理整頓、清掃 ③金銭感覚(経済観念) ④持続力(維持力) ⑤勉強、努力~現実と未来 ⑥イイ加減と貞節 |
||||||||||||||||||
| 前のページはこちらからどうぞ |
