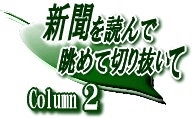 |
|
||
| NO.80 平成16年9月24日 |
||||
【プロ野球スト中止 ファンの声経営側動かす
|
||||
|
|
||||
|
|
| NO.79 平成16年9月23日 |
【プロ野球 スト回避へ前進 「来季パ6、歓迎」
|
|
政府官房長官・小泉首相までがこの問題に発言をするような国民的な関心事となったプロ野球の改革・再編問題はどうやら先が見えてきたようだ。 |
| NO.78 平成16年9月18日 |
【プロ野球 スト突入 交渉が決裂。史上初
|
|
|
| NO.77 平成16年9月7日 |
【今年の稲作は豊作と言われていますが・・・
|
百姓学校の稲も穂を出し順調に成長しています。 今年のお米は豊作といわれていましたが、私がお世話になっている秋田県大潟村のあきたこまち生産者協会より、8月20日に秋田沖を通過した台風15号により甚大な被害が出たとの報告がありました。 昨年は冷害で東北3県、特に太平洋側が減収でした。 自然の脅威の前に今年も思わぬことがおこりました。 大潟村はご存知のように琵琶湖に次ぐ日本で二番目に大きな八郎潟を干拓して出来た、周囲54キロの堤防に囲まれ、南北25キロ、東西14キロの広さです。 これは東京の山手線の内側の2倍の面積を持つもので、今年で立村40周年、一世の入植者は30数年間様々な困難を乗り越えて今日に至っております。 食料不足の当時、日本のモデル農業を目指して期待された村でした。 しかし、営農開始と同時に減反政策が始まり、その後も定まらない農政に振り回されて大変な苦労の連続であったと聞き及んでいます。 今回の被害は遅い稲の出穂期で、稲の穂が開花し、受粉する時期であり、風と雨、乾燥等の被害に最も弱い時期だったことも被害を大きくしたとあります。 男鹿半島の近くに大潟村はあり、355メートルの寒風山が大潟村の横にあります。 台風15号はこの寒風山にぶつかり、風が山の周りを巻くようにして、風の力が2倍~3倍になって、稲を直撃したようです。 私も冬、この寒風山に登ったときは風の強さと寒さによって数分しか立っている事ができなかった。 また、昨年は7月に訪れたましたが、今度は霧と風でこれまた早々と引き上げた事をおもいだします。 8月23日になり被害の状況がはっきりと現れて、収穫が皆無の方が20%、半分以下に方が30%、10アール当たり3俵位減収の方が30%、10アール当たり一俵減収の方が20%位と判明したといいます。 生産者協会員の方は大潟村の全域にまたがっており、被害の大きい方がいる反面、少ない方もあり、私たち消費者には心配なく届けることが可能であると紹介されていました。 |
| NO.76 平成16年8月31日 |
アテネ・オリンピック報道より
|
| ・ 男子レスリング55キロ級 銅メダル 田南部 力 「勝ったというより、終わったという気持ち。楽しんでやろうということを、テーマにしてきた。(日本の連続メダルという)伝統が守れてよかった。 ・ 男子レスリング60キロ級 銅メダル 井上 謙二 「攻めのレスリングがしたかった。最後の最後まで」 「守りに入ったら負けてしまう。絶対に攻めよう」 男子・富山監督「一番未知の選手。 その分、何かを引き起こしてほしかった。形にはまれば勝てるとはおもったが、正直言って、期待していなかった」 男子・和田コーチ「あいつ、本当に化けましたね」 ・ 男子ハンマー投げ 繰上げ「金」メダル 室伏 広治 「精一杯努力してきた。このような結果を残す事ができ、本当に嬉しく思います」 「本当は直接、表彰台で受け取りたかった」 「メダルの色は色々あるが、大事なのは努力」 (ドーピング違反に関して)「悔しいというか寂しい」 ・ 男子マラソン 5位入賞 油谷 繁 「五輪の方が価値あるかもしれないけど、また5位だから」(2001,03世界選手権も5位)「メダルがほしかった」 ・ 男子マラソン 6位入賞 諏訪 利成 「まだまだ強くなれる。次に期待してください」 「スタートからこんなレースは初めて、給水のたびに離された」「これほどとは思わなかった」 ・ 閉会式より 「五輪て・・・すごかった」 「北京まで頑張ります」レスリング女子48キロ級 銀メダリスト この言葉に至る過程に、バレーの竹下佳江選手(26)がかけた言葉、「女はね、30歳から味が出るのよ」があった。 竹下は一度負けてコートを離れた経験を持っていた。 女子レスリング 金メダリスト 吉田沙保里「最後まで暴れまくり。終わったって感じでスッキリした。 4年後も金メダルを取って、こうやって騒ぎたい」 陸上1万メートルの弘山晴美(35) 「五輪は最後になると思う。自分がここまで頑張ってきたことが刺激になって、長く競技を続ける女性選手が増えてほしい」とほほ笑んだ。 ~何度、報道記録からの「勝者・敗者の一言」の掲載をやめようかと思ったか知れない。 その度に勝者・敗者の一言が胸に突き刺さって最後まで続きました。 たったこれだけのこと(現地ではきっと記者が苦労し、走り回って取材した一言)ですが、それでも新聞を最低3回はひっくり返して読む事になり、普通なら読み飛ばす、あるいは気にもしなかった一言をキャッチできたのではないかと今は思います。 競技が終わった瞬間、あるいは一夜明けてのインタビュー・発言、中には日本の関係者の一言も加えてみました。 私にとっても暑い(熱い)17日間でした。 途中でも書きましたが、なぜ予想もしなかったメダルの数になったのでしょうか? "よかった、よかった"で済まさずに、この背景には大きな宝物が潜んでいると感じてなりません。 だって、「人間の力・技・精神」が新たな世界を生み出して行く基です。 それを引き出す創造してゆく社会、リーダーこそ今求められているのですから・・・ |
| NO.75 平成16年8月30日 |
アテネ・オリンピック報道より
|
| ・ 女子ホッケー 8位 「常連チームは五輪に調子を合わせてくる。集中力が本当に凄かった。 五輪で勝つことは本当に難しい」 副主将・FM岩尾 「あきらめずやれば、何でもできる事は残せた」最年長33歳、加藤 ・ レスリング・ゲレコローマン男子 60キロ級 5位 笹本睦 微妙な判定に抗議したが、認められず。 「やり切れないっす」 「5位には納得しない。ナザリャンに勝てばメダルに近づくと思いた」 日本レスリング協会、富山英明強化委員長 「ルール上、判定は覆らない。ただ、彼の名誉のために抗議文は出す。これは笹本の一生にかかわる問題だから」 ・ シンクロナイズドスイミング、チーム・テクニカルルーチン 銀メダル 井村ヘッドコーチ、(54歳・アテネを持って、日本代表コーチ勇退)前半を終えて 「あきれて笑ってしまった。」「ぜんぜん切れ味がなかった。もっといい演技ができるはず。」 「このままではアテネの五輪は終われないよ! 出来ないものをやれと言っているんじゃない。出来るものを全部出さなきゃあかん」 「練習で(完璧に)出来る確立が低すぎた」 後半を終えて 「人間、緊張しなければだめですよ。緊張せずに出やんといてほしいわ、こんな大会(五輪)。 緊張してもらわな。緊張はいいことです」 「一人ひとりの技に切れがないから、タイミングとか外れていなくても、勢いがない。 余韻をのこすとか、目に見えないものを人に見せ、感じさせるということはそういうことでしょ」 「力を出し切れば何位でもいい。この舞台で出さなければいつ出すのか。信じなさい。 今までの厳しい練習は、このときのためにやってきたんだから」 「開き直る事。捨て身になって、良いものをすべて出さなければ終われないとおもうときに何かがかわる。それには勇気がいる。 「技術点は選手の責任。芸術点は私の責任」 演技後の言葉 「よくやったね。精一杯やったね」 「ロシアが強かったということ。こちらも精一杯の力をだした。悔いはない」 「戦い終えて『汝(なんじ)の敵を愛せよ』の意味が又一段と良く分かった気がする」 シンクロ作曲の大沢 みずほ(今回の"サムライin アテネ"の外、10年目) 「きっと日本はパイオニアなんです。一歩前に出ているのに、今は気が付いてもらえない。後に評価される日が来るはず」 ・ 陸上男子110メートルハードル 金メダル 中国・劉 翔(21歳) 「アジア人がトラック種目で、黒人や欧米人に勝てないことはない証明ができた」 「一種の奇跡のようなものだ」 「これから練習を続けてゆく。4年後は競技者として一番いい年齢になる」 ・ 陸上女子 一万メートル 18位 弘山 晴美(35歳) 「三回目で一番冷静に走れた」 周回遅れも「満足でした」 「母は私を一番応援してくれる人。最後だからと思ったのでしょう」(初めて海を渡る) |
| NO.74 平成16年8月26日 |
アテネ・オリンピック報道より
|
| ・ バレーボール女子 5位 中国に 0対3で破れる 「これが世界のレベルの高さ」 「8年間は長すぎた。五輪を知っている選手がいなかった」(柳本監督) 高校3年から全日本入りしていた大山、アテネへの出発前に母校(高校)の監督から 「20歳そこそこのお前が全日本をしょって立つなんておこがましいことを考えるな。 次の五輪に生かすぐらいな気持ちで行ってきなさい」と言われていた。その大山は、 「自分にできる事は出し尽くした。この経験は財産になります」 ・ 陸上男子200メートル 一次予選敗退 20歳の新鋭高平 「のまれた。 ボクシングで意識がなくなったまま戦っているみたい」 ・ 男子板飛び込み 8位 寺内 健 「自分が、まだまだということを痛感させられました。まったく内容のない試合になってしまった」 「頭は真っ白。 一番やってはいけないことを一番大きな大会でやってしまった事に腹が立つ。 応援してくれた人に申し訳なく、やりきれない・・・ これでやめるつもりはない」 「度胸が足りない。 高い技術はあっても、出せなければ何にもならない」(馬渕ヘッドコーチ)精神面の弱さを指摘。 ・ なぜ敗れた長嶋ジャッパン 「得点できずに、あせりがチームの中にあったかな、と思う」(中畑コーチ) 「国際大会では長打で決する展開は少ない。つないで、野手の間を抜けて点を積み重ねないと」(長嶋監督) 「プレシャーの一言で片付けてはいけないけど、勝たなくてはならない野球の大変さが良く分かった」(中日・福留) 「1チームから2選手というのは、安易な選択だった。 五輪はアマのものにして、プロはワールドカップで世界一を争うと言う方法もある」(中畑ヘッドコーチ) ~適時打の欠乏は金メダルを義務付けられた戦いに選手が緊張した精神面に負うところが多い。日本のため、プロ野球のため、長嶋監督のため。と 対カナダ戦に大勝して銅メダルが決定。 長嶋監督「胸張って帰って」と談話発表 ・ シンクロナイズド・スイミング デュエット 銀メダル 立花・武田 試合前に「私たちは敵と闘うんじゃない。自分の最高の演技をどれだけ披露できるか」(井村ヘッドコーチ)そして、試合後に"鬼監督"と呼ばれた井村雅代ヘッドコーチは 「よくやった」と立花・武田選手を抱きしめて、泣いた。 「私のエネルギーを全部送るからね」と送り出した。 「最高の演技、念じると届くのですね」手放しで教え子をたたえた。 「(あれは、もう)演技ではなく、ファイトだ」 「メダルの色なんて何色でもいいと、今日は本心からそう思えました」 武田「金はほしかった。でも、力を出し切った。遣り残しはぜんぜん感じない、銀で満足」 立花「歯を食いしばって頑張った。精一杯戦えた事が嬉しい。今日(の演技)は今までの集大成だった」 |
| NO.73 平成16年8月26日 |
アテネ・オリンピック報道より
|
| ~アテネ・オリンピックもやっと終盤を迎えた。 日本のメダル獲得数は過去最高を更新している。 金メダルだけでも東京オリンピックの16個に、後ひとつと迫っている。 大人(過去活躍していた人々)が政治・経済で自信喪失(?)であたふたして来た・いるときに、新時代の扉が若い力、新しい指導方針(リーダーシップ)で開け放たれ、成果を出している事に喜びたい。 これはスポーツの世界だけの事でなく、これからのあらゆる側面における組織運営、リーダーシップのあり方に通じることといえる。 いつか紹介しますとNO72で書きましたが、少しでも早くと思い、いまから入力します。 『実践リーダーシップ学』第6章 リーダーとメンバーの交流を活性化して、業績をあげる手法。 それをスポーツのコーチと選手の関係に応用した記述。(藤原 直也のワールドレポート NO427より) ① 退屈な練習、ストレスのたまる訓練をおこなうときにはコーチは選手の満足度をたかめるために、支援と気配りをかかさないことが必要 (つらいことを頑張りとおすことに意味があるといって放置しないこと) ② どうやって結果を出してよいか簡単に分からない課題、選手にとって経験の乏しい課題については、リーダーは的確な指導と指示を行って選手のやる気と満足の妨げになる主要な障害を取り除く事。 (自分で考えて結果をだせといって放置さないこと) ③ コーチは選手に常に明確な課題、手ごたえのある課題を与えること。 (途方もなく高い課題やあいまいな課題を与えて後は自己努力といって放置しないこと) ④ コーチは選手がどのように課題を理解しているか理解しなければならない。 (選手が必ずしもコーチと同じように物事を考えているとは限らない事を自覚せよ) ⑤ コーチは選手の挑戦と自立の必要性を考慮せよ。 (助ける場面と見守る場面を使い分けよ) ⑥ コーチは自分の先入観が選手にどのような影響を与えているかを知れ。 (コーチは選手との間にどのような認識ギャップがあるかを理解していること) ~入力し、読み直すと私の持っている感覚・センスはいかに過去のものであるかが分かる。 ここ数年、気がつき少しでも修正、体質改善を心がけてきたつもりであるが、改めてチャックするとお恥ずかしい限りである。 だが、今回のアテネ・オリンピックで結果を出した選手と指導者には、私とあまり年齢さのないコーチ、監督がおられる。 きっと選手と同様な努力をされた事であろう。 現代のオリンピック(スポーツ)は肉体面、精神面を含めて、あらゆる経験と科学に裏打ちされたトレーニングが行われており、その国の総合力(経済的支援も入る)が示されていると思う。 そのときにあって、このような成果が出たと言う事は素晴らしいことであり、誇りに思う。 まだ、閉会式は終わってはいないが、こんな思い・考え方にさせてくれた全ての選手・監督・コーチそして関係者に感謝したい。 ただ一時の祭典と喜びに終わらせる事なく次の一歩に繋げてゆきたいものである。 |
| NO.72 平成16年8月25日 |
アテネ・オリンピック報道より
|
| 今夜(日本時間8月24日午後6時半より)、野球は準決勝戦、対オーストラリアである。 プロ選手で固めた「長嶋ジャッパン」は勝って当たり前との見方か、予選は対キューバ、対台湾、そして黒星となった対オーストラリア戦ぐらいしか、大きく報道されないできた。 その間、日本国内の高校野球大会の熱戦もあり、野球ファンはそちらに目が行ってしまったのか。 それとも読売ジャンヤンツの優勝の目がなくなったことによるのだろうか。 私なんぞの中日ドラゴンズ・ファンはチャンネルをアチコチ廻して忙しいことである。 今夜も、後楽園球場での対巨人戦である。 一方、長嶋ジャパンも予選で負けた対オーストラリアとの準決勝戦。 この一文は「コラム1」ではないかと言われてしまいそうな、書き出しである。 まず、対キューバ戦8月18日の夕刊、19日朝刊対オーストラリア、そして22日対台湾戦の報道から見てゆきましょう。(ここまでは8月24日午後5時に入力) ・ 対キューバ戦 ・ 和田一浩(県立岐阜―東北福祉大―神戸製鋼―西武) 「甲子園に行きたい」~アテネに「決まったよ」と母に~そして 「よっしゃー」と2点本塁打 「これからの野球人生のなかで、思い出に残る本塁打」 ~8月25日 午前11時である。 上記まで入力して、この後は対オーストラリア戦の勝利の後に入力しようと思っていたが、なんと1対0で負けてしまった。 よってこの間の事を入力する気が失せてしまいました。 記録として残しておくほどの事もないので割愛させていただきます。 宮本主将は「2回続けて負けたのですから、力負けです」 中畑ヘッドコーチ「すいませんとしか言いようがない」 『打線沈黙 強振 強振・・「つなぎ」失う』 とのタイトルが試合内容を示している。 リハビリのため現地で指揮がとれず、日本でテレビ観戦の長嶋茂雄日本代表監督の話 「お疲れ様でした。正直とても悔しい。 しかし、それ以上に諸君達はもっと悔しい事でしょう。 松坂君は右腕のアクシデント以降、今日は1点取られはしたものの、良くぞ投げた。 ナイスピッチングでした。 諸君たちの最後まであきらめない姿勢がテレビをみていた日本のファンの方たちに、たくさんの感動を与えている事は私もうれしい限りです。 勝っておごらず、負けて腐らず。 明日の試合も今まで通り、全力で戦ってください。 諸君達のためのオリンピックだったと思うためには、有終の美を飾る事がとても大切です」 ~私も見ていて、普段のプロ野球では見られない、クリーンナップの送りバント、滑り込みの走塁など国旗を背負っての眼差しを随所に見る事ができました。 と同時に、ペナント・レースにおいてもこんな気持ちでプレーしていたならば、球団合併・再編なども避けられたのではないかとも思いました。(いや、やはり選手に頑張りを促す前に、プロ野球協会の開かれた改革なくしては行き詰まりを打破できない事でしょう。) 本日の3位決定戦に勝利する事を期待します。 ・8月24日 夕刊より 〔女子レスリング 金メダリストを育てた中京女子大・栄和人監督について〕 『五輪で勝つ喜びより、負けの苦しさ、怖さを良く知っている。 ロスアンゼルス五輪をめざした。 直前の世界選手権は4位。が選考会で敗れる。 4年後のソウル五輪。 応援にきていた両親と会えず、集中できずに4回戦負け。 この2度の失敗が、指導者として五輪金メダリストを育てたいとの思いにつながった。 その後は、選手の環境を整えるために寮を4000万円の借金で購入。 のめりこむ練習の明け暮れに、選手の世話をしていた妻と離婚。 「五輪は選手自身の戦いであり、私の戦いでもあった」』 ・ 男子体操個人 鉄棒 銅メダル 米田 功 27歳 「一番チャンスがあると思っていた個人総合11位で終わった。自分に負けた」 「団体での金メダルをとったうれしさが薄れてきた」 「最後にいい縁起が出来て満足。個人総合のミスも修正できたし」 「五輪は想像以上にすごいところだった。自分にプレッシャーをかけながら練習してきたけど、それでも失敗した」 「北京五輪までにもっと強くなれるとおもう。自信がある。」 ~上記の発言にも新しい意識、感覚の若い人たちの力を感じさせてくれる。 「ワールド・レポート NO427」の藤原 直也さんもこんなことを書いている。 『超気持ちいいという言葉を発しながら勝利を収める。 実にすがすがしい明るさをもって勝利する。 今回の日本選手の勝ち方をみているとスポーツ界には経済界に先駆けて新しいリーダーシップを駆使するコーチ・監督がたくさん出てきている事を感じさせる。 単に頑張るだけの会社よりも業績の良い会社がある。 それは仕事を楽しく行っている会社であるというのが現代のリーダーシップの非常に興味深い結論ですが、それをスポーツ界で実行して最高の成績を上げる事に成功した人々が日本でも本格的に出てきたのではないでしょうか』 (注)「実践リーダーシップ学」にはリーダーとメンバーの交流を活性化して業績を上げる手法について解説してある。 それを読むと洩れ聞こえる"俺れ流"の中日監督・落合の言動・行動に通じるものが多い。 いつか紹介します。 |
| NO.71 平成16年8月24日 |
アテネ・オリンピック報道より
|
| 8月23日朝刊より ・ レスリング女子 48キロ級 銀メダル 伊調 千春 <五輪前> 「一緒に(妹の千春)五輪で金メダルを取ろうね」 <予選後> 「オリンピックという気がしなかった」 「試合中も監督の声が良くきこえました」 <決戦後> 「自分の勇気のなさが、金が銀に変わった」 「弱い相手ではないから思い切りやれなかった。入って返されたら怖い。 自分の勇気のなさが金と銀の差になった」 ・ レスリング女子 55キロ級 金メダル 吉田 沙保里 <予選後> 「絶対に勝たなければいけなかった」 「あと2試合。金メダルしかない」 <決戦後> 「神様が、このチャンスをあたえてくれた。私のために五輪があるみたい」 「根っこを作ってくれたのは父。花を咲かせてくれたのは監督。 根っこがしっかりしてるから、きれいな花が咲いたんだと思います」 「オリンピックの金メダルだけ家になかったので、これで全部そろいました。 (勝利の)パフオーマンスは、コーチを肩車することに決めていました。 最高にうれしかった。金メダル確実といわれてプレッシャーがあったけど、自分自身と戦い自分に負けなかったことで勝てた」 ・ レスリング女子 63キロ級 金メダル 伊調 馨 <五輪前> 「千春(姉)は何時も遠回りしてわたしに追いつく。最後に人を感動させる人です。 わたしもそんな試合がしたい」 <予選後> 「ひやひやした。あいてはロシアのレスリングだった。私は何か体が起きていない感じだった」 <決戦後> 「千春(姉)がいたからこそ・・。勇気を貰って、攻められた」 「最後には絶対自分が勝つとおもっていたので、良かったです。 千春(姉)がいたから、千春に勇気を貰って、自分も決勝戦、攻めることができました」 ・ レスリング女子 72キロ級 銅メダル 坂口 京子 <予選後> 「康生(柔道)さんが負けてびっくりした。 その分、私がなんとかしないと。 「アテネは特別。ここは縁起のいい場所」 <決戦後> 父親・元プロレスラー平吾さん 「女性としてどこまで強くなれるか」を追い求めた。 「13歳の泣き虫が、13年かけて夢をつかんだ」 ・ 女子サッカー 対米戦のその後のこと 2対1で負け 川渕サッカー協会長 「最後まであきらめない姿勢に感動した」 「彼女たちの頑張りに負けないようにしっかりと支援しないと」と強化方針を語る。 8月24日【聖地から】の記者(野村悦芳)コラムより 『直接的な負けの原因はオフサイドトラップの掛け損ないだった。 記者会見で「オフサイドトラップを指示したのは私の責任」と素直に認め、判定に一切、未練がましい態度をとらなかった。 この態度にアメリカのメデイアが驚き、日本の記者も潔さに感心。 メダルにわく今大会であるが、その何倍もの敗北がある。 勝ったときより、散り際に人柄はにじみでる。』 |
| 前のページはこちらからどうぞ |