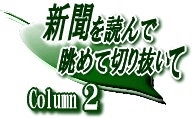 |
|
||
|
|
|||
| NO.90 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����16�N10��26�� |
�y�A�T�q�r�[���������u���@�P�O���Q�R�����
|
| �@ �@�u�n���͐��̘f���v�Ƃ����Ă��邪�A�n����̂X�V�E�T���͊C���B
�@�@�@ |
| NO.89 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����16�N10��20�� |
�y�������Ƃ���̃��[���h���|�[�g�S�R�T�����
|
| �@�w���̔N�̏t�炭���̉ԉ肪��������̂͑O�̔N�̏H�ŁA�܂��C���̍��������ɐ������Ă����A�₪�ď��~���}���ċC����������Ɖԉ�͋x����Ԃɓ���B �@���̌�A�^�~�̌������������K���ƁA���x���̌������������ڊo�܂��ƂȂ��ĉԉ�̍Ċ������n�܂�A�₪�ċC���̏㏸�Ƌ��ɒ~�ς��Ă����{�����g���Ĉ�C�ɐ������A�����ȂǑ��̐����̊����J�n�ɍ��킹�ĊJ�Ԃ���Ƃ̂��Ƃł��B �@����͖��������������l�̎d������̂�����ɂ����Ă͂܂�܂��B �@�P�ɊO���̏ɑΏ����Đ����Ă��邾���Ȃ�A�H�̎����ɂ͉Ă̗]�C�����܂ł��y���݁A���̔N�̉ԉ�̐S�z�Ȃǂ��Ȃ��ċC����������܂Ŏ��Ԃ�{��������Â��܂��B�@�₪�Ċ����Ȃ��ē����Ȃ��Ȃ�Ƃ��̂܂܃W�b�Ƃ��Ă��ĉ��������A���͂̉Ԃ��炫�n�߂��̂����ď��߂ďt���������ɋC�Â��A����ĂĉԂ��炩�����Ƃ��Ă��ԉ���{�����������o���Ă��Ȃ��A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B �@���ɗǂ��l���čs������l�͏�ɐ��̒��̕ω��ɓ���čs�����A���������i���������ɖ����̏������R�c�R�c�����߂Ă����܂��B �@�������ł����Ƃ���ł��炭�x�ށB�@���̋x�݂Ƃ͍��Ō����ƋC�����������Ă����Ƃ��ł�����A����ׂ������Ƃ͐����ɐ��̒��������Ă���Ƃ��ŁA����ΐU��q�����Ε����ɗh��Ă���Ƃ��ł��B �@����ȂƂ��͈ꎞ�x�~���đ҂��Ă���Ηǂ��̂ł��B �@�������ĊJ������̂͒g�����Ȃ����Ƃ��ł͂Ȃ��A��Ԋ����Ƃ��Ȃ̂ł��B �@���Ȃ킿�A����ׂ������Ƃ͐����ɋɌ��܂Ő��̒����������Ƃ����������ĊJ����Ƃ��ł���A����ȂɊ����Ȃ������x�ƒg�����Ȃ���͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv����u�Ԃɂ����A�g�������̂��߂̏������͂��߂�̂ł��B �@�A�̋ɂŏ������ĊJ�����āA�Ō�ɉԂ��炩����̂͒����o�Ă��Ă���A���Ȃ킿���͂̏������S�������Ă���ł���A��l�Ŕ����삯�����ĉԂ��炩���Ă��u�����炫�v�ƂȂ��Ă������Ď��R�̒��a�������A���ʂ����܂�Ă��܂��̂ł��B �@��X������������������S�����������̂ł��B�x �`�������p�ɂȂ�܂����B�^�C�g���͎�������ɂ������̂ł��B �@�ǂ߂Ȃ�قǂƊ�������̂ł����A�ł͍s���ƂȂ�Ƃ��̎��̏�A����܂����ł��B�@���͍�Ƃ�����Ώ����͐g�ɂȂ邩�Ǝ��s���Ă݂܂����B �@ �@
|
| NO.88 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����16�N10��19�� |
�y����ρ@�s��͒����u������
|
| �@�w�E�E�E�E�A��ۖ싅�Ɗ����A���ςȂljߋ��̃P�[�X�����Ă݂悤�B �@�����Z�D���͉ߋ��T��A �@ ���D���͂P�X�T�S�i���a�Q�X�j�N�g�c���t�̑ސw�Ŕ��R�M���t���a���B ���N�̕��ϊ����͗z���i�N�����N���������j�ŁA�_���i�C���n�܂����B �A �P�X�V�S�i���a�S�X�j�N���z���ő�ꎟ�Ζ��V���b�N�����z���A�c�����t�����r�A�O�ؓ��t�����܂ꂽ�B �B �P�X�W�Q�i���a�T�V�j�N���z���ŁA���E�I�ȋ��Z�ɘa�̔N�B�@��ؓ��t�����ށB���]�����t�a�� �C �P�X�W�W�i���a�U�R�j�N���z���B�@�o�u���i�C���d�グ�̔N�ŁA���N�|�����t���ސw�A�F��A�C�����t�ւƈڂ����B �D �P�X�X�X�i�����P�P�j�N�͉A�����������A���Z�p�i�h�s�j�u�[���B ���N�A�������a�����A�X���������܂ꂽ�B �����D���̔N�͊������D�ފ����̊m�����������A���ϑ����Ƃ����ď����̍s�����C�ɂȂ�Ƃ��낾�B �����s��Ƃ��Ă͗����E�����̏��������҂������Ȃ�Ƃ��낾�B�x �@�`������������������ɏo���āA�����D�����F�肵�Ă�����̂ł͂Ȃ��B �@�e����ŁA�����D���̔N�͐��ς���Ƃ͕����Ă������A���ׂĂ݂�ɂ��Ă��������s�����Ă����B�@���̋L�����ڂɂ����̂ŖY��Ȃ����ɂƂ����ɋL�^�����B �@�������Č��Ă݂�Ɗm���ɐ��ς��N�����Ă���B �@ �@���A���Ƃ�������A�R�b�v�i�����}�j�̒��̐��ςƂ������͎��セ�̂��̂��ϊv�A�]�����Ă���ɂ���ɂ�������炸�A�����Ɍ����A���u�����}���Ԃ��ׂ��A�����ς���v�Ƌ����̎����}�̃��[�_�[�������Ȃ��������Ƃ��A�₯���ς��Ō������̂ō��������҂���Ƃ���ƂȂ��Ă��܂����B�@�i�ނɔC����A���̂悤�Ȉ�̑O�̏��a�̎���i���a�͉����Ȃ�ɂ���j�ɖ߂�̂��Ǝv���āE�E�E�j �@ �]����@�ɂ͂Ȃ����������̒�R���͂Ƃ������z�G�Ƃ��āA�А��̂������i�t���[�Y�j�����X�Ɍ��ɂ��A���S���o����Ȃ��ꎞ���̂��ő�O�A�e���r�͂������̂́A���ǁA�����\�ȐV�������̂�����A���l�ρA�\���A�����A���x���̕����݂͂����A�����̃}���J�V�ȏC���Ŏ���ϊv�E�\�����v�̎��ԉ����������ɉ߂��Ȃ������B�i�O�̓��t�A���}�V�Ƃ����������邪�A�j�S�̂Ƃ���ɂ͎肪���炸�A�����}�̉����ƂȂ��������j ���ʁA�^�̕ϊv��x�点�����ɂȂ����B�i�������̖����\���A�����\���̉����B�j �@��}���s�b��Ȃ����A����͒ɂ݂������A�ۂ����߂�A�����A�ێ�I�i�����S�̂ɉ��t���ƁA���x�͍s�߂��邭�炢�ɓ˂�����j�ȍ������ɂ��̂��낤�B �@����ł��A���̍������E�ōŏ��Ƀo�u�������̌����A���E��į�߂��s�����Ƃ��āA�V����̐��E�����A���̂�����A�l�X�̐������̈�̃��f���̒����҂���Ă��鍑�Ȃ̂ł���B �@�܂��A�g�߂ȂƂ���ł́A���{�ō���Ԍ��C���ǂ��Ƃ����钆���̒��S�n���É��͒����h���S���Y�̗D���i���������{��Ƃ��Ȃ�A�����Ȃ�j�B�@ ������ɗ����A�������ۋ�`�u�Z���g���A�v�J�`�A�u���E�n�����v�J�ÂƂȂ�ƁA�R�b�v�̒��̐��ρi��~�̐킢�j�Ȃɖڂ�D���Ă���Ƃ��ł͂Ȃ��ƍl���܂��B �V����̖����関���ւ̔����J�������͂̒n�ƂȂ�˂Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@ �����A���邢�͗����E�P�ƔN�Ŏ��͍ς܂����قǒP���A�ȒP�Ȏ���Ɏ������͑��݂��A�����A�������Ă���̂ł͂Ȃ��B�@ ����̎���̍Ō�̏I���̖��������i�߂��Ă���Ɠ����ɁA����Ői�s������{�i�I�Œ����̎��Ԃ�v����V�K���������i�j���[�f�C�[���j�̃X�^�[�g�ɗ����Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B �@�@���̎���A�Љ���������ł��⊶�Ǝv���Ă���C����������Ȃ�A�����Ɏ������ӔC�̈���~�߂āA�e�����l���肩��E���ĕ���i�߂�Ƃ��łƌ����������Ă��܂��B �@ �h���S���Y�̗D���̔N�̘b����v��ʕ����ɘb��������ł��܂��܂����B ������D���Ƃ����͂����ݏo�������̂Ȃ̂ł��傤���B
|
| NO.87 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����16�N10��19�� |
�y�Ђ�@������̂قǂقǐl���_�@�P�O���P�V�����
|
| �@�w�@���͐^���ԂȉR���B�n����Ɋy��y�Ȃ�ĉR�Ɍ��܂��Ă���B�@���{�̒m���l�́A�قƂ�ǂ̐l�������v���Ă���悤�ł��B�E�E���E�E�E �@�\�݂Ȃ��[�Ƃ������t������܂��B�w�L�����x�ɂ��܂��ƁA�s�������قɂ��鎖���ɂ��āA�@���ケ��ꎋ����t�Ɖ������Ă��܂��B�@���Ƃ��s�َ��́A�����ɂ��ẮA���ɐ��܂ꂽ���̂Ƃ݂Ȃ��t�Ƃ���܂��B�E�E�E���E�E �@�����̂���y������Ɠ����ł��B�@�F����Ԃ̉����ɂ����݂��܂���B�����������҂́A���ꂪ����Ƃ݂Ȃ��Ă���̂ł��B�@�����݂Ȃ����Ƃ��A�M���邱�ƂȂ̂ł��B�E�E���E�E �@�Ȃ��A�����́A����y������Ƃ݂Ȃ��̂ł��傤���H �@���̐��ŁA������x�▼�_���l�����悤�ƁA���������̐��E�Ɏ������ނ��Ƃ͏o���܂���B�@�������ɁA����y������Ƃ��āA���̂���y�ɂ����Ă��������o����̂́A���̐��ō�����A�|�������v���o�\�����ł��B�@�����Ƃ������Ǝv���܂��B�E�E�E���E�E�E �@����y��M���Ă���l�́A�l���̂ǂ����ł̒i�K�ŁA����y�ɂ����čs���A�u�������v���o�v����낤�Ƃ��܂��B �E �E�E�E���E�E�E ����y������Ƃ݂Ȃ��A����y�̑��݂�M����ꂽ���A�u�������v���o�v�����A���悤�Ȑ��������ł���̂ł��B ����y�Ȃ�ĉR���ς����Ǝv���Ă���l�́A�����x�▼�_�Ɏ���������ق��ɂȂ������ł��B �@���������l�͋C�̓ł��ƁA���͎v���Ă��܂��B�x �`�������p�ɂȂ�܂����B�@����ł��S�̂̕��͂̔����ɏk�����܂����B �@�����ƕ�����₷���A�Ⴆ�b�����p����Ă����̂ł����A���������Ă��������܂����B �@�������g�̂��Ƃ�U��Ԃ��Ă݂�ƁA�x�▼�_����]���A�ǂ������������ł������Ǝv�킴������܂���B�@ �@�u�����̂��������������v�Ȃǂƌ��ɂ������͂���܂����A��������~�̉������ł��������Ǝv���܂��B�@�����āA���ȕٌ삷��Ƃ����Ȃ�A���̂܂ܐi�ނƁu���o�C�v�ƋC�Â��Ȃ������킯�ł͂Ȃ������̂ł����A����o���ē����o�����͎��ȋ\�ԁA���܂�ɂ��g����Ɗ��������炾��������ł��傤���B �@����A�����͎��s���Ă��邻�̎��Ɏ���̗���������Ă������Ƃ�����܂����B �@�����������x�̌`�ɂ��鎖���o����̂Ȃ�A�u�����̂����������ƂɂȂ�v�Ƃ̎v�������������Ƃ͎����ł����B �@���A�u�������v���o�v���ƕ\���o����悤�ȍl�����ł͂Ȃ����Ƃ��Ƃ͊m���ł��B�@ �@�����ŁA�����Ɏ��グ�邱�ƋC�ɂȂ����̂ł��傤���B �u�������v���o�v����������ł��n�߂Ă݂悤�Ǝv���Ă��邱�̂���ł��B
|
| NO.86 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����16�N10��17�� |
�y�_�C�G�[�A�������f�O�@
|
| �@�P�O���P�S���̒����̌������ł���B �@���X�̖��ł��邪�A��͂�s�Ǎ����̍ő�̉ۑ�ł��������͊m���ł���B �@���̉e���͂��]��̂��傫���Đ��{���i������t�j��x�ׂ͒��Ȃ��Ƃ̔��f����A��s�c�Ɏx���v���������o�܂̂���A���扄���̉ۑ�ł������B �@�悪�����Ă���̂ɂ��̏����̑Ή������Ă����Ⴆ����ۑ�ł������B �@���̎����ǂ������������Ƃ����̂ł͂Ȃ��B �@�_�C�G�[�Ƃ����͎̂��ɂƂ��ĐN������R�O��`�S�O��O���ɖ��R���������Ă��ꂽ��Ɩ��ł������B �@�����Y�ƁA�ƑԂ̗��ʋƂɍݐЂ��Ă������ɂ����A�_�C�G�[�̐������W�A����͓����Ɏ��̃G�l���M�[��~�����Ă����̂ł������B �@���������Ȃ��Ƃ������͊��ɓ����̃_�C�G�[�͗��ʋƊE�̃g�b�v�u�S�ݓX�O�z�v��ǂ��z���ăg�b�v�ƂȂ�A���X�ƑS���W�J�ɏ��o���Ă������B �@�����Ԃ����̂ł͂Ȃ����Ƃ��v�����قǂł������B�@���A����ł̓_�C�G�[�̊���͂��̋ƊE�̐����E���W�̉\�����������̂ł��藊�������A�u��[���A������邺�I�v�Ƃ������������Ă��ꂽ�B �@�u��X�̍s���Ƃ���K������@�@��X�̂���Ƃ���K������@�Ƃ̐M�O�������� �@���邢�Љ���ɍv������v�@�Ƃ̎А��E�X���[�K���ɔR�������̂ł���B �@�o�u�������̂Q�`�R�N����A��藬�ʋƊE�͑��̎Y�ƁA�ƊE�Ɠ��l�ɒ�����Ă������B�@�����̒��Ԍ��Z�̏����Ă��\���s���Ǝ�ŁA�����Ƃ����X�g���A���Ƃ̍ĕ҂ɂ���čň�����E�����ƕ��钆�A�Ⴆ�Ȃ��������Ă���B �@ �����ň꒚�オ��̎�������̗��ʋƂ̐헪���p���Ă���Ƃ����̂ł͂Ȃ��B ���̃R�����Ŏ��グ��̂��~�߂悤�ƐV����p�i����̑��ɔ��肱�����Ǝv�����Ƃ���A�ēx�ڂɂ����̂ŁA�����͂��Ƃ��ꌾ�ł�����قǂɔR���������Ă��ꂽ��ЁA�g�b�v�m�В��̂��ƂɊ��ӂ����߂ċL�^���c���Ă����ׂ��ƍl�������Ă����܂œ��͂��܂����B �@ �N�������҂Ƃ��āA�������Ă��̋ƊE�ɍݐЂ����҂Ƃ��Ă��ꂩ��̗��ʋƂ̈�̂������ʓr��Ă��Ă݂����B �@�����āA����قǕ����������Ă��ꂽ�_�C�G�[�̏I���������T�ς��Ă���̂͐\����Ȃ��Ǝv������ł���܂��B �@���͏�ɗ���A�V���Ȃ鎞�オ�܂��n������Ă䂫�܂��B �@ �@
|
| NO.85 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����16�N10��16�� |
�y�a�l�c�E���E���E�_�E��@���ʐM�@�m�n�R�X���
|
| �@���̏��ʐM�����̃R�����Ŏ��グ��̂͏��߂ĂƂ������܂��B �@�����V�N�P�P���P�T���Ɂu�Ȋw�Z�p��{�@�v���{�s����܂����B �@���̊�{�@�͍���̂킪���̉Ȋw�Z�p����̊�{�I�Șg�g�݂�^������̂ł��B �@�܂��A�킪�����A�Q�P���I�ɂނ��āu�Ȋw�Z�p�n�������v���߂����ĉȊw�Z�p�̐U�������͂ɐ��i���Ă䂭��ł̃o�b�N�{�[���Ƃ��Ĉʒu�t������@���ł��B�i���t�{�z�[���y�[�W��蔲���j �@�����ĕ����P�P�N�P���̑����͔N���̎��Ŕ��Ȋw����{�Ƃ����u�i�m�e�N�m���W�[�v�ɂ��u�Ȋw�Z�p�n�������v��ڎw������錾���܂����B �@���̕���͏��ʐM�E��ÁE���E���C�t�T�C�G���X�E�ޗ��E�E�Ƃ���Ă��܂��B �@�ȏ�̂��Ƃ��玄�ɂ͐��m�ɔF���ł��Ȃ����ł��B�@ ���A�w��ɂ͖ڂɌ����Ȃ����E�͊܂߂Ȃ��Ƃ���Ă����̂��A�ڂɌ����Ȃ����ׂȉȊw���܂ޑ����Ȋw�̍\�z�Ƃ��̑����Ȋw�̍\�z�Ƃ��̑����Ȋw����{�Ƃ����@���̎{�s�A����Ɋ�Â����{�̎Љ���܂��A�w�����悤�Ƃ��Ă���Ɛ錾�����Ǝ~�߂��܂����B ���̔��ׂȐ��E�ɒ��ڂ��Č����𑱂��Ă���ꂽ�̂��A����Љ��ߓ��@�a�q����ł��B �@���͂P�O���N�O�ɏ����ɂ���Ēm��A����ȗ��J�����ꂽ���i�̈ꕔ�����킹�Ă��������Ă��܂��B�@���������Ă���ʐM�̒��́g���敗�h�Ƃ����R��������ł��B �w���ׂȉȊw����{�Ƃ����V��������́A����������𐧂���悤�ɂȂ�A�Q�P���I�͐S�̎���ɂȂ�Ƃ����Ă��܂��B �@���̍l�������p���ł���̂��A�����{�̍��́u�l�Ǝ��R�ɂ₳�����v�Ƃ�����{�@�����A�e�Ȃ����̍l��������{�Ƃ��A��茻���I�ɋ�̓I�Ɋ�{�v����쐬���Ă��܂��B �E �E�E�����E�E �@���̊�{�@�����܂ꂽ�v���͐l�Ԃ̒m�b�ł͂Ȃ��A�n���̉c�݂Ƃ�������s���Ă���A���R�ɑ��Ă͉ߋ��̎��s�Ȃ��A�Đ������A�l�ɂ����ẮA����犴���փn�[�h����\�t�g�ւƕω�����������e�ł���A�X�̗͂����f���閯�Ԏ哱�^�̎Љ������������̂ł���A���܂łƂ͈Ⴄ�ƐM���Ă��܂��B�x �`���̕��̕��͓��e�͉��������ɂ͓�������܂��B�@�������n�v�l�ł��藝�n�v�l���ア���ɂ����̂ł��傤���A����ł������Ȃ����E�̎��ɂ͊S������Ɠ����ɁA���̑��݂��ǂ��炩�Ƃ����ƐM���Ă���̂ŁA���Ƃ��������Ă������ł���B �@ �{���̌ߌ�́u�g���̉�v�̒���Ŗ��É��E�����ɏo�|�����ԂƉ�܂��B�@ �����Ắu�g���v�Ƃ��������Ōh��������������������i�����̏@���Ƃ��Ԃ����āj�A�������N�Љ�̕s����������s���E�s�M�E�s���̒��A�����͎����X���Ă�����������B �@���A���x�͎�������M���������Ƃ������A���Ă��܂��āA���̓��̗���̂�҂����Ȃ����ƁA���̎��ɑ�������͏��Ȃ��Ȃ��Ă���Ƃ����̂�����ł���B �@����x�̒��ԂƂ̉�ŁA�V����̓����Ƒ��̎��̐S�\���ƍs���𖧂��Ɍ����������Ă��鎄�ł���A����ł�����B �@
|
| NO.84 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����16�N10��12�� |
�y�k���߂�ڂɁ@�[���l�@�u�������v�@�c�Ӂ@���q
|
| �@�E�E�E�A�Ⴂ���������̎G���ɁA�u�y�����l���̃q���g�v�Ƃ����悤�ȃG�b�Z�C���˗�����A���̂悤�Ȓ�Ă����Ă݂��B �@���܂��A�l���͏�Ƀo���F�A�ƐM���邱�Ɓ� �@���l���͖�����ɒl���遄 �@���l������ɓ����ɂ͏����ȓw�́A�傫�ȗE�C��Y��Ȃ��Ł� �@���̌��e���Q���ɂȂ��Ăe�`�w�ŗ���Ă����B�@�]���ɕҏW�҂̒�K�����Ă��悤�ȕM�ՁB �@���搶�A�ʔ��������e��L��Ƃ��������܂����B�@�����͏�Ƀo���F�A���͖�����ɒl����A������ɓ����ɂ͏����ȓw�́A�傫�ȗE�C�\�Ȃ�Ĉӕ\�����Ėʔ����ł��� �@���̓Q�������ċ��|�����B�@�l�����S�ċ��ɂȂ��Ă���B�x �@�`���ɂ�������̎��Ǝv���܂����A�u�l�v�Ɓu���v���u�������v�ŏ�����Ă����̂ŁA�u���v�ƂȂ��ēǂ܂ꂽ�Ƃ������Ƃł���B�@���āA�����蔲�����B �@�u�l���v�S�āu���v�ƓǂA�����Ⴂ�ҏW�҂ł��낤�B�@���{������A�����m�����x���̕��ł��낤�ҏW�҂ɂ��Ă��̎n���ł���B���������Ă����������Ȃ�����ɂȂ����؋��ł����낤���B����Ƃ���͂�u�l���v�́u���v�Ȃ��H �@���͎������ɔF������A�g���M�ɉ����āA���G�Ȏ��ł���h �@�ǂ݊��ꂽ���ł����A�u�R�x�ǂݒ����āA����ƂȂ�ƂȂ�������v�Ɖ�����������B �@�c�ӂ���̂��̃G�b�Z�C��ǂ�ŁA���\�M�܂߂Ȏ��̏o�����莆�A�n�K�L�͂ǂ̂悤�ɓǂ܂ꂽ���Ƃł��낤���E�E�E �@�ߍ��̎Ⴂ�l�̏������͊����̂悤�Ȑ^�l�p���A���������܂����ە����Ō����Ȃ��B �@�N�ɂ����������Ȃ��悤�Ɋ����̂悤�ɂȂ邩�i�˂����邩�j�A������C�ɂ��ď_�炩���A���̂Ȃ��ۂ܂��������ɂȂ�̂ł��낤���B �@���M�ŗ��G�ȕ����A�����C�����ď����Ă݂悤�Ƃ͔��Ȃ���̂����E�E�E |
| NO.83 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����16�N10��2�� |
�y�M���ƃ��X�g���Ȃ��S���싅
|
| �@�m�n�W�Q�Łu�V���[�_�[�V�b�v�_�Ɨ����єz�v�������Ƃ͌��������̂́A���S�_���߂��ꂸ�ɁA�V�������x�����x���ǂݕԂ��Ă݂��B �@���_�́g��ɐM���A��ɐM���@�`�[�����[�N�Ƌ����h�ƂɎ������B �@ �@���̎�����ǂ�Ȏ����ƍ˔\���������l�̏W�c�ł��邩�͖����B ����ɑ��ė����ḗw�F�v���A���̐��E�ɓ����Ă���z�́A�݂�Ȕ�}�ȍ˔\�������Ă���B�ꗬ�Ȃ̂��x�ƑI���F�߂�Ƃ��납��n�܂����B �@�Ƃ͂����A�`�[���͒��ǂ��N���u�ł͂Ȃ��B�����Љ�̒��ł̓`�[���������Ƃɂ���ď��߂ă`�[���́A�����ċ��E�̋������\�ƂȂ�B �@���N�̒����͈�R�A��R�̍����L�����v�Ŏn�܂�A�I�肪������f�X�^�[�g�����B �@ �@�����ē��g�A�P���������т��c���Ă��邪�A���߂���G���[�g�I��Ƃ��Ă��̐��E�ɓ����Ă����킯�ł͂Ȃ��B�@����䂦�ɑI��̒ɂ݂�������B �@�w�I���͈�R������ł��̐��E�ɓ����Ă����l�ԁA�G���[�g�Ƃ͈Ⴄ�x �@���������S�Ɛl�ɂ͌����Ȃ����K�ʂ��������B�w�w�͂͗���Ȃ��x �@���[�_�[�V�b�v�̋Z�p�̈�ɁA�u�R�[�`����\�́A��q�����炷��Z�p�A�l�̔\�͂��J������Z�p�v������B�@�ē͌X�l�̗͗ʂɌ�������邱�ƂȂ��A�v���Ƃ��ē��c���Ă����I��̍˔\�A�����Ȃlj\�������o���A�����o�����B �@ �@���ł͒����̐擪�Ŏ҂Ƃ��Ė����Ă͂Ȃ�Ȃ��r�ؑI��A�w�łĂȂ��ėǂ��B�@���O�̎���͈ꋉ�i�Ȃ���A���S���Đ킦�x�Ƃ������B�@���S�ł��A�܂���Ɏ����ɏo�ꂷ�鎖�ɂ���āA�o�������M�ƂȂ��Ĉ�[�I��Ƃ̓��{��̓�V�ԃR���r�ƂȂ������肩�A���Ⴆ��悤�ȍ��ŗ����c�����ɂȂ����B �@�x�e�������Q���������ƁA�J�������̑�s���̊Ԃ��g���������B�w�O����ē�����O�x�A�����Ńx�e�����́w�����M���Ȃ����x�Ƃ����B �@���̌�̓��ɂU�`�V���̊���͖ڂ���������̂��������B �ȏ��U��Ԃ��Ă݂�Ɓg�䖝�łȂ��A�I���M���������h�B�I���F�߂鎖�ɂ���ĐM���ݏo�����Ƃ�����B �@�������A�ڕW�́u���{��v�ƌ��������A�������ڕW�m�ɂ��Đ킢�������B �@�Z���[�O�D�������߁A���͓��{�V���[�Y�ł���B�@���Ō����قǐ��Ղ������̂ł͂Ȃ����낤���A�S�苭���A������߂Ȃ��A�R�c�R�c�ƌq���̖싅�A�X�ɉ����ē��O��̓S�ǂȎ���A���X�ƌJ��o������w�̐w�e���l����Ɩ��͖c��ށB �@����͒P�Ƀv���싅�̐��E�Ƃ��������łȂ��A�z�[���������͈�ʂ̋��l�̂S�O���A�`�[���ŗ����Z���[�O�̑�T�ʂƉ��ʂɂ���Ȃ���A���A�x�e�����̌����Z�������ʂ����������ƁB �@�g�D�̎��ԂƂ��Ďg���̂Ă�Љ�E��Бg�D�A�ڐ�̗��v�ɂƂ���Ĉ��Ղȃ��X�g���̎��������ɖ����o�c�ɑ��āA�����N�T�����[�}���Ɋ�]��^�������A��Љ^�c�̂�����ɂ��傢�Ȃ��𓊂������ɂȂ����B �@�O���[�o���X�^���_�[�h�E�A�����J���A�s�ꌴ����ӓ|�̂����Ɍ��E���݂�B �@�Ԏ��̎��Ƃ������E���v�ɂ��A�܂��ɑ傢�Ȃ郂�f�����������Ƃ������ƂɂȂ�B �@���ۛ��`�[���̂��Ƃ��������A��c�����ɂȂ����ł��낤���B �@ |
| NO.82 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����16�N10��2�� |
�y�����T�N�Ԃ�@�D���I��M����͒�グ�z
|
| �@�@���Ԃ̖��ł������Ƃ͂����A���̋L�����f�ڂ��������҂��ǂ����������B �@����܂��������Ƃ����̂��A���N���g�����l�ɕ����Ă̗D������B�i�ǂ�Ȍ`�ł����Ă悢�B�@�D���͗D���j�@ �L���A�����������P�Q��ɔj��A�����`���グ�Ƃ����̂Ƀu���E���ǂ�ʂ��Ă݂Ă���ƁA�f���Ɋ�ׂȂ��Ƃ������A��C�ɐ���オ��Ȃ����i�������B�@ ����ƃ_�C�������h�ŗ����ē̓��グ���n�܂��������A�I��ɏΊ炪�݂�ꂽ�B �@�{���͑��̎��̎����g�̊��z�A�������q�ׂ�Ƃ����̂ł͂Ȃ��B �@���X�V�S�̐��i�̂ɁA���Ԃ��������߂������B�@���������C���C��������ꂽ�v���싅�ĕ҂ɗ��ރX�g���A�u�v���싅�X�g�ƐV���[�_�[�V�b�v�_�v�ł��B �@���̎��̎t���ł���A�������Ƃ���̕���e�[�v���Q�l�ɂ��āA�܂Ƃ߂����̂ł���B �@����̑����͑I���ɗ��Ɛ헪���������B �@����́u�v���싅�I�������z�[���y�[�W�v�ɂ��f�ڂ���Ă���B �E �I�葤�́g�v���싅�͒N�̂��̂��H�@���̂��߂ɂ���̂��H�h�ƒ�N���Ă����B ����Ɍ̂ɁA�ꕔ�̋��c�ɐ�͂Ǝ������W������̂����������ƌ����Ă���B ����ɑ��Čo�c�ґ��͎������~�A��������ȋ��c�̎��{�̘_���ł������B ���ߋ��Ɂu���q���ւ��������Ƃ����B�@�Q�`�R�l�̈��|�I�ɋ����I�肪���āA��ɏ��s�����܂��Ă����B���Ǐ������A�q�����ɂȂ炸�ɁA�p�~�ƂȂ����� �E ���I���s���T�������̒��� �u�I���́A�������f�C�A�Ƃ��āA�z�[���y�[�W�����p���A�L�������J�����܂��v�Ƃ���B �V���A�e���r�̃}�X���f�C�A�ł͂Ȃ��A�C���^�[�l�b�g�E�z�[���y�[�W�����p����Ƃ����헪�����ʂ����B�@�ꕔ�}�X�R�~�Ɏx�z�A�c�߂��Ă���}�X���f�C�A�ł͂Ȃ��A�{���ɋ��c��������t�@���̓C���^�[�l�b�g�ŏ���m��A���[���ʼn������B �@�����݃C���N�ŋN���Ă���A�����J�A�A�����J�R�̓C���^�[�l�b�g�ō��X�Ə���J����Ă��鎖�ɂ��A�^���̏���ɂ���ċꋫ�ɗ����Ă���B���╉������������Ă���Ƃ����遄 �@ �@�X���P�X���i�X�g���s�̓��j��������E���}�n�z�[���Łu�݂�Ȗ싅���D���Ȃv�`�t�@���̊F�l�ƑI��̏W�����J�Â��ꂽ�B �@���̏��̓}�X���f�C�A�ł͕���Ă��Ȃ��B�@�X�^�[�ƈ�ʂ̐l�Ƃ����W�A���i�A�u���E���ǂ̌������ɂ���l�Ƃ����W�łȂ��W���ł������B �@���̂��Ƃ�ʂ��đI����t�@���̂��߂Ƃ����d���Ǝ������������낤�B �@���C�A������^����Ƃ����V�����������l���I�聁�X�p�[�X�^�[�ł���ƁE�E �E �싅�͕������ł���B �������͌����Čo�c�ҁA�I�[�i�[�����L������́A�ǂ����Ă��ǂ��Ƃ������̂ł͂Ȃ��B�@�ꎞ���a���肵�Ă�����̂Ƃ������l�̂��̂ł���B ����͔��p�فA�y�c�A���c�A�z�e���A���c���������ƂŁA���j�̒��̎g�����������Ă���B�@�����̕Ƃ��Č����т炩�����̂ł͂Ȃ��B ���Ȃ킿�A�n��A���������ɍ����������́B�g�F�̃��m�h�Ȃ̂��B �ȏ�̂R�_����̍l�@�Ɍ�����悤�ɁA����̃v���싅�̍ĕҖ�肩��[�����X�g���C�L���͐V����Ɍ������ĕϊv�̎�������Ă��鍡�A����̂���ׂ��u�V���[�_�[�V�b�v�̂�����v�������Ă���Ƃ�����B �t���̈ӂ��\���ɋ���ł܂Ƃ߂łȂ��Ƃ���A�S�Ď��̎���Ȃ��ł� ����ɑ����āA�����E�����ē̍єz���@���ɐV���[�_�[�V�b�v�_�ɂ��Ȃ������̂����Љ�悤�Ǝv���܂��B |
| NO.81�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����16�N9��24�� |
�y���̐l�@�����V���X���Q�S���������
|
| �@�w�č��͈��|�I�Ȍo�ϗ͂ƌR���͂Ő��E�̋��X�܂ʼne���͂��y�ڂ��B �@�u�e�����鑤�ɂ��đ哝�̑I�Ɉӌ���\�����錠���͂���v�ƃC���^�[�l�b�g�ō��ۓ��[���n�߂��B�@�z�[���y�[�W��http://www.choice21.org �@���炪������鍑�A�ł̐�Z�����̌����錾�����č��́g�W�Q�h�œ�q�����B�@ �u�b��������ςݏd�ˁA�l�ގЉ���F�ō��Ƃ������ێЉ�̓y�䂪���̂S�N�Ԃłނ��Ⴍ����ɂȂ����B�@�ق��Ă����Ȃ��v�x �@��L�̂��Ƃ͂P�O���P�U���ɑI�����ʂ����\�����Ƃ����S�������Č���肽���B �@�{�����ɂ͑����������t�̊�Ԃꂪ���܂�Ƃ������A���ꂾ���A�����J�E�u�b�V���̌����Ȃ�ɂȂ��Ă���i����A��̐��������Ēǐ����Ă���j�䂪���̎̌����A�s�������邱�ƂȂ��炱�̍��ۓ��[�Ɉ�[�𓊂��鎖�ɂ����B �@���̂悤�ȃC���^�[�l�g�̊��p�̂���̂��Ɗ��S������A���̉��ɍL����G�l���M�[�͐��E���삯����l�b�g���[�N�ƂȂ��āA���ь����Ɠ����ɉ����ǂ̂悤�ɑI�����Ĕ��f���Ă䂭�̂��������Ɗ����Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��B �@�H�J�O���������m��ɗ��܂�{�����{�~�肪�����Ă���B �@�����������͉J�ŗ�����Ă͂��Ȃ����낤���H |
| �O�̃y�[�W�͂����炩��ǂ��� |