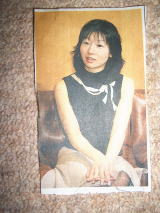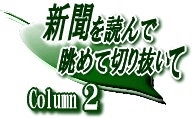 |
|
||
| NO.120 平成17年2月18日 記 |
中部国際空港 ”セントレア” が開港した。 |
2月17日、中部国際空港、通称”セントレア”が開港した。  その前日2月16日、名古屋空港は中部の国際線、空の玄関の幕が閉められた。 代わって、伊勢湾・知多・常滑沖に新中部国際空港がオープンした。  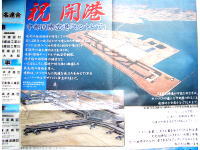 2月17日開港記念特集の中日新聞より、転載  そして、数々の夢や希望を載せて新空港が開港した。 3月25日からは「愛・地球博」が始まる。 世界の人々がこの空港に降り立つ事になる。 |
| NO.119 平成17年2月14日 記 |
【今週のことば 池田 勇諦】2月13日朝刊より『仏に帰依せば 終(つい)にまた その余の諸天神に帰依せざれ 『涅槃経』 |
| 2月15日は仏教の開祖・釈迦の入滅の日と伝える。 「死」を「入滅」、涅槃に入ること、と説くところに、仏教の「死生観」があらわれている。 「涅槃」は原語サンスクリットのニルバアーナで、「吹き消すこと」または「吹き消した状態」といい、煩悩の火が消滅して智慧が完成した「さとり」をあらわすとされる。 それは涅槃がわたしたちにとって、「生」の「完全燃焼」を意味することによって、却って現在の行きかたを問い返す「光」と説く。 その意味で標記の一節からわたしたちは、いかに似非(えせ)ものに呪縛され不完全燃焼の生きかたをしている事か。 “幽霊”は他人事ではない。 愚痴る、残念(念が残る)みんな幽霊の象徴だ。』 〜毎朝、神棚に向かう中に、『延命十句観音経』がある。 そこに「常楽我浄」(じょうらくがじょう)との4字があり、 「常徳」「楽徳」「我徳」「浄徳」の4つの徳を実行せよと教えている。 その「浄徳」とは“トン・ジン・チ”(残念ながら私の日本語力では変換できない) 意味するところは「貪る」(むさぼる)「怒る」「愚痴る」ということです。 ところで以前にも書きました私事ですが、私の父の死の瞬間は私の腕の中で息を引き取る直前、「それでは皆さんサヨウナラ」と一言言ったことです。 このことは、その後色んな方のお話を聴くにつけなかなか出来る事ではないということが理解できるようになり、今では私の最後の時における課題となっています。 全ての煩悩を吹き消して、涅槃に逝けるとは思ってもいませんが、せめて「みなさん、アリガトウ、サヨウナラ」と言って見たいものだと願っています。 |
| NO.118 平成17年2月13日 記 |
【けさのことば 岡井 隆 2月11日朝刊より】 |
| 二日続けての「けさのことば」である。 こんな事は初めてではないか。 と言って何が、どうと言うことはないのだが・・・・ 『我らは常に単純なる心を持ちたい。 そして複雑なるこの世を味い知りたいと思う。』 『藤村随筆集」(十川信介編) 島崎藤村 「修道者が、身に粗服を纏い」 「家を捨て」 「寂しき生涯を草庵に送った」というのも、簡素な生活から「単純な心」が生まれると信じたからだ。 それほどまでに社会は複雑になってしまっている証拠でもある。 ということは「単純なる心」は容易なことでは持つことはできないということだ。』 〜本日長野県木曽郡山口村が岐阜県中津川市に併合された。 そのために本日の「けさのことば」に、中仙道・馬篭宿(山口村)に生まれ、育った島崎藤村が登場したわけでもないだろうが、私のイメージでは明治時代になり、その地の指導的立場にあった旧家が押し寄せる新たな時代の波の中で、寂れ逝く旧街道とそれまでのシキタリ・因習の中で、事実を元に書き上げられていった作品内容が浮かび上がる。 富国強兵・先進欧米諸国に追いつけ、追い越せと遮二無二と走った日本。 列強と肩を並べたと思ったら、それはバランスを欠いた猪突猛進でゼロとなる。 再び、様々な状況・条件が重なり、それまでの世界歴史になかったスピードで復興・再建から右肩上がりの成長。 そして1989年にその頂点を極めた。 それから15年の今、「不満、不信、不安」という言葉が支配して、 大半の人々には「夢、希望」の語が見当たらない。 世界秩序の安定は当分望めそうにない。 日本の政治、経済、金融、社会、教育等、あらゆる分野で、これではいけないと口にして、また感じてはいるものの次なる道筋に向かっての歩みは遅々として進んでいない。 藤村の言った言葉の時代背景と次元は異なるが、「単純なる心も持って、この世を味い知りたいと思う」に、心が反応した今朝でした。 |
| NO.117 平成17年2月11日 記 |
【けさのことば 岡井 隆 2月10日朝刊より】 |
|
『歩きはじめたばかりの坊やは/ 歩くことでしあわせ/ 歌を覚えたての子供は/ うたうことでしあわせ 「しあわせ」 高田敏子 「坊や」とか、「子供」とか言うが、このごろは大人も同じだ。 大人も、また、ならいたてのパソコン、料理、運動から「しあわせ」以上のものを得て生きる不思議な時代』 〜「いやあ〜! 僕はしあわせだなあ〜。 パソコンも、運動も、朝昼晩のご飯もある。 庭では次々と芽を出し、花をつける花々があり。 今年から放送大学の生徒にもなれる。 どんな新しい知識が加わって、どんな新しい友達との出会いがあるのだろうか。 なんたって、毎日美味しくワンカップのワインが飲める。
|
| NO.116 平成17年2月11日 記 |
【週をひらく フオト歳時記 岩木呂 卓巳
|
| 〜この連載は毎週楽しみに読み、眺めている。 時々の花が紹介されるからです。 特に今回は「ロウバイ」です。 昨年までは写真がなかったので、私のコラムには1‾2回しか登場しませんでしたが、今年はコラム1−Dに4回は写真付きで登場しました。 好きな花、香の良い花、この時期に花がないこともあります。 それと同じような事が、岩木呂さんのエッセイにも書かれていました。    『ロウバイの花を近くで眺めているとうっとりした気分になり、時間がたつのを忘れてしまう。 理由はロウバイから放たれる甘美な香のせいだ。 ただ余りにも濃厚な香のため、長時間かぐと気分が悪くなる人もいるという。(略) 中国の原産で、江戸時代に朝鮮から日本に観賞用として入ってきた。 当時から高貴な人たちに人気があり、冬の間、この花を眺めて至福の時を楽しんだらしい。 ただ不思議な事にこの花を季語とした有名な短歌や俳句が見当たらない。 ロウバイを漢字で書くと「蝋梅」となる。 梅という字がはいっているが、梅の仲間ではない。 名前の由来は蜜蝋の色とか半透明のロウ細工に似ているとか、蝋月(陰暦の12月)に似た花を咲かせるからとかの諸説がある。 寒い冬にこれだけ強烈な香を放つ理由はなぜなのか。 植物が香を発するのは第一に受粉活動のためにある。 昆虫をおびき寄せ、花粉を運んでもらうためだ。 でもいまは精力的に活動している虫などいない。 ひょっとすると、人間をたのしませるためなのであろうか。』 〜私はこの時期虫になって、受粉活動のお手伝いをしているのかもしれない。 花に鼻を近づけるどころか、提灯の形をした花弁の中にまで鼻先を押し込んで、この花の香を楽しんでいる。 確かにときにクラクラとしてしまうほどの強烈な香ではあるが、一瞬冬の戸外の寒さを忘れさせてくれる。 受粉成功のためか、数年前には数個の実をつけた。 鉢に押し込んでおいたら一つだけ芽をだした。 なかなか大きくならない木である。 今は背丈30Cmになった。 今年当たりは地面に降ろしてやろうかと思っている。 |
| NO.115 平成17年2月6日 記 |
【『恋する歌音(カオン)
|
|
このコラムのNO111で取り上げた、佐藤真由美さんへのインタビューである。 |
|
|
|||||
| NO.112 平成17年1月31日 記 | |||||
【“現代を読む” 千葉商科大学長 加藤 寛
|
|||||
| なぜ国民の関心事、年金改革でも、景気回復でもない郵政改革が重要なのかを元・政府税調・調査会会長の加藤寛学長が書いている。 『国民には郵便貯金・簡保を原資とした公的部門が官僚支配の要となり、国民生活を保護・規制で縛り、大きな政府の官製国家を創り上げていることが目にみえないからだ。 この資金の囲い込みが年金改革を阻み、2007年問題対応を遅らせている。 ① 2007年、日本の人口減少がはじまるが、社会進出を望む女性のための育児体制が出来ていない。 保育所と幼稚園すら官庁の縄張り争いだ。 ② 団塊の世代が60歳を迎える。 時間的余裕と知識経験があり、しかも住宅ローンや子女教育負担を終えた上質の労働力である。 この団塊の世代を力づける年金改革は官僚には出来ない。 ③ 今のまま公務員改革もせず、歳出削減をしないで推移すると2012年の基礎的収支はGDP比3.6%の赤字となり、地方債を含む公債残高は05年の780兆円から1213兆円に拡大し、名目長期金利は10%に跳ね上がり、財政破綻してしまう。 官僚は増税しか考えていない。 ④ そうだとすれば、消費税の引き上げは避けられない。 納税を重たいと感じるかは課税のやり方いかんである。 複数税率も、戻し減税もあり、工夫次第である。 年金改革の一助として、社会保険庁を民間化すべきだ。 基礎年金の国庫負担率を引き上げて、企業の拠出金を減らしてはどうか。 納税者背番号制にすれば企業の経理は縮小できる。 ⑤ 日本の金融の立ち遅れが不安である。 最後は国債増発で穴埋めできると思い込んでいるようだ。既に国債の海外売込みが始まっている。 ⑥ 2007年以降、日本基準による財務諸表ではEUで資金調達はできなくなる。 「のれん」処理問題などが残されているからだが、財務開示は不可避である。 公認会計の近代化を遅らせているのは誰か。 ⑦ 2007年ごろから経済を左右するのが中国経済である。 いま東アジア諸国では対中国輸出超過だけでなく、直接投資や証券投資の純流入高が激増し、日本の外資準備高は8445億ドル、中国、東アジア合わせて2兆ドル時代に入っている。 ドル資産がキャピタル・ロスを起したらという危惧はある。 ドル支配を漸減させる東アジア通貨の形成が急務となっている。 郵政民営化をやらずして、これに根をおろした官製国家をいかにして乗り越えられるのか。』 〜長々とほとんど全文を入力した(一部割愛)。 入力する事によって少しはその意味するところを理解できる度合いが高まるかと期待して・・ 多分、その因果関係が正しく理解できているのはやっと半分程度であろう。 ただ、戦後60年面々と政官財が一体となって築いてきた構造は冷戦構造の崩壊、それに続く経済のグローバル化の進展により、それまで日本の長所であり、強みであった旧来の仕組みが如何ともしがたい負の側面を露呈してきたと教えている一環であると指摘していることは理解できる。 そのことを一般大衆はまったく知らされもせず、自ら察しもせずに今日に至っているのであろうか。 バブル崩壊後からの14年の長きに渡る時間の経過と共に、あるいは日々の勤め・生活を通じて不満・不信・不安の感覚と感情が累積され、また負組みなどと呼ばれることによって、ハッキリと時代の様相を認識し、自分がその負組みの一つの層の中にいるのではないかとの疑念すら多くの国民が抱き始めている。 いや行き詰まり、疑いもなくその一人として自らの生を絶っている者の数は毎年3万を超えて数年の実態である。 一方、勝ち組と呼ばれている層も確実に出現してきている。 確かに新時代に通用する、ふさわしい考え方、やり方と評価できる組織、活動も散見されるが、大半はリストラという名の下での減量、切捨てはないのだろうか。 果たして勝ち組が勝ち進むだけで事は済まされるだろうか。新たな希望に満ちた時代が来るのであろうか。 負組みといわれた者の中から、再び立ち上がり光が見えてくる社会にならないことには新しい社会に変革したという事にはならないのではないのだろうかと考えます。 また、加藤学長の言っていることを批判できるほど、知識も見識もないが、どうも日本は遅れている、駄目なところばかりだ、欧米の基準に早く到達しなければと強調されているように感じてならない。 では、かの国の人々の生活ぶりや人々の満足度・幸せ度は如何なものでしょうか。 グローバル化された世界の中で、ある一定の考え方・評価されるべき基準があることは事実でしょうが、それが果たして、欧米の作り上げてきた基準がすべてなのでしょうか? かの国に人々の作り上げてきた考え方、基準、やり方こそ今問われているにではないでしょうか。 決して、今の日本が良い、このままで良いと言っているのではありません。 日本には日本の、アジアにはアジアの伝統、歴史、文化、宗教等によって築かれてきた長い歴史があります。 アジアあるいは環インド洋の伝統文化・歴史、そしてシルクロードが結んだユーラシア大陸の交流を切断・崩壊したのは欧米の力によるところである事は明白であると思います。 歴史は常に新たな文化・文明が創出されてゆくことを示し、常に変化することは免れ得ない事を教えてきましたが、いま、ルネッサンス・人間復興から産業革命を経た近代社会から現代社会にいたる現実は大きな岐路に立っているとの認識は誰しも持っているところであろうと考えます。 その岐路に立っている今、過去の歴史に学び、新たに構築される人間の営みのあり方に対し、一つのモデルを提示できる資格と責任が日本にはあると考えます。 日本のトップクラスの識者の一人・加藤学長の論文は現代日本社会の病巣(=官僚機構)を切り開き、診断し、病状を開示し、今こそ郵政民営化を実施すべきとのご宣託と思います。 こんな事を言っては見も蓋もないのですが、官僚制度・機構をどうこう言っても、彼らはことの最後の最後まで国家権力にしがみついて、吸い尽くすのではないでしょうか。 “郵政財務肥大亡国症候群” “巣くう役人・無能腐敗官僚病”とでも言うのでしょう。 このくらいのことを言って腹の虫を収めるのが庶民の鬱憤晴らしでしょうか。 が心安らぐのは、すでに天がお見通しのようです。 ほったらかしておいたら如何でしょうか。 そのほうが、彼ら自身が心配して少しは自ら改める気になるのでは???? そんな期待は夢の夢かとも感じますが・・・・・ そんな・こんな事に気を回しているよりは人様の厄介になることを少しでも少なくするように心身の健康づくりに励む事でしょうか。 これぞ、修行なりと。 |
| NO.111 平成17年1月30日 記 |
【“恋する歌音(カオン)” 歌人・佐藤 真由美
|
| 毎週気に留めて、時にはチラッと目を向け読んでいた。 恋歌の数々。 大半、昔の短歌を引き合いにだし、その解説とその短歌にまつわる思いや感じ方ををエッセイ風に語り、その短歌に返歌するようにご自分の短歌を紹介していた。 『今週は 新古今和歌集 藤原清輔 の短歌 ながらえば またこの頃や しのばれむ 憂しと見し世ぞ 今は恋しき ―生きていれば、また今の事をなつかしく思い出すだろう。 だって、あんなにつらいと思っていた昔が、今は恋しく思われるから。―と歌の意味を解説したあとに。 最初は<辛い月日も時が過ぎればなつかしい思い出に変わるのさ・・・>という流行歌のような意味だと思った。 のど元過ぎれば熱さ忘れる、くらいの。 でも、「つらい日々さえも、いつか時間がその苦しさを忘れさせてくれるのでなく<憂しと見し世ぞ>・・ 辛かったあの時代だからこそ、今は恋しく思えるのではないか。 近頃、そんな風に考え始めている。 最後に いいことが 悪いことより二個増えるように 数えている 帰り道 真由美』とあった。 〜初めてこのコラムに取り上げましたが、なんと本日が最終日であった。 何で今まで、もっと取り上げなかったのだろうかと、今頃になって悔やまれる。 なぜ、掲載しなかったのであろうか。 取り上げる気持ちの裏に、心根を読まれているように感じたこともあるし、まだこれからだなどと力んでいる自分があったこともあるように思える。 <憂しと見し世ぞ 今は恋しき> などと口にするにはまだまだ修行中なのである。 |
| 前のページはこちらからどうぞ |